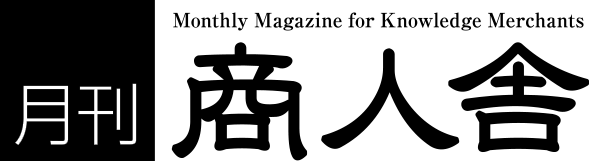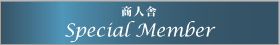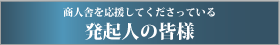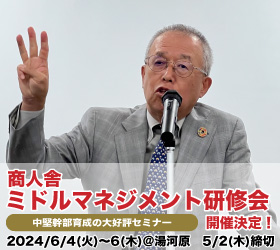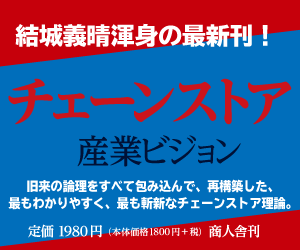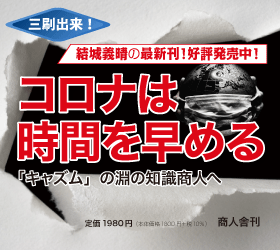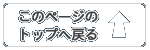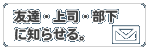9月21日、大阪は暑かった。
全国的に菓子が売れない夏だった。
菓子卸NSグループの勉強会で講演。
テーマは、
「自己革新なくして、サバイバルなし!」
白石製菓社長・白石純一郎さんには、特にお世話になった。
若い経営者の熱気ある研究会、
応援します。
今、私自身、
自分がさまざまな人たちに応援していただいている。
だから、よく分かる。
応援してもらうことの有り難さ。
私も、若い経営者、若い実務家を応援したい。
一緒に苦しみたいし、一緒に喜びたい。
その後、オール日本スーパーマーケット協会を訪問。
油座栄専務理事にご挨拶、そして懇談。
温かいおもてなし、心より感謝。
そして、同協会の応接室の『スーパーの女』のパネルの前で、
油座さんと並んでポーズ。
油座さんこそ、まさに、スーパーな女。
私が尊敬する女性経営者でもある。
油座さんなくして、この協会もない。
そして、思い出した。
伊丹十三さんの映画『スーパーの女』のことを。
1996年、6月までの数カ月のことを。
私が編集長をしていた『食品商業』は、この映画を応援した。
そして、脚本・監督の伊丹十三さんと、
アドバイザーの安土敏(荒井伸也)さんに、
誌上対談してもらった。
安土さんは、この映画の原案となった『小説スーパーマーケット』の著者。
私は、ただただ伊丹十三が、
大きな顔をしていることに圧倒された。
そして、当時の『食品商業』名物の巻頭メッセージを書いた。
今日は、その再現。
『スーパーの女』と闘おう 結城義晴
映画『スーパーの女』が生まれた。
生まれるべくして生まれた。
「価格破壊」の、あの熱病のごとき風潮への反動のように生まれた。
日本商業の歴史にとっても、
スーパーマーケットに一段の進化を促すという面でも、
とても重い意味をもつ。
なぜなら、多くの主婦たち、日本中の客たちが、
この映画を見て、
舞台となった「正直屋」の、
商品と鮮度とサービスと、
公明正大さとエンターテインメントとを、
知ることになるからだ。
その裏側をのぞいてしまうからだ。
日本中の店が、『スーパーの女』の「正直屋」と競合することになる。
日本中の経営者は、監督・伊丹十三と競争することになる。
日本中の店長は、宮本信子扮する井上花子と力量を競うことになる。
こんなことがあっただろうか。
なんと楽しい競争だろう。
なんとやり甲斐のある競争だろう。
なんと誇らしい競争だろう。
ふるい立て、立ち上がれ。
全国の「スーパーの人びと」よ。
『スーパーの女』と闘おう。
正々堂々と闘い続けよう。
この巻頭言によって始まる『食品商業1996年7月号』は、
それまでの(株)商業界48年の歴史上、
最高部数を記録した。
<結城義晴>