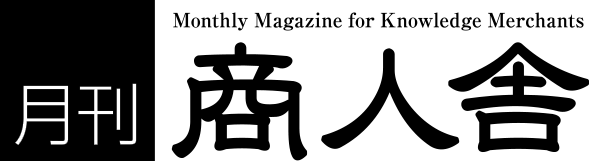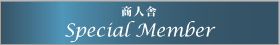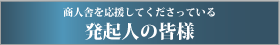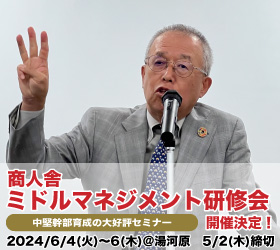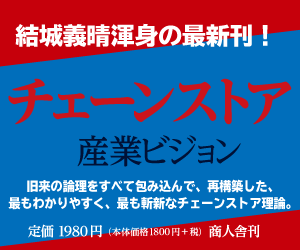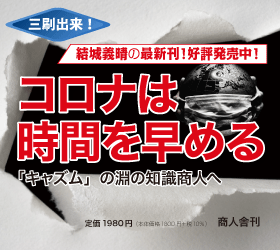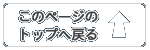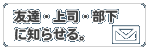朝日新聞のオピニオン欄。
いつも正面からテーマを据えて、
そのテーマに対して、
正面から語ってくれる人が登場する。
今日は「プレゼンする力」。
「聴衆に対して情報を提示し、理解・納得を得る行為」、
それがプレゼンテーション。
その能力が「プレゼンする力」。
まず鷲田清一さん。
大谷大学文学部哲学科教授。
元大阪大学総長といったほうが通りがいい。
「すらすら、なめらかに話す。
言いよどんだり詰まったりしてはダメ。
何度も練習して臨む」
それが鷲田流のプレゼンテーション。
私は講演や講義、プレゼンテーションの練習はしない。
いつだって、ぶっつけ本番。
ただし、学生時代から、
挨拶や語りに対して、
積極的であろうと努力してきた。
その意味では左翼のアジ演説も拝聴した。
「演説調・軍体調」の「であります調」も、
ちょっと研究した。
しかし、鷲田さんは、最後にはこう語る。
「言葉は世界を読み取る網のようなものです。
もやもやしている問題に言葉を与えることで、
そういうことだったのか、と腑に落ち、
見晴らしがよくなる」
「そんな確かな言葉を見つけられればいい。
口べたでもいいんです」
「腑に落ち、見晴らしがよくなる」
そんな言葉を発見するのが、
おもしろいし、やりがいがある。
プレゼンテーションの醍醐味だ。
ファーストリテイリングの柳井正さんは、
「グローバル人材に求められるのは、
人種、文化、宗教を問わず
コミュニケーションができる能力です」
これを読みつつ、
ワンアジア・コンベンションを思い出した。
柳井さんは競争と教育の在り方を指摘する。
「横並び教育は世界最悪です。
競争させなければいけない。
音楽でも趣味でも競争させる」
「競うことによって
他人とは違うことを考え、
相手に伝え、
実践するようになる」
ここで結城義晴『メッセージ』から。
少し長いけれど、一挙掲載。
「競争はあなたの仕事です」
1
あなたは、競争が好きですか。
他者と競争することに、喜びを感じられますか。
競争そのものを楽しむことができますか。
2
「店は客のためにあり」
もう何度も何度も声に出し、
心の中で繰り返してきた言葉です。
この金言の中に実は
「商売とは競争することだ」という意味が
込められています。
あなた自身、ひとりのお客だとイメージしてみてください。
あなたが住んでいる町に、レストランがあるとします。
あなたは、1軒のレストランで満足しますか。
私は満足できません。
違った種類のレストランや外食業がいくつか、
それぞれのメニューや味や価格や販促を提示しながら、
お客である私に訴えかけてくれる状態。
それを、その日の気分によって、自由に選択できる状況。
そんな環境こそが、お客である私を喜ばせるものです。
すなわち、「店が客のためにある」ことをまっとうするには、
競争がなければならないのです。
どんなにすばらしい店でも、
無競争の中では改善や改革が進みません。
競争は、店の革新を促進させるものなのです。
商業とは、正々堂々の競争をお客の目の前で
展開してみせる業(なりわい)なのだと私は思います。
お客はいつも、商業の健全な競争を歓迎しています。
商業ビジネスにとって、競争は宿命のようなものなのです。
3
ただし、気をつけねばならないことが二つあります。
第一は、競争をするといっても、お客たちから、
軽蔑されるようなものは避けなければならない、
絶対にやってはいけない、ということです。
倉本長治師は、こう書き残しています。
「競争を戦いだと思い、相手を憎んだり、
そねんだり、傷つけたりする。
まったく困ったことだ。
商売の競争はオリンピックと同じように、
また囲碁や将棋のように、
相手方を尊重し、ルールを守って実力を競うべきである」
商売のルールを守る。
相手方を尊重する。
お客から尊敬される。
そんな競争なら、喜んで参加できるはずです。
スポーツ選手は、オリンピックに出場するために
たいへんな努力を払います。
自らを鍛える日常の努力そのものが競争であり、
オリンピックに出て、勝利に向かって奮闘することも競争です。
商売でいえば、顧客を満足させること、
自らの経営の中から適正の利益を出すこと、
そのための努力をし、仕組みをつくることが、
お客から軽蔑されない競争となります。
4
第二のポイントは、
「差異性」を生み出す競争であることです。
再び、先ほどのレストランの例をイメージしてみてください。
あなたの町にレストランが3軒あったとして、
それがみんな同じようなファミリーレストランだったとします。
同じような店構えに、
同じようなメニューに、
同じような価格帯。
違いがあるといっても、微差の優劣。
これでは、お客であるあなたや私は、
うんざりしてしまいます。
総合大型スーパーや食品スーパーマーケット、
ホームセンターやファミリーレストランといった新しい業態が、
おしなべてみんな経営が苦しくなっていったのは、
全体が「微差の優劣」にこだわりすぎてしまったからなのです。
これは競争のとり違えです。
結局、価格の競争にならざるをえなくなってしまった。
競争の本質は、
同業他社との本質的な「差異性」を競うものです。
「差異性」こそが利潤を生み出すのです。
世界はものすごい勢いで標準化の方向に動いています。
ITをはじめとする情報化によって、
物流システムや交通システムの高度化による商品の移動性によって。
しかし、だからこそ、
最終顧客に商品を提供する段階での
「差異性」が求められているし、
それが決定的に効力を発揮します。
そして、この「差異性」には規模の大小は関係しません。
むしろ大企業は大企業らしさを、
中企業は中企業らしさを、
小企業は小企業らしさを出すことによって、
競争力の核となる「差異性」を生み出すことができるのです。
これを「コア・コンピタンス(核となる競争力)」といいます。
5
100円ショップ「ダイソー」を展開して、
衰えを見せない企業のように感じられる
大創産業社長の矢野博丈さんが語っています。
「20世紀は勝つか負けるかの時代だった。
しかし、21世紀は死ぬか生きるかの時代だ」
衝撃的な発言ですが、矢野さんの言葉は、
「差異性を競う競争」がさらに
企業や店の生死をかけた熾烈なレベルに
なってきたことを示しています。
ルールを守り、相手を尊重し、
しかも顧客から尊敬される競争は、
顧客とマーケットから、
さらに強い要求をつきつけられ始めたのです。
しかし、わがままで、きびしい要求が、
お客たちから発射されるからこそ、
自らのコア・コンピタンスは明確になってきます。
それが競争の良さでもあります。
さらに、現代の会社制度とは
「敗者復活」を許容する仕組みです。
競争の敗者にも、再び立ち上がるチャンスが与えられます。
会社の従業員の皆さんは、競争によって真の能力を身につけるとき、
たとえ組織は敗れたとしても、個人は立ち直ることができます。
真の競争者はむしろ飛躍することすら可能となります。
現代の競争とは、そんなものなのです。
6
むしろ、はじめから競争に参画しない者、
すなわち競争を楽しめない者には
進歩も革新も与えられず、
能力開発の余地もないことをこそ
認識すべきでしょう。
だから、私は、商人や商業ビジネスに携わる人々に対して、
こう言いたいのです。
「競争は、あなたの仕事です」
〈㈱商業界刊〉
さて日経新聞に連載記事。
タイトルは「スーパー再編(上)」
日経新聞が大好きな「業界再編の最前線」。
「スーパー」という言葉を使うが、
食品スーパーマーケットの話題。
3つの小売業の事例が出てくる。
「強力なライバルが登場したが、
売上高は前年を1割上回っている」。
北海道最大手のアークス店長。
5月にイオンの「ザ・ビッグ」がオープン。
しかし「安さでひけを取らない」。
大手メーカーのダシ(500ミリリットル)は、
希望小売価格の6割引きで安さを競う。
アークスの今年度の売上高見通しは4200億円。
「イオンのスーパー事業の1割強にすぎない。
規模で劣るアークスが大手メーカー品で低価格を実現できる秘密は、
地域でのシェアの高さにある」
私はこれを「範囲の経済」と表現している。
北海道・青森・岩手3道県のシェアは、
ユニバースやジョイスが加わって、
30%弱(スーパーの食品販売、10年度推計)。
全国チェーンのイオンのこのエリアのシェアの約2倍。
「大手食品メーカーは地域ごとに
販売ノルマなどを設けるケースが多く、
そこでシェアが高いほど価格交渉は有利」
横山清社長は「クリティカル・マス」と表現。
次は中部地区に店舗展開するバロー。
2011年度売上高は4105億円。
前年比プラス8.3%と絶好調。
ローコストオペレーションとプライベートブランドが特徴。
「18円の豆腐、48円の緑茶(500ミリリットル)などがずらり」
このプライベートブランドは、
日本のドラッグストアのほか、
米国や韓国のスーパーマ-ケットにも供給されている。
そしてここでは「規模の経済」を働かせる。
最後はヤオコーとライフコーポレーション、
その業務提携。
「首都圏での食品販売額は4000億円規模となり、
首位のイトーヨーカ堂(推計約4500億円)に一気に迫る」
23期連続増収増益&独立路線のヤオコー。
ライフスタイルアソートメントをさらに極める。
川野清巳社長の言葉。
「井の中の蛙(かわず)では生き残れない」
新しく流通担当になった記者が、
仕入れたばかりの情報を
整理した習作のような記事。
しかしよくまとまっている。
アークス、バロー、ヤオコー。
それぞれに差異性があるところが、よい。
ルールを守り、
相手を尊重し、
しかも顧客から尊敬される競争。
日本中が、そうあってほしいものだ。
<結城義晴>