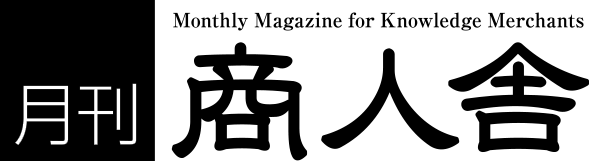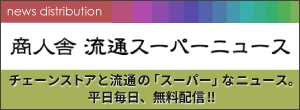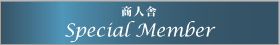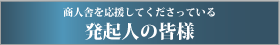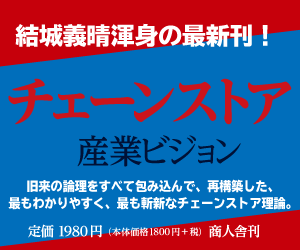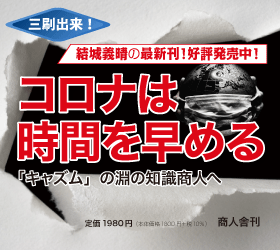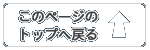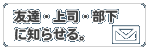毎日新聞の巻頭コラム『余録』。
「『選ぶ政治家がいない』
『誰がやっても同じ』
『どうせ世の中は良くならない』。
どこかで聞いた嘆きをもらす向きもあろうが、
『結果』は自らにふりかかる。
まず政治の底を固める有権者の1票だ」
まったくの同感。
どんなことになろうが、
私たちは選挙結果に責任を持たねばならない。
だから、
選挙に行こう!
投票しよう!
朝日新聞の巻頭コラム『天声人語』。
〈この子らに戦(いくさ)はさせじ七五三〉水野李村(りそん)。
「国を守る決意もいいけれど、
戦没者の悔しさを思い、
孫子の顔を浮かべての一票も悪くない」
憲法9条を変え、
自衛隊を国防軍にする。
そんな主張に反論する。
今日は真珠湾攻撃の日。
1941年12月8日。
それから71年経った。
国民も政治家も、
朝日、読売、毎日の大新聞も、
得体のしれないものに引きずられた。
アイデンティティを失った。
私は今日、
いつもの土曜日のごとく、
東京・池袋の立教大学。

銀杏の葉が落ちて、
もうすぐ丸裸。
それでも銀杏は天に向かって、
すっくと立っている。
午前中から結城ゼミ。
ゼミ生は全員、修士論文・調査研究レポートに邁進中。
提出日は来年1月11日。
私もこの日が実質的な正月。
それまで無呼吸泳法。
今日も個別指導。
武藤麻代さんは、
自分の研究を白板に書いて整理。
すごくいい研究が進んでいる。
全員の研究、ほんとうに楽しみだ。
私の信条は変わらない。
「邪魔をしないこと」
人間や組織や会社が伸びていく。
その障害物になったり、
方向性を捻じ曲げたりは、
絶対にしない。
指導にエゴイズムは禁物だ。
大学院生も、
会社の部下も、
指導先も。
「邪魔をしない」し、
「脱グライダー」であることを求める。
だいいち、
ひきずられつつ、
教えられたまんまをやるなんて、
生きている意味がない。
会社ならば経営している価値がない。
昨日の日経新聞の経済コラム『大機小機』。
タイトルは「外から日本を見ると」。
「自分が外国の日本経済研究者だとしよう。
自分は日本経済のかじ取りについてどう考えるだろうか」
これがコラムニスト隅田川氏のスタンス。
「第1に気になるのが財政であろう。
日本の財政は先進国中最悪の状態だ。
消費税の引き上げが決まったとはいえ、
それだけでは2020年度に基礎的財政収支を黒字化」できない。
「このままでは、いずれ
金利の暴騰やインフレなどの大混乱をもたらしかねない」。
「ところが、現実の日本では、選挙があっても、
消費税引き上げ後の財政再建について議論する政党は皆無である」。
「第2に環太平洋経済連携協定への対応ぶり」
「今後は成長著しいアジア地域との連携を
強化していくことがほぼ必然の対応であり、
TPPのような機会があったら、
日本は真っ先にこれに加入し、
これをテコに更なる発展を目指すはずだと考えるだろう」
「ところが、日本ではTPP交渉への参加をめぐって
延々と議論が繰り返され、一向に明確な方針が出ない」
「第3に人口変化への対応が重要」
「先進国中で高齢化比率が最も高く、
生産年齢(15~64歳層)比率が最も低い国となる」
「生産年齢人口が減れば、
労働力不足が成長を制約するだろうし、
負担者である働く層が減り、
受益者である高齢者層が増えれば、
現在のような年金・医療・介護などの社会保障システムを
維持していくことは難しくなる」
「ところが日本では、
外国人労働力の受け入れには消極的であり、
社会保障給付の抑制策はほとんど実行されていない」
コラムニストは、『外から日本を見るとどう考えるか』の発想を勧める。
つまり「自己客観化」の方法である。
この国への警告はそのまま、
人間に当てはまる。
会社にも当てはまるし、
店にも事業部にも適用できる。
私たちは「自立」していなければならない。
つまり自分で立って、自分で物事を行うことだ。
さらに私たちは「自律」しなければならない。
自らをコントロールすること。
「自立と自律」。
それが自己客観化のために必要だ。
そのために必須のことは、
「外から自分を見て、考えること」だ。
外部の人に助言を求めるもよし、
ベンチマークする企業や店を見るもよし。
海外を訪れるもよし。
ただし、助言を求める外の人や、
ベンチマークする対象、
海外の企業や店は、
よく吟味されていなければいけない。
これを間違えると、
反対の方向に行ってしまう。
そしてその時、
「自立と自律」が不可欠だ。
私の言葉でいえば、
「脱グライダー」であること。
グライダーのように、
ロープで引っ張ってもらい、
エンジンなしで空を浮遊することは、
いま、最も避けなければいけない愚行だ。
なぜならば今こそ、
「ポジショニング戦略」が、
不可欠だからである。
ポジショニングとは、
自己客観化なしにできるものではない。
では、良い週末を。
〈結城義晴〉