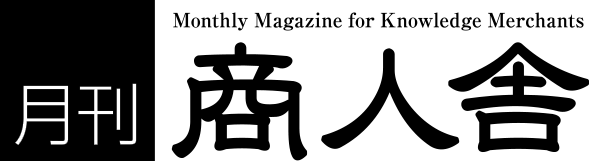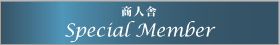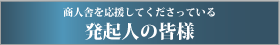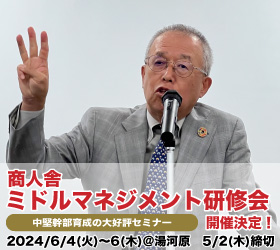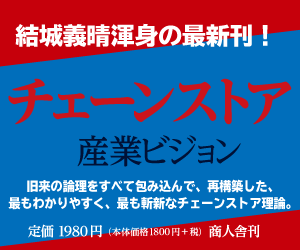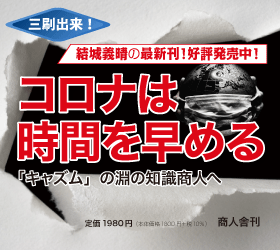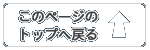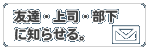昨夜は満90歳の母の誕生祝い。

蝋燭1本が30年分。
おめでたい。
そして今日は、午後から、
新幹線ひかり号。
神奈川の丹沢山系も雪をかぶっている。

そして富士の山は、
このあたりにあるはず。

滋賀県に入ると、伊吹山。

米原で乗り換えて、
彦根駅前の平和堂アルプラザ彦根。

ホテルからは彦根城がちょっとだけ見える。
夜は平和堂の幹部のみなさんと会食。
専務取締役営業統括本部長の平松正嗣さん、
取締役商品本部長の田淵寿さんと、
取締役店舗営業本部長の福島繁さん。
最後は平松さんと握手。

さて日経新聞『私の履歴書』
大山健太郎さんの巻が佳境に入っている。
㈱アイリスオーヤマ社長。
今日は第16回で「問屋の壁」
東大阪で小さな工場を引き継いだ。
業務用プラスティック製品の製造業。
その商才でめきめきと業績を伸ばして、
宮城県に新工場を移し、
東大阪の工場閉鎖を断行し、
さらに消費財メーカーへと業態転換をした。
マーケティング感覚にも優れ、
次々にヒット商品を開発する。
さらに1980年には、
消費者向け園芸用品市場に進出。
このとき、頭を悩ませたのが、
「問屋とのつきあい方」だった。
「当社は地方に本拠を置き
名前も売れていない会社だった。
しかも今まで問屋が扱ったことのない
提案型の商品を作る。
彼らには売れるかどうか見当がつかない」
「仕方なく当社の営業が
問屋の担当者に同行し
小売店のバイヤーに売り込んだ」
「取引量が拡大すると
問屋が当社の売り込みに
ブレーキをかけ始めた」
「仕入れを絞った商品が
予想外に売れると欠品が起き、
バイヤーから問屋にクレームが来る」
「しかしそれよりも問屋は、
仕入れた商品が予測より売れず
過剰在庫になる方を怖がった」
「売れ残りを恐れた問屋が
当社への発注を控え、
需要のピークの春先に
十分な量の商品が店頭に並ばない」
「問屋の壁」
1968年の林周二著『流通革命』
林が糾弾したのは、
こういった古い問屋だった。
大山さんは、やむなく、
「新興勢力のホームセンターとの間で
問屋を通さず直接取引を始めた」
当時はホームセンター業態の台頭期。
「陳列や品出し、商品への値付け、
改装や新店の開店準備などの作業を
問屋に依存していた」
取引量が拡大すると、
大山さんにもそうした要望が増えていった。
「私は二者択一を迫られた。
問屋経由で商品を供給する
普通のやり方に戻すか。
または自社で問屋の機能を持つか」
社内の意見の大勢は、
「他のメーカーと同様、すべて問屋を通そう」
大山さんは述懐する。
「私はあえて難しい道を選んだ」
「今後はベンダー機能も自社で持つ」
「問屋外しだ」
「商道徳に欠ける」
業界からは罵詈雑言。
怒った問屋から大量の返品。
このころ私は㈱商業界で、
大山さんを取材したことがある。
私はアイリスオーヤマを、
イノベーターであると見ていた。
「得意先である小売業が味方である限り、
勝負を決めるのはマーケットニーズだけだ
と私は楽観的だった」
「小売店への品ぞろえ提案や
売り場作りも請け負う。
もちろんプラスチック製品だけでは足りず、
素材の違う売れ筋商品の開発も
しなければならない」
「毎回の配送も
ケース単位ではなく単品になる。
物流の仕組みや社員の意識を
根本的に変える必要がある」
こうして大山健太郎によって、
「メーカーベンダー」への挑戦が始まった。
例のないビジネスモデル、
つまりイノベーターだった。
今日はもうひとつの話。
糸井重里の『ほぼ日』
巻頭言は「今日のダーリン」で、
糸井が「チーム」について書いている。
「あるチームが育っていくときには、
メンバーそれぞれの力だけでなく、
メンバーの間の『関係』までも育っていく」
実にいい。
「地方でやってきたバンドが、
全国で活躍する場合、
特別にスター性のあるひとりが
目立つことはあっても、
『それ以外』とか
言われそうな他のメンバーも、
変わらずにやっていくことが多い」
ビートルズがそうだった。
甲斐バンドも海援隊も、
オフコースも。
「連続テレビドラマなどでも、
無名の役者を含んだ
スタート時からのキャスティングが、
そのまま成長していくことが多い」
「おおいにヒットしたときなど、
映画化されたりするが、
そういう場合に、
予算が余計についたからといって、
スターを加えたりすることも
わるくはないけれど、
できるだけそのままの配役、
同じメンバーでやれたほうが
おもしろくなるように思う」
糸井さんの経験からの話だけれど、
実にマネジメントの真理だ。
「朝のドラマの『あさが来た』なんかの場合、
家族や昔からの店のメンバーが、
チームの核になってる」
そして、これが正しい。
「知識や経験の豊かな専門の人で固めても、
『関係』が成熟してこないと、
どうしょうもないのだ」
「昔だったら
工場を建てるくらいの覚悟で、
人を入れる」
糸井さんは、こう言う。
アイリスオーヤマの大山さんと同じだ。
「ひとりひとりの人に、
基本的に『関係』はついてこない」
ただし「ほぼ日」というチームの場合、
「まだ会ってなかったメンバー」だったりする。
「つまり、読者だったり、
買い物をしてくれてたり、
イベントに参加していたり、
つまり、外にいるけど
『気持ちはメンバー』みたいな人がいて、
そういう人が参加してきてくれることが多い」
「こういう場合は、
『関係』も半分できていたりする。
これは、どっちの立場でも、
とてもありがたいことだ」
商人舎もまったく同じ。
毎日更新宣言ブログの読者、
月刊『商人舎』や商人舎magazineの読者。
セミナーへの参加者、
海外研修会の受講者。
大学院の結城ゼミ生たち。
コーネル・ジャパンのメンバーたち。
つまり知識商人の関係。
米国のホールフーズやトレーダー・ジョーは、
こういった「関係」が出来上がった人材が、
どんどん会社に入ってくる。
だから、「即戦力」になる。
特にホールフーズは、
「チームマネジメント」を採用している。
店舗や部門のチーム、
商品部の中のチーム、
会社の役員会ボードチーム。
野球やサッカーのチーム。
すべてに通ずる。
「あるチームが育っていくときには、
メンバーそれぞれの力だけでなく、
メンバーの間の『関係』までも育っていく」
平和堂のボードも店舗も、
今、そんな感じだ。
平松さんに、それを話した。
「あるチームが育っていくときには、
メンバーそれぞれの力だけでなく、
メンバーの間の『関係』までも育っていく」
そしてこんなチームこそが、
イノベーションを起こす。
実に正しい。
私はそんな知識商人のチームを、
たくさん育てたい。
〈結城義晴〉