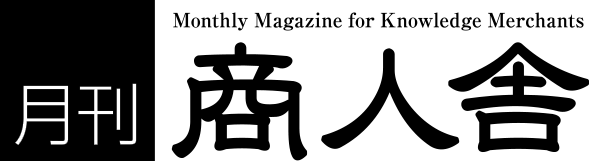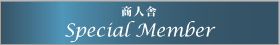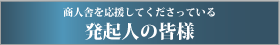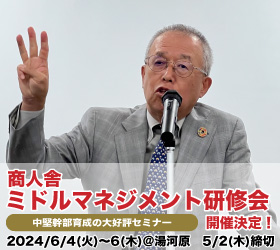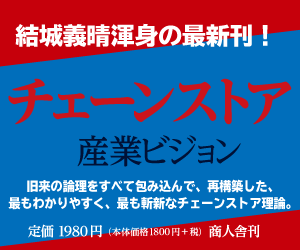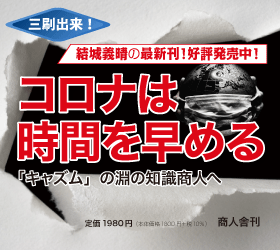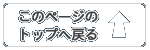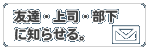「雪と桜とブイヨンと。」
3月21日午後3時16分、
糸井重里さんの愛犬ブイヨンが死んだ。
「病院に向かう途中の桜並木に、
雪が降りかかるという
なんともめずらしい春分の日に、
家人の腕のなかで眠りながら
旅立ちました」
私は2年前の1月4日に、
ジジを亡くした。
糸井さんの気持ち、わかる。
何も言うまい。
ただ、幸せだっただろうと思う。
合掌。
そのブイヨンが逝った今年の桜。

横浜商人舎オフィスの遊歩道も、
とてもいい季節。

春の雪しきりに降りて止みにけり
〈加舎 白雄〉
今日は朝から、前川智範さん来社。
第一屋製パン(株)代表取締役社長。

私は3年前から、
同社社外取締役。
いくつかの報告と、
様々な問題に対する議論。
がんばってほしい。
そして夕方には、
商人舎Web会議。

いつものメンバーが参集して、
実に建設的な提案ばかり。
Webの世界は激しく変化している。
それを実務として体験し、
学習することができる。
こんなにいい勉強はない。
学びつつ、仕事ができる。
さて、日経新聞電子版。
「経営者ブログ」
高原豪久ユニ・チャーム社長。
タイトルは、
「三手の読み」の先を読む思考術

高原さんは重大な問題提起をする。
「日系企業は、
欧米の同業に比べて
収益性が低い」との指摘がある。
高原さんはその要因を、
「過剰品質」に求める。
そんなことを表明していいのかと、
ドキドキしてしまう。
「商品やサービスに対する消費者の期待」
これは常に高まっていく。
「しかし、
企業が開発した新技術や機能革新によって
ある時から
商品やサービスが提供する価値が
消費者の期待値を飛び越して、
あまりにも先へ進化してしまう」
「期待値を過度に超えた新技術・機能革新」
これを高原さんは「過剰品質」という。
それが発生した時点から、消費者は、
その商品やサービスの価値の進化に、
「あまり反応しなくなる」
パソコンや携帯電話がよい例。
ある商品が世の中に出始めたころは、
消費者は高機能や多機能を要望する。
しかし、その商品が、
ほとんどの世帯や個人に浸透すると、
「頻繁に使う機能に絞り、
シンプルで使い勝手の良い商品を
求める消費者が増えています」
「今以上に機能を高めたり、
できる事を増やしたりしても、
消費者は興味を示しませんし、
開発コストを反映した
高い価格では買わないでしょう」
まさにコモディティ化現象である。
そこで、その商品は、
「消費者の期待にミートしていない
『過剰品質』」となる。
「その市場やカテゴリーそのものが、
消費者の頭の中で『過剰品質』と
認識された状態では、
新たな技術を投入し、
プロの目から見れば
『機能的に進化した新製品』だとしても、
消費者は割高な対価を支払ってまで、
その新製品を買ってはくれません」
クレイトン・クリステンセンが、
「イノベーションのジレンマ」で指摘した。
「企業は、
その新製品を投入するために
かかった費用を短期間で
手っ取り早く取り返すため、
生産設備を稼働させようとして
莫大な販促費用をかけ、
不毛な価格競争へ飛び込んでいきます」
これがまた、
コモディティ化を促進させてしまう。
「結果として、
開発にかかった費用はそのままに、
新たに費やした膨大な販促費によって
利益率がさらに低下する」
高原さんは推察する。
メーカーと消費者の間に、
「意識のズレ」「ボタンの掛け違い」
が生じて、それが、
日系企業の「低収益構造」になっている。
しかしこのコモディティ化現象に対して、
小売業は一足早く発想を転換し、
プライベートブランドに力を入れた。
これも高原さんの見方だ。
PB商品の展開は、
「商品を自社開発し、
ローコストの調達網を整備し、
常時低価格を訴求」して、
「利ざやの大きさで稼ぐ」考え方。
ウォルマートに象徴される経営戦略だ。
しかし「従来の日系小売業の多く」は、
「回転率で稼ぐスタイル」
が主流だった。
この従来型小売業に対して、
チェーンストアのコンセプトは、
まさにアンチテーゼだった。
高原さんは述懐する。
「しかし、この発想の転換は
容易ではありません」
「日本の消費者は独特だ」との思い込みが、
「我々日本のビジネス・パーソンには
染みついているからです」
ここからが正直な発言だ。
暗黙のうちに考えている。
「日本の消費者は変化を好み、
新製品が好きだ」
「商品の鮮度や品質に厳しい」
これを全く否定することもないとは思う。
しかし、この暗黙の了解に従って、
日本のメーカーは、
「消費者からの多様な要求に対応」して、
「次々に新製品を投入」し、
「多様なライン・バリエーション」を、
構築し、展開してきた。
日本の流通と日本のメーカーが、
協働で作り出してきた方法論、つまり、
「変化率で勝負する」やり方。
「多くの日系企業は、
変化率で勝負する方法で
グローバル競争を戦っています」
もちろん、高原さんも、
全面否定はしない。
「変化率で勝負するという得意技は
これからも主軸におくべきだと思います」
「得意技を封印して勝てるほど、
グローバルでの競争は甘くない」
そこで最後の提案。
「変化率で勝負するという得意技に
利ざやで勝負する新たな技を習得し、
合わせ技にしなければ勝てない、
勝ち続けられないと思います」
その通り。
「日本の流通や消費者は独特である」
この固定観念に縛られてはいけない。
「日本で成功すると同時に、
海外でも通用する」
これを前提に戦略開発する必要がある。
従来の考え方をテーゼとする。
「変化率で勝負するという得意技」だ。
それに対するアンチテーゼが、
「利ざやで勝負するという新たな技」
そして両者をアウフヘーベンして、
ジンテーゼを導き出す。
それが高原さんの「三手の先を読む法」
素晴らしい。
しかし、私はいつも言うけれど、
三井高利の「店前現金無掛値」は、
欧米よりもずっと早い1673年の、
「利ざやで勝負する法」だった。
クレイトン・クリステンセンも、
その主張の「破壊的イノベーション」に、
類似したジンテーゼを見出している。
もちろん、中小ローカルの日本企業は、
「変化率で勝負する法」で、
生き残っていくこともできる。
悲観することはない。
念のために。
〈結城義晴〉