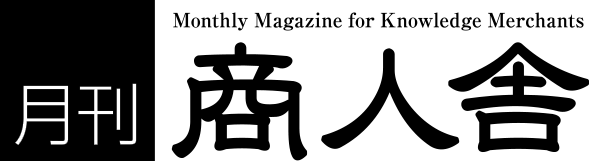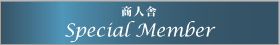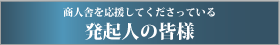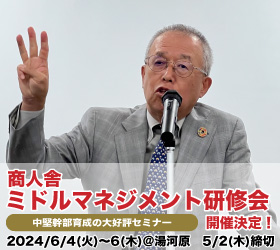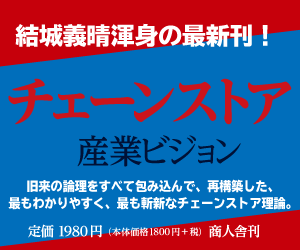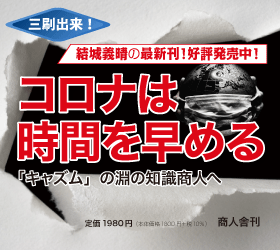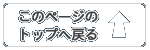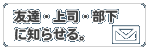ドナルド・トランプ大統領が、
ヒドロキシクロロキンを、
毎日、服用している。

この薬は抗マラリア剤であり、
マラリアの治療や予防に用いられる。
投与された症例から報告も多い。
重篤な、生命を脅かす副作用がある。
失神、心停止、突然死、心筋症、
さらに網膜症などなど。
ただのMr.トランプならば、
あんたの勝手でしょ! で、
済むかもしれない。
しかしプレジデントとなると、
万が一、副作用が出たら、
一気に国家の危機がやって来る。
喩えは悪いかもしれないが、
テロリストをホワイトハウスに、
招き入れるようなものだ。
誰かすぐに止めさせられないのか。
大統領とはそんなにも裸の王様なのか。
もちろん当人の無知蒙昧ぶりは、
これまでも何度も報じられている。
コロナ治療法として、
「紫外線か非常に強い光を体内に当ててみてはどうか」
「消毒液を注射してみたらどうか」
「興味深いと思う」
驚くべき大統領だ。
日経新聞「大機小機」
コラムニストは辛口の一直さん。
安倍政権支える「自発的隷従」
「39県の緊急事態宣言が解除され、
政府の新型コロナ対策は
第2段階に入ったが、
横浜市の筆者宅には
いまだにマスクは届かず、
10万円一律給付の便りもない」
横浜市の拙宅にも、
どちらも届かない。
「これは政府の不手際を示す
ささやかな一例にすぎないが、
独りよがりの政策決定、
行政の緊張感欠如、
強権的な政策遂行など、
このところ安倍長期政権の問題点が
鮮明になってきているように思う」
同感。
「今回の検察庁法改正のごり押しは
最近の典型例であろう」
同感。
「それでも政権交代を求める強力な勢力は
どこからも現れてこない」
なぜだろうか。
ここで一直氏は、
「自発的隷従論」を持ち出す。
エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ著。
(西谷修監修・山上浩嗣訳、筑摩書房)
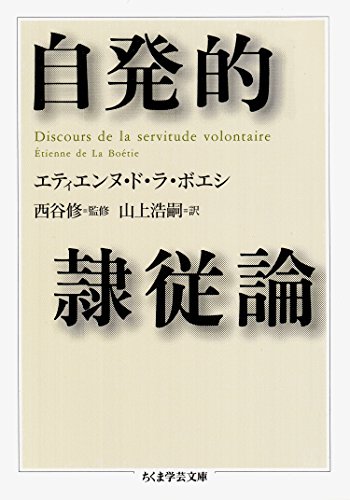
この本の著者は16世紀のフランス人で、
有名な思想家モンテーニュの親友だった。
なぜ人々は権力者に従うのか。
「彼の論理によると、
人々は強制されて従うのではなく、
自発的に従うのである」
その理由は、
「自分が得をするからだ」
なるほど。
「まず数人が権力者の信頼を得る。
この数人は権力者に尽くし、
それによって甘い汁を吸う。
この数人のそれぞれが、
甘い汁を吸う人間を数人抱える」
「この連鎖が続いて
圧制者の権力システムができあがる」
会社組織にも、団体組織にも、
このメカニズムが働くことがある。
いや会社や団体こそ、
この構造で動くことが多い。
一直氏はこの自発的隷従論を、
今の日本の政治に当てはめる。
まず「官僚」。
「2014年に、
安倍内閣の下で内閣人事局が発足、
審議官以上の高級官僚の人事が
官邸主導で行われることになった。
これにより官僚の自発的隷従システムが
完成したといってよい」
森友問題の官僚の忖度(そんたく)行為も、
加計問題や「桜を見る会」の役人たちの動きも
ここから発生する。
そして政治家も。
「実は政権与党の自民党の内部でも、
同様の行動原理が働いているのではないか」
「小選挙区制となって、
派閥はなくなったといわれる」
「かつては内閣の運営に問題が出ると、
自民党内部の派閥の有力者から
政権批判が出て、首相が交代する
というのが普通だった」
コラムニスト。
「こうした与党内部の自浄機能が消えうせている」
そして最後に、
「われわれ国民も、
自発的隷従から
自由な立場にいるのかどうか。
一人一人、真剣に問い直してみたい」
私も思う。
そのためには、
自分が属する会社において、
自分が属する部署において、
自分が属する団体において、
自発的隷従から自由でいるかどうか。
それをまず、問い直してみることだ。
アメリカ合衆国の政府や与党共和党でも、
この自発的隷従現象が起こっている。
だからプレジデント・トランプは、
誰に止められることもなく、
平気でヒドロキシクロロキンを飲んでいる。
自発的隷従が起こると、
隷属する者は、
隷属させられる者に対して、
意外なほど無責任だからである。
会社における自発的隷従を、
安土敏さんは、
「社畜」と呼んだ。
商売における自発的隷従を、
結城義晴は、
「グライダー商人」と言う。
ラ・ボエシは、
「なぜ、人は自由を欲さないのか」
という問いに解を与えている。
「自由は欲するだけで、
得られるから」
自由はだれでも、どこでも、
手に入れようと思えば得られる。
獲得があまりにたやすいから、
逆に人々は自由を欲しない。
パラドックス。
ラ・ボエシはこの本の最後に語る。
「圧政者とその共謀者に対する格別の罰を、
神が来世で用意してくださっていると、
私は確信している」
「私はまちがっていないだろう。
圧政ほど、完全に寛大で善なる神に
反するものはないのだから」
最後に日経新聞の最終面「私の履歴書」
今月は女優の岸恵子さん。
コロナ・パンデミックのなかでも、
読める。
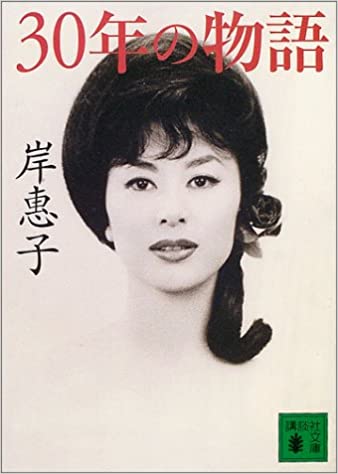
「君の名」「忘れえぬ慕情」「雪国」など、
女優としての地位を確立していたが、
フランス人監督のイヴ・シァンピと、
結婚するためにパリへと旅立つ。
25歳の1957年。
「女優としての私、祖国、両親、
愛してきたすべてのものへの決別」
そのとき、心に刻んだのが、
夫となるシャンピの言葉。
「人の一生には何度か
二者択一の時がある」
「卵を割らなければ
オムレツは作れない」
「オムレツは食べたいけれど
卵を割りたくないという未練がましさは
私にはなかった」
自由になるとは、
自ら卵を割ることだ。
欲するだけで、
誰にでもできる。
〈結城義晴〉