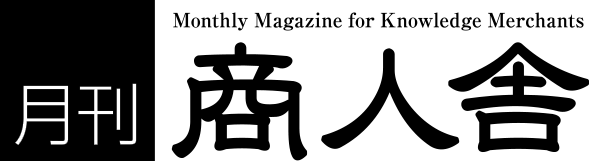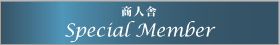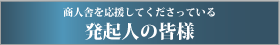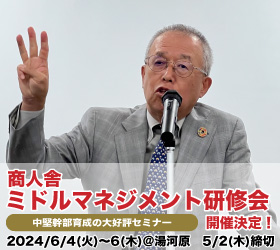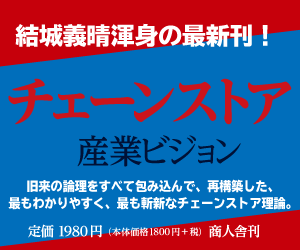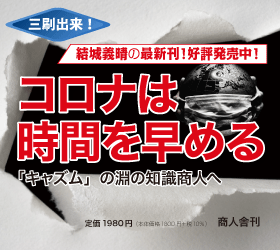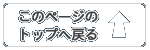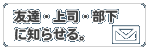日経新聞の「私の履歴書」
今月は小野寺正さん。
KDDI㈱相談役、72歳。
はじめは日本電信電話公社に入って、
それから不退転の転職。
やがてKDDIのトップとなる。
菅義偉総理が河野太郎大臣を起用して、
「聖域なき行革」を推進しようとする。
そのタイミングで、
小野寺正さんを取り上げた。
日経の「ジャーナリズム感覚」。
まったくの偶然ではないだろう。
政権への「忖度」はない。
連載を組むには準備期間が必要だからだ。
電電公社は1985年に民営化されて、
日本電信電話㈱(NTT)に変わる。
その年、小野寺さんは、
京セラ㈱の稲盛和夫さんが設立した、
第二電電企画㈱に転職する。
さらにこの第二電電(DDI)と、
トヨタ自動車のKDDなどが統合して、
KDDIとなって、NTTに対峙する。
小野寺さんは2001年に、
そのKDDI社長に就任する。
小野寺さんは宮城県仙台市生まれ。
父は宮城県庁の職員だった。
仙台第二高等学校から東北大学工学部。
そして「電電公社」に入る。

その小野寺さんの電電公社の時代に、
いわゆる「土光臨調」が発足した。
政府諮問機関の「第2次臨時行政調査会」。
土光敏夫さんが会長を務めた。
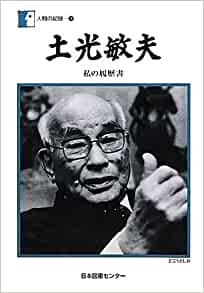
土光さんはもともとはエンジニアだ。
石川島播磨重工業の社長から、
東芝の社長・会長を歴任、
経済団体連合会会長に就任し、
「ミスター合理化」と呼ばれた。
「土光臨調」は1981年に設置されて、
1983年に解散したが、
「増税なき財政再建」を掲げて、
三公社の民営化などを推進した。
この1981年、
電電公社の大改革のために、
真藤恒(しんとうひさし)さんが、
総裁として送り込まれた。
真藤さんは石川島播磨重工業の再建で、
辣腕を振るった経営者である。
もちろん土光さんが信頼する後輩だ。
電電公社の最後の総裁。
NTTの初代社長。
こちらは「ドクター合理化」と呼ばれた。

その電電公社総裁となった真藤さんは、
“課金”や”加入者”といった言葉を
「電電語」と名づけて忌み嫌った。
課金は電話代の使用料金を「課する」こと。
その使用料も「課金」という。
「加入者」は当時、電話に加入した人。
国が経営する公社は独占事業体である。
「加入者」に「課金」して、
収益を得た。
小野寺さんの述懐。
「私も末席に連なったある会議で
真藤さんが突然激怒したのを目にして、
驚いた覚えがある」
真藤さんは「加入者」のことを、
「なぜ”お客様”と言わないんだ」
と叱責した。
小野寺さん。
「ただ私の肌感覚でいえば、
真藤さんの改革への熱意は、
電電公社に十分浸透しなかった」
「あれから40年近くたつが、今もNTTは、
加入者という電電語を使い続けている」
「三公社」と言われた。
国が経営する事業体。
日本専売公社。
日本電信電話公社。
日本国有鉄道。
いずれも中曽根康弘内閣時代に、
民営化されてJT、NTT、JRとなった。
アルファベットで象徴される会社。
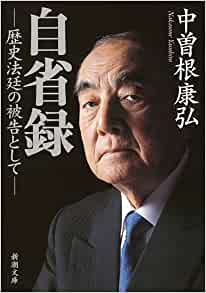
中曽根さんはすごい総理だった。
公社に決定的に欠落していたのが、
「お客様」の視点であり、
「お客様」の発想だ。
真藤さんはそれを払拭しようとした。
日本の官僚は「公僕」と呼ばれる。
その役所や官僚が、
国民を「お客様」と見たら、
ずいぶん変わるのだろう。
もちろん小売業やサービス業は、
その視点や発想を失ったら、
瞬く間に自壊する。
巨大化した小売業組織も、
茹でガエルとなったら、
「土光臨調」が必要になる。
巨大化しないまでも、
「中小企業の大企業病」となったら、
「ミスター合理化」や「ドクター合理化」が、
求められる。
しかしそれも古いやり方では、
成就はしない。
土光さんの「モーレツ経営」も、
東芝では失敗し、
真藤さんも電電公社の体質まで、
変えることはできなかった。
だから最後に、
ブレーズ・パスカル。
鹿島茂編訳『パンセ抄』から。

「人を効果的にたしなめ、
その人が誤っていることを教えるには、
その人がどの方向から、
ものごとを見ているかを
しっかりと見極めなければならない」
「というのも、
その人が見ている方向からは、
ものごとはたしかに真に見えるからだ」
「そして、それが真に見えることを、
認めてやる必要がある」
ここがパスカルの真骨頂。
「しかし、同時に、
別の方向から見ると誤っている事実を、
発見させてやらなければならない」
「そうすれば、その人は満足するだろう」
人間の心理。
「というのも、
自分が誤っていたのではなく、
全方向的に見入る術(すべ)を
欠いていたにすぎないと
気づくはずだからだ」
ここで人間の本質を突く。
「人は、全方向的に見ることができない
と言われても腹を立てないが、
誤っているとは言われたくないものである」
激怒して改革を唱えても、
すぐには改革は成就しない。
別の方向から見ると誤っている。
その事実を発見させてやることだ。
パスカルは鋭い。
〈結城義晴〉