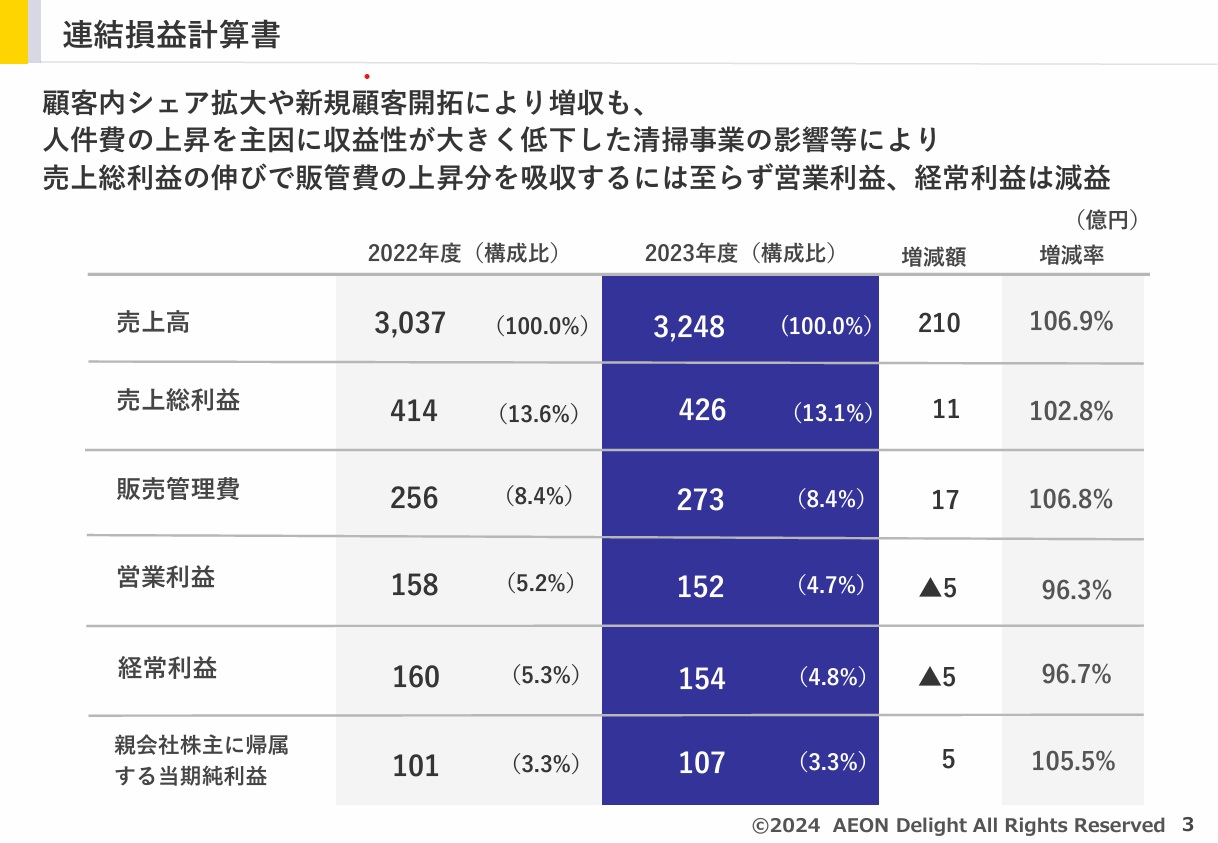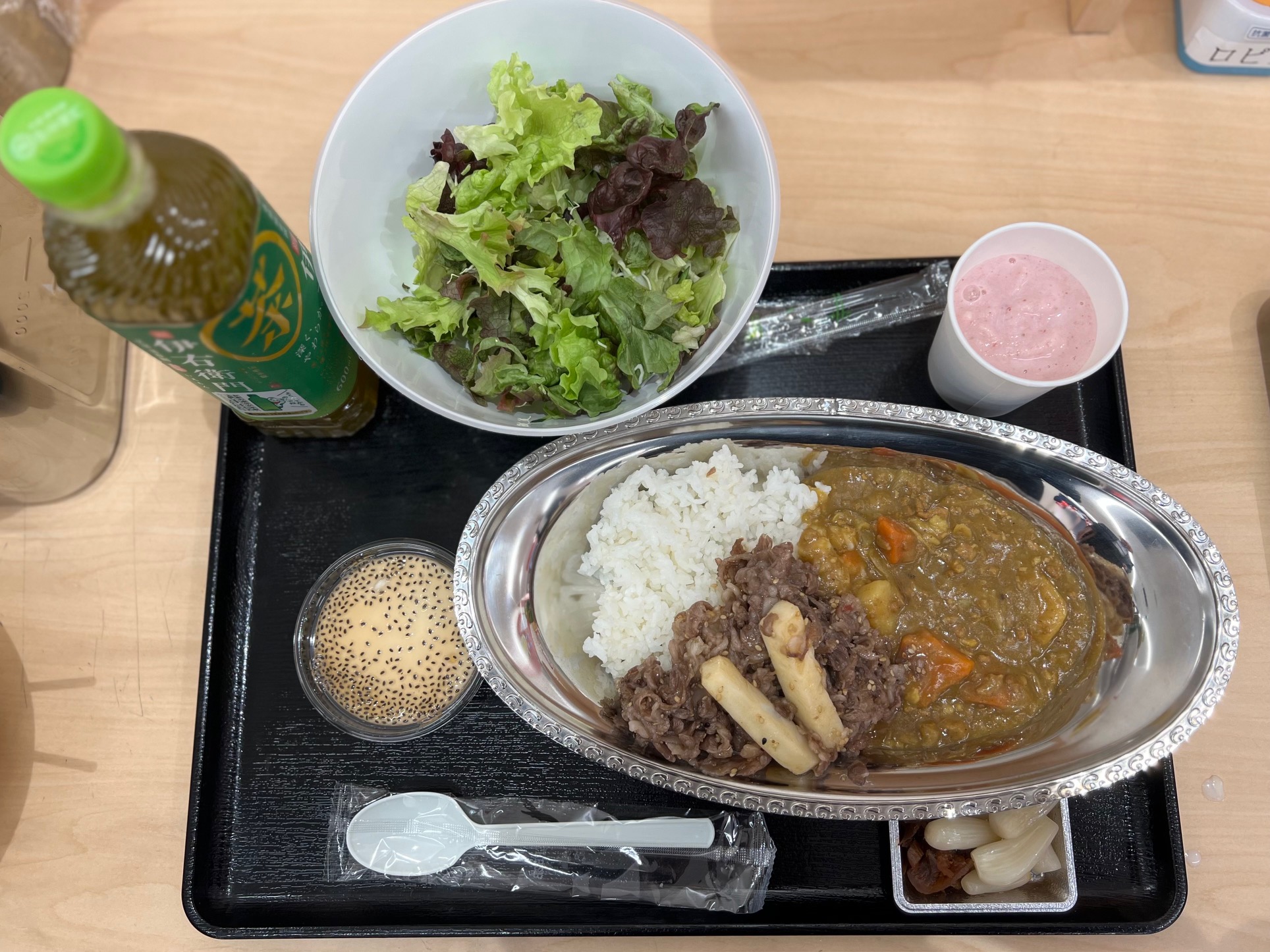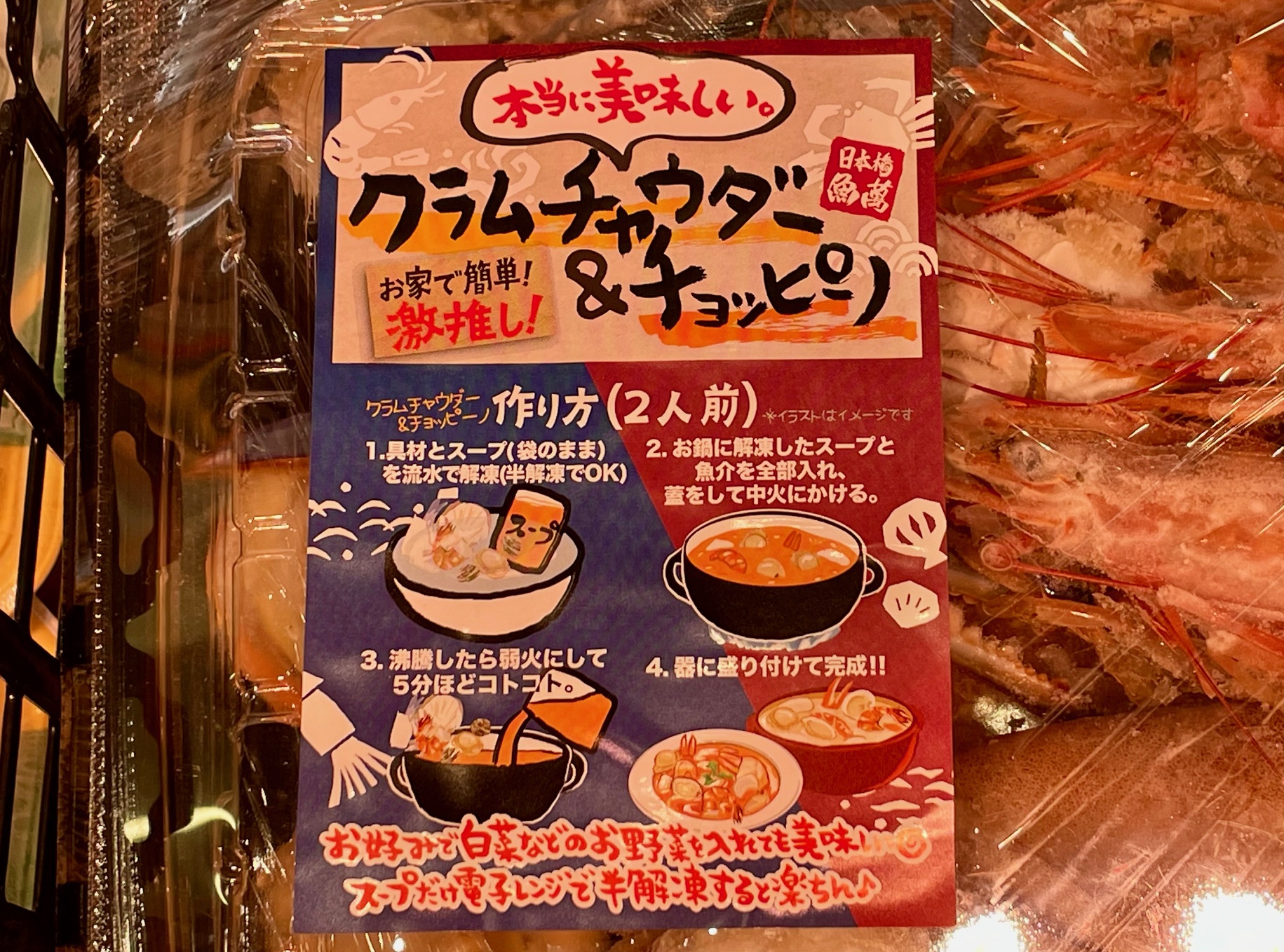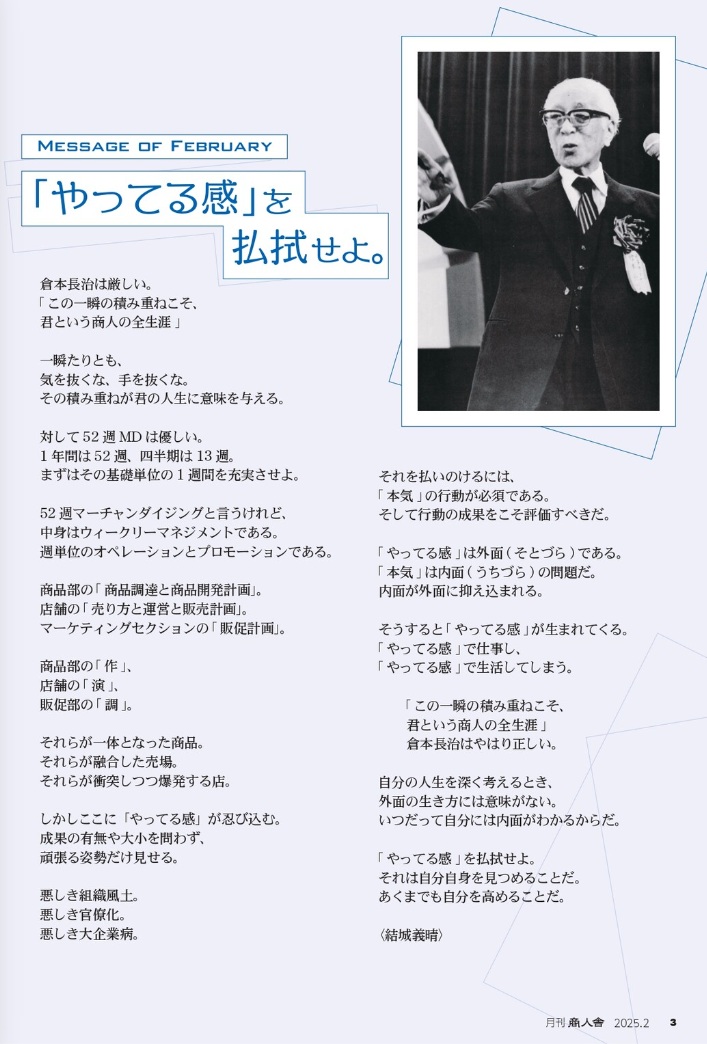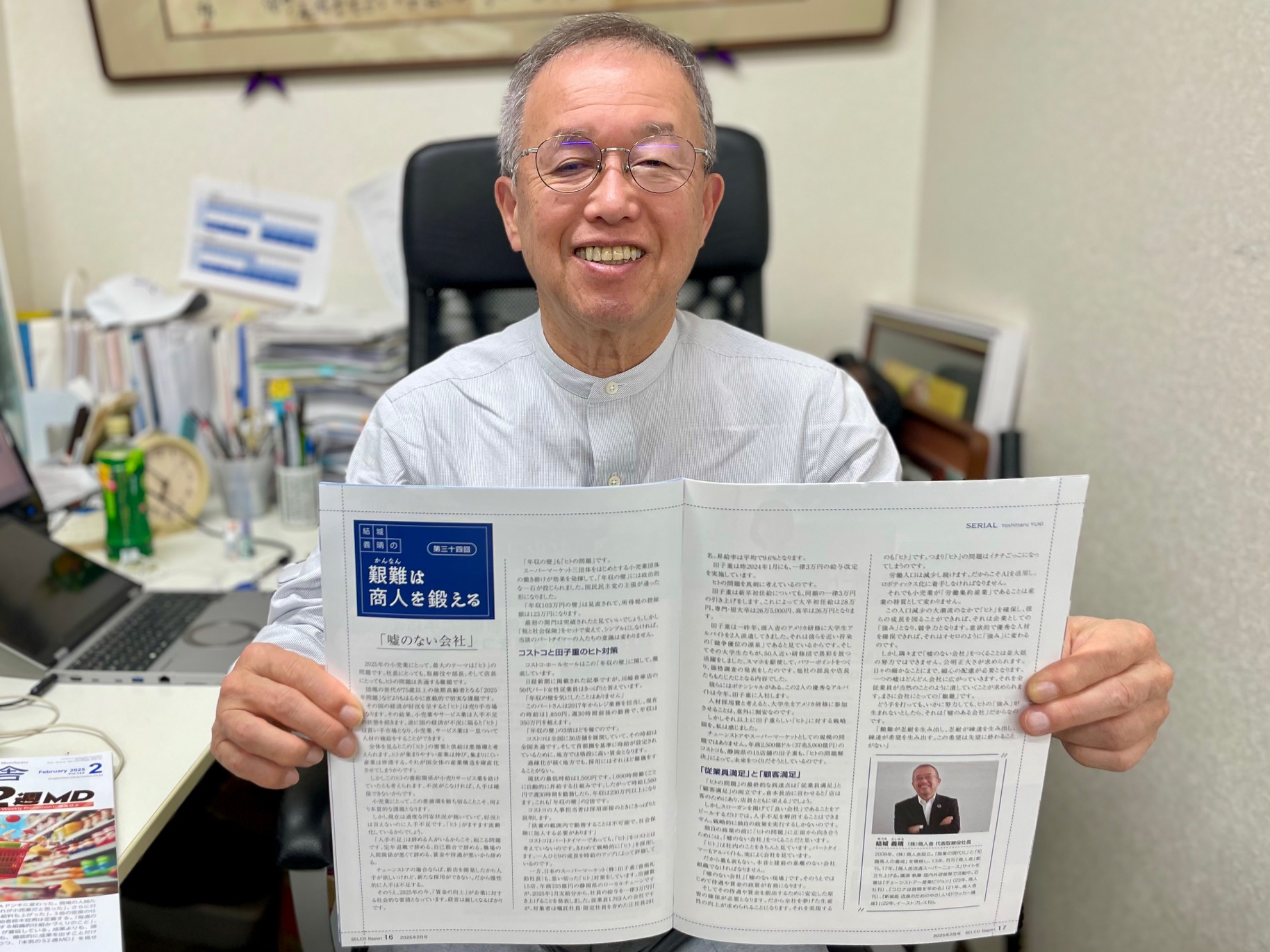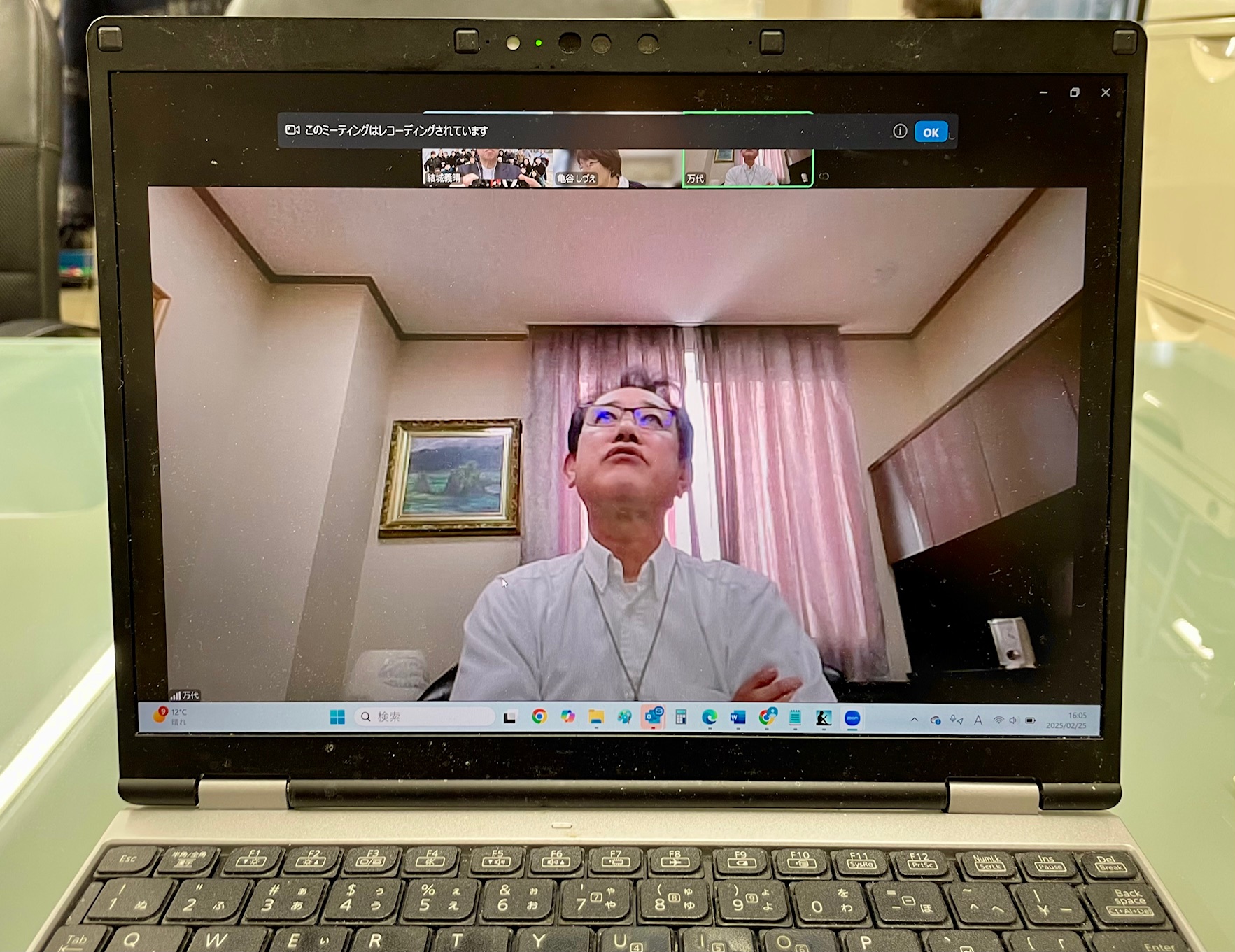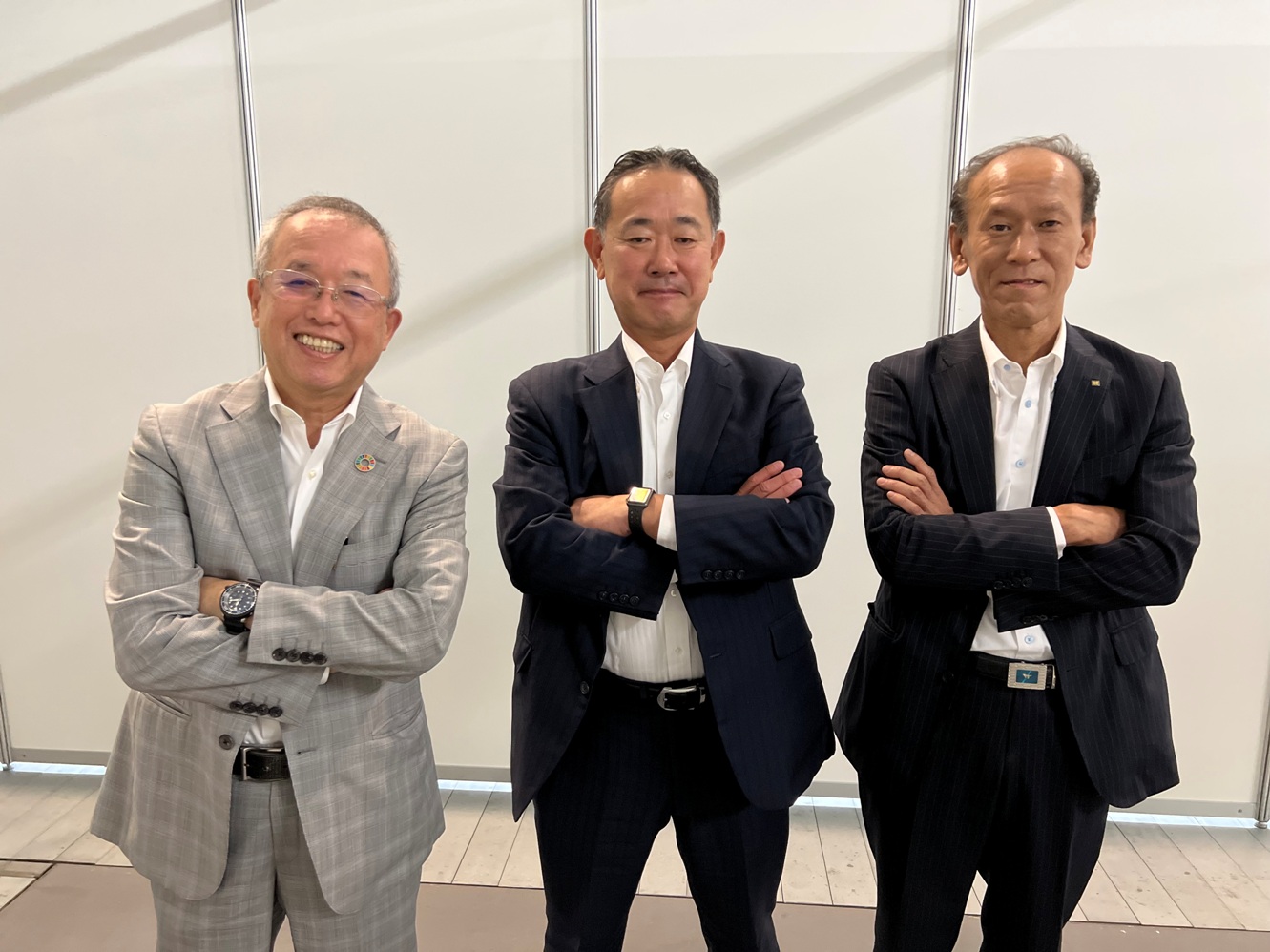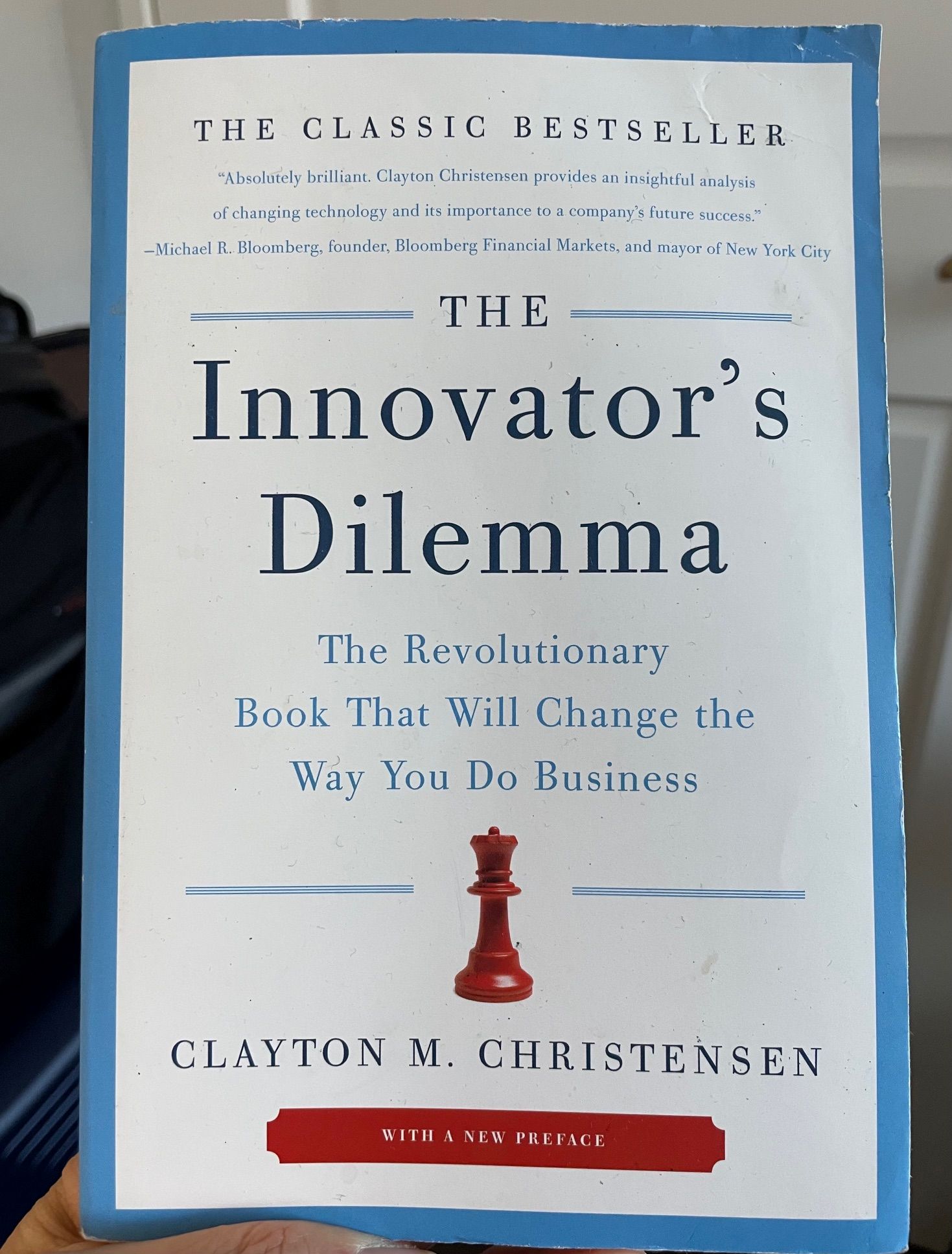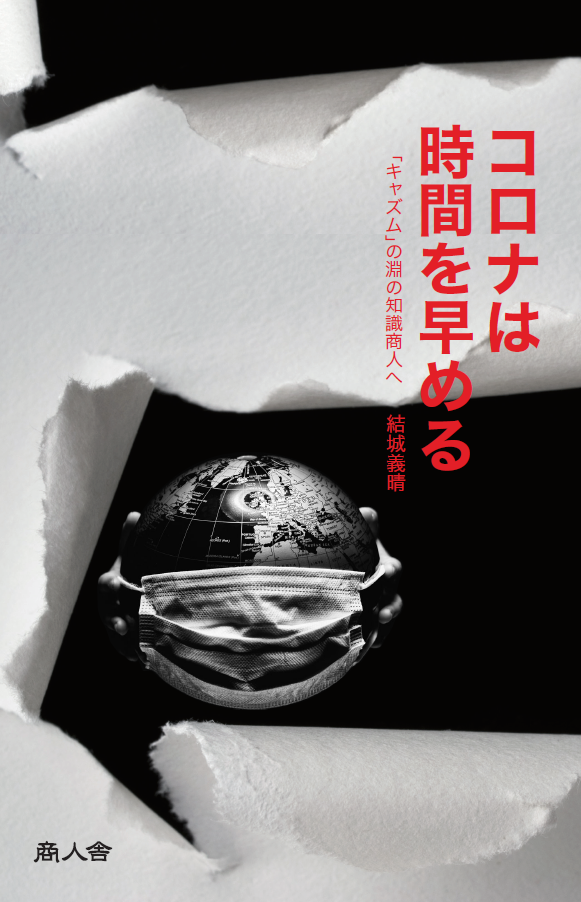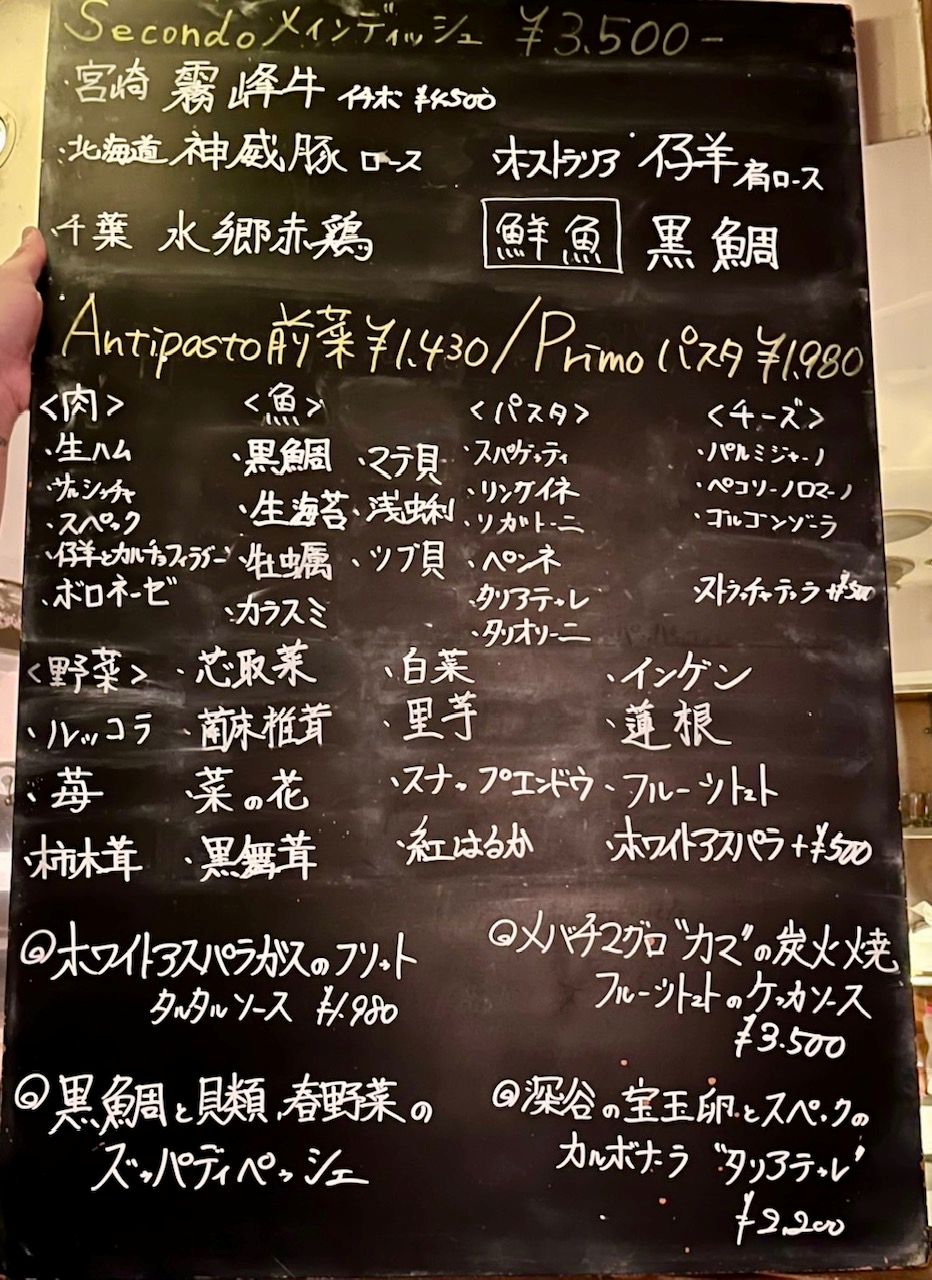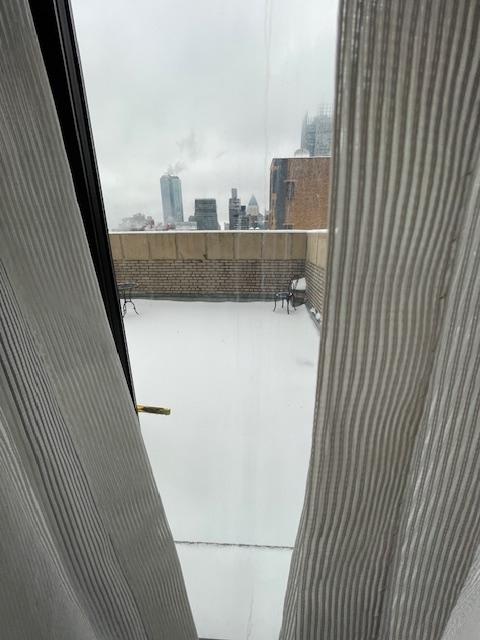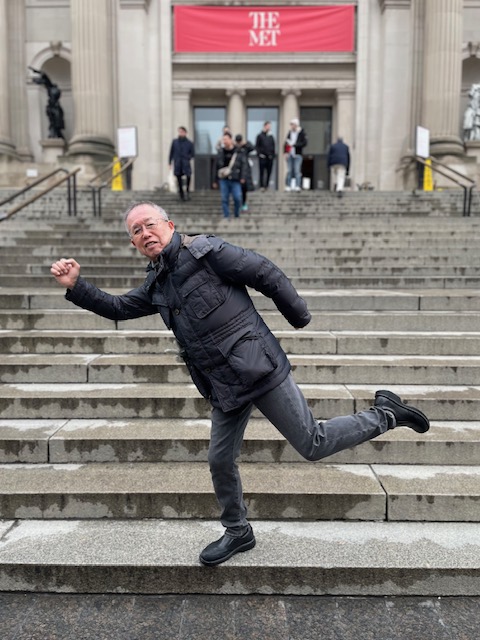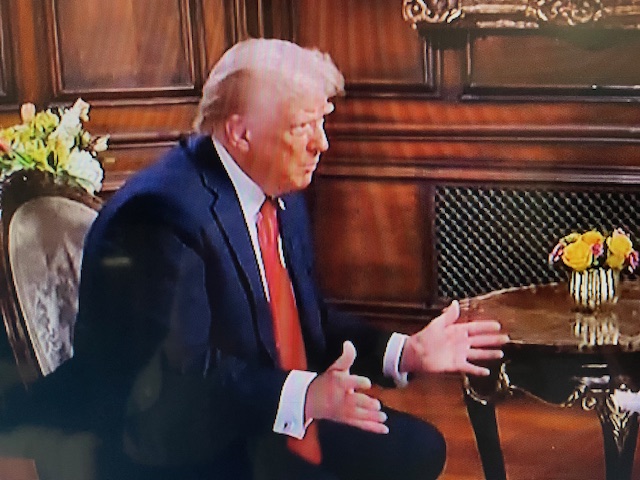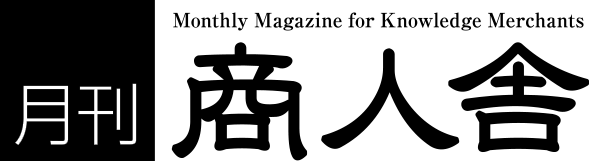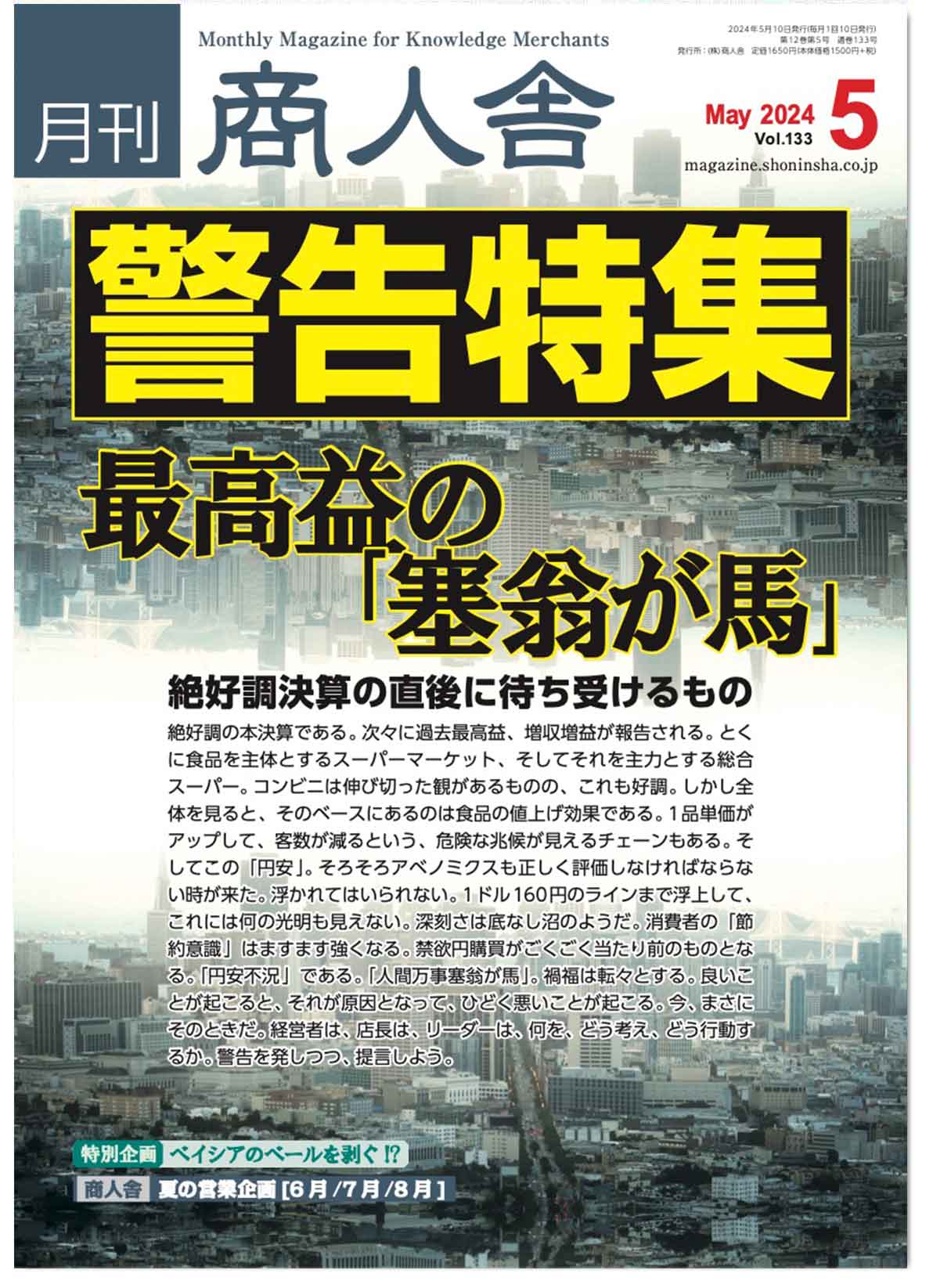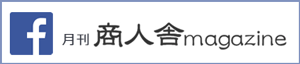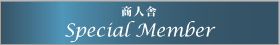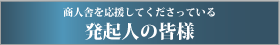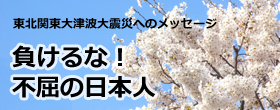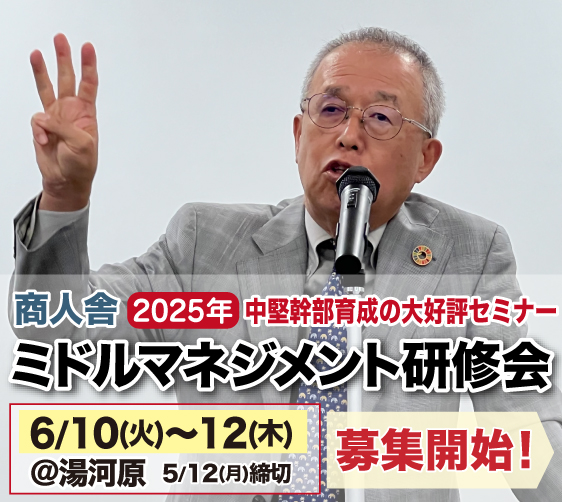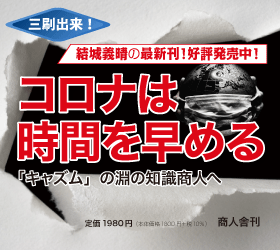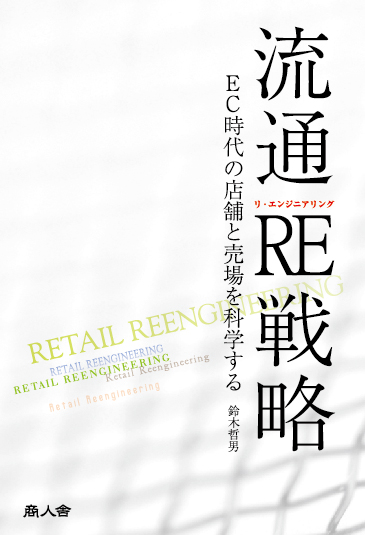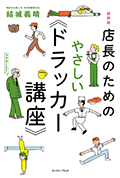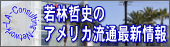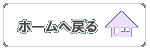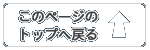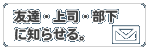2025年2月最後の日。
イオンの緊急記者会見。
月刊商人舎3月号の入稿の真っ最中なので、
on-lineで参加した。
イオン㈱がイオンモール㈱とイオンディライト㈱を、
完全子会社にする。
吉田昭夫イオン㈱社長が冒頭で趣旨を説明した。

大野恵司イオンモール㈱社長は、
ショッピングセンター事業の、
成長のビジョンを語った。
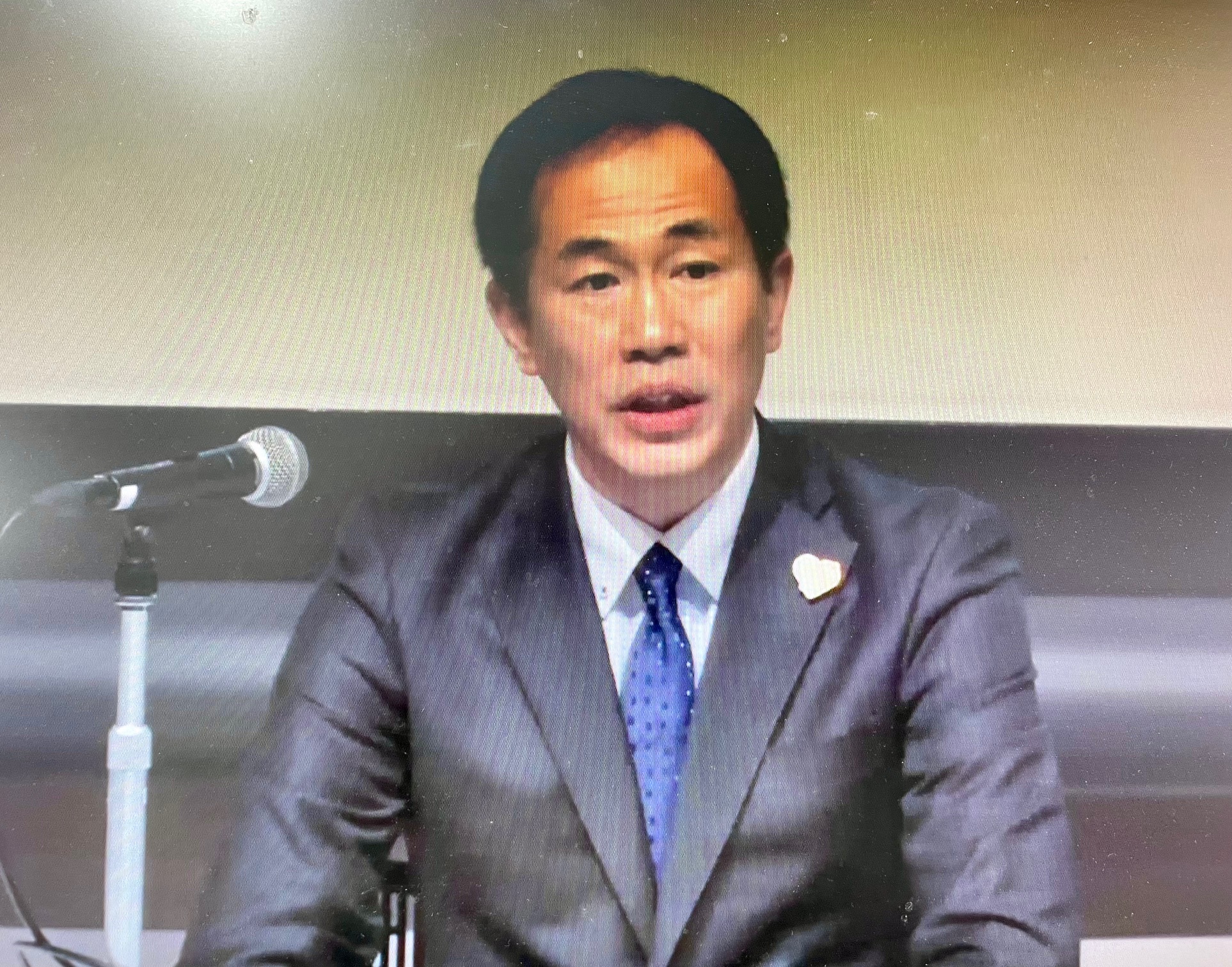
濵田和成イオンディライト㈱社長は、
機能を果たし続けたいと決意を述べた。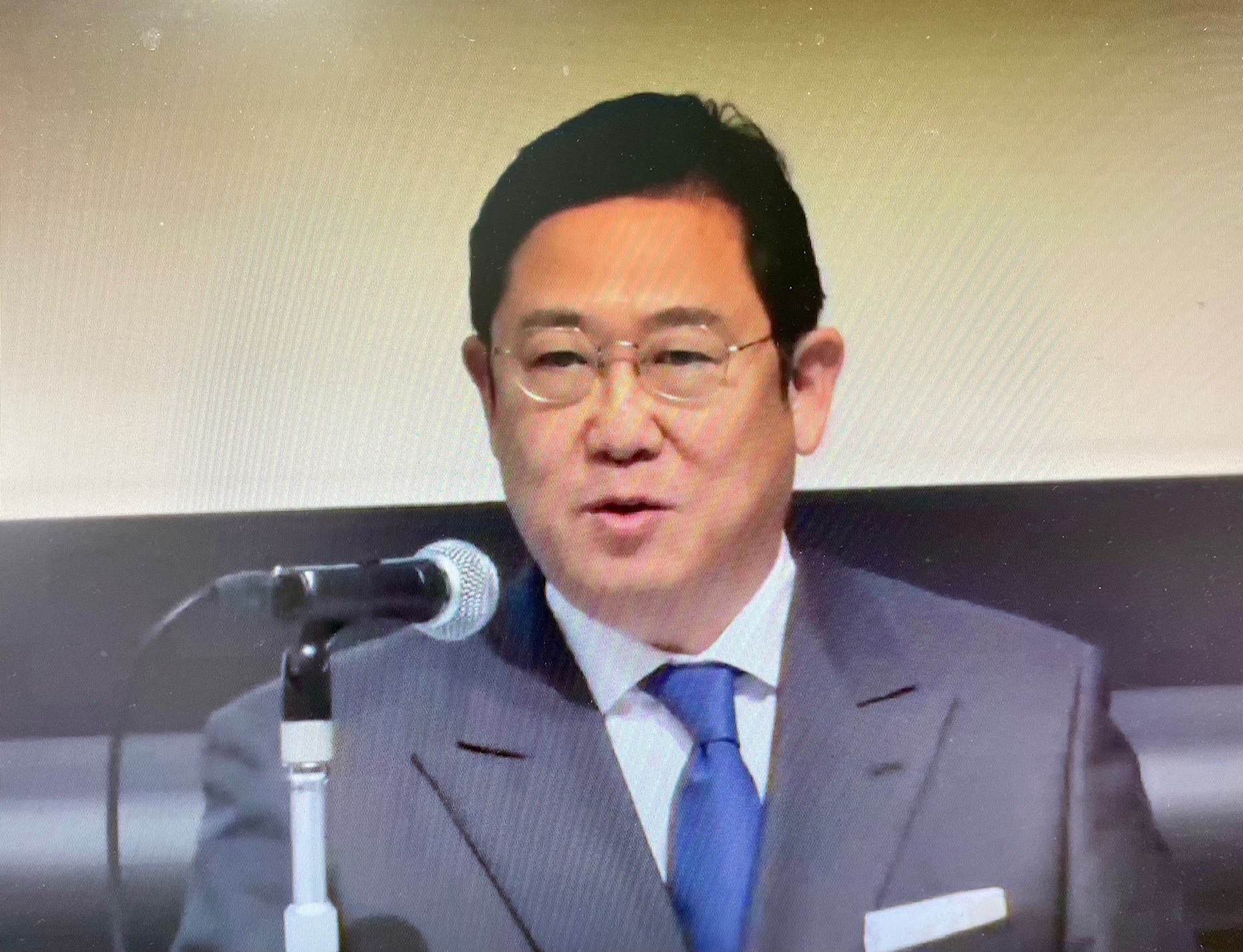
商人舎流通Supernews。
イオンはグループのホールディングカンパニーだ。
イオンモールは、
ショッピングセンターを開発し運営する。
主にリージョナルショッピングセンターだ。
2024年2月期決算。

営業収益4232億円、営業利益464億円。
国内のモール事業として確固たる地位を築いている。
そしてイオンディライトは、
ファシリティマネジメント事業を展開する。
その事業範囲は決算のセグメント分類でわかりやすい。
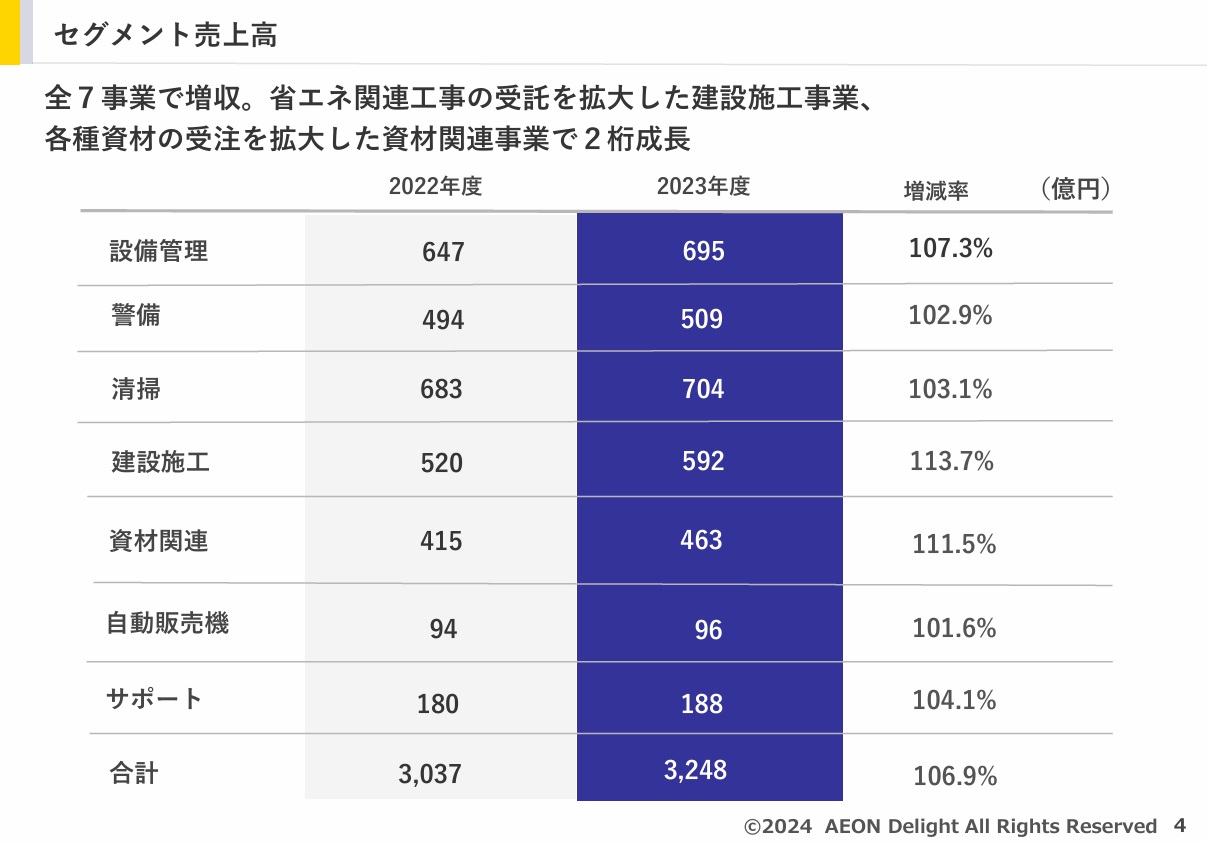
国内・海外の店舗の清掃事業が、
売上高704億円で一番多い。
次が設備管理(施設管理)で695億円。
建設施工が592億円、
警備が509億円などなど。
イオンモールとは2月28日付で、
株式交換によって子会社化に向けた協議を開始。
これは全く問題なく進む。
イオンディライトに関しては、
公開買い付けによって完全子会社化する。
2月最後の日の発表は、
タイミングが絶妙だった。
この会見のキーワードは、
イオングループのもつ「スケーラビリティ」。
「組織が需要の増加に応じて、
規模を拡大できる能力」
つまりイオンモールとイオンディライトが、
完全子会社になることによって、
人財や資金、その他の要素を、
これまで以上に迅速に緊密に獲得して、
規模拡大していくことを可能とする。
イオンディライトの業績は、
イオンの小売店舗が成長を遂げれば遂げるほど、
自然増する。
他グループ、他企業にも営業をかけて、
清掃や施設管理、建設施工の事業を拡大していく。
イオンモールに関しては、
アジアに大きな成長の可能性を求める。
一つの問題は、
国内のリージョナルチェーンが、
どのように発展するか。
アメリカではこのフォーマットは、
すでに衰退している。
しかし発展途上の国や社会では、
まだまだニーズは高い。
イオンの吉田昭夫社長。
「イオングループは、
自主自立を基本にして成長してきた。
それは変わらない」
いいことを言う。
「グループのリソースを当てて、
再成長をスピードアップさせていく」
さて私は1日中、横浜の商人舎オフィス。
ランチの後、コーヒーを買いに行った。
「珈琲問屋」は 国内に17店舗、海外2店舗。
年商は27億9000万円。
欧米のコーヒーのバルクの売り方。
商人舎で飲むコーヒーは全部、
珈琲問屋のものです。
おいでください。
飲んでみてください。
記者会見を見ていて、
セブン&アイ・ホールディングスとの、
大きな差を感じた。
イオンは自分のことを自分で決めている。
ただし、イオンは、
親子上場がもっとも多い会社のひとつ。
コングロマーチャントだからでもある。
しかしそれは一つの流れとして、
統合に向かっていく。
だから吉田さんはあえて、
「自主自立」という言葉を使った。
インディペンデントな存在でありながら、
一つのグループとして機能することを強調した。
しかし株式市場のなかでは、
集合したほうが株価には好影響が出る。
だから一つになっていく。
それは自然、必然、当然のことなのだと思う。
〈結城義晴〉