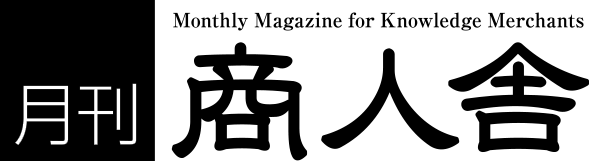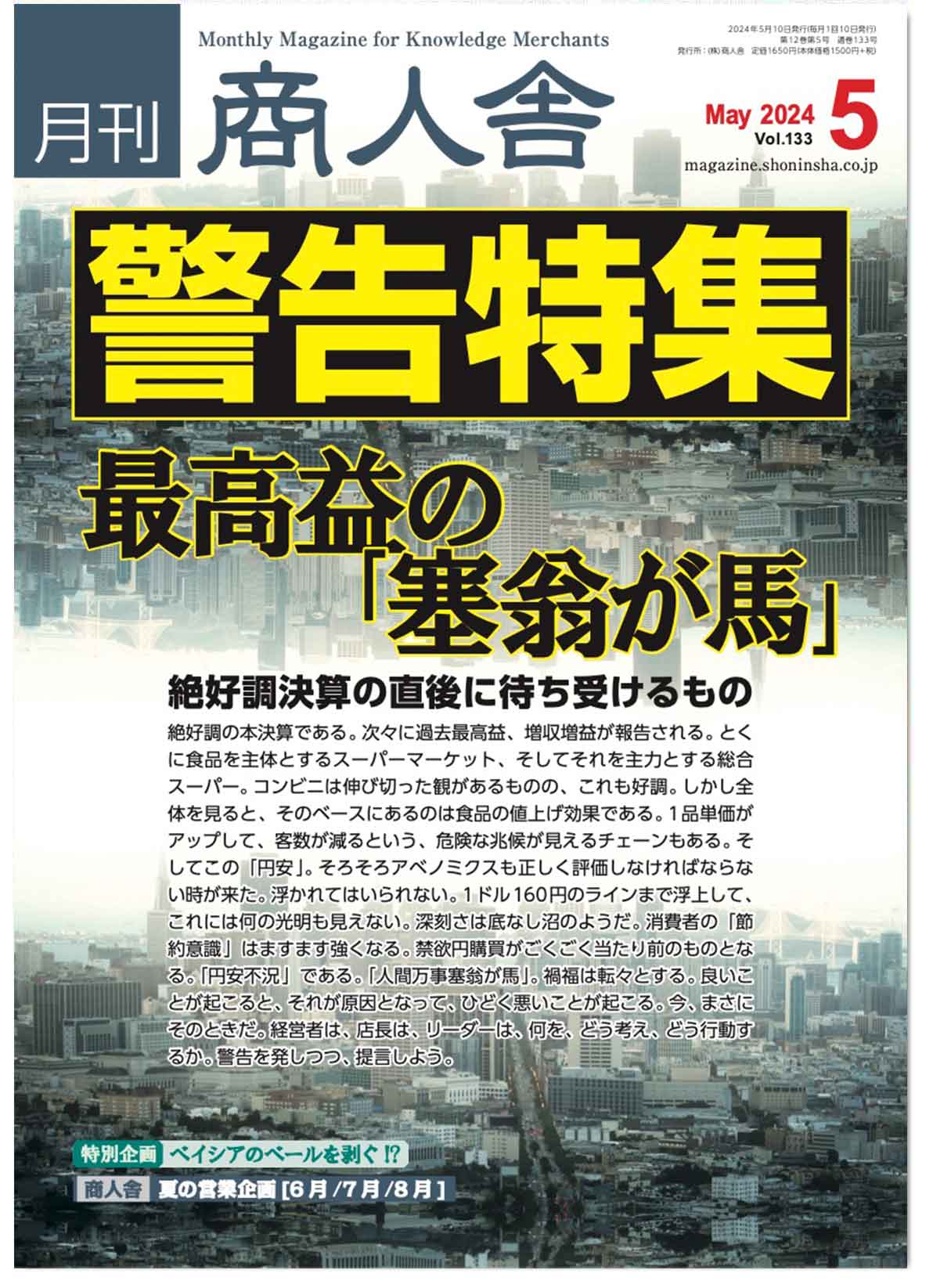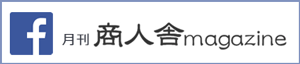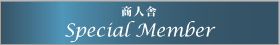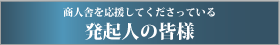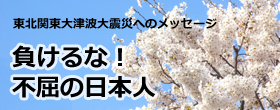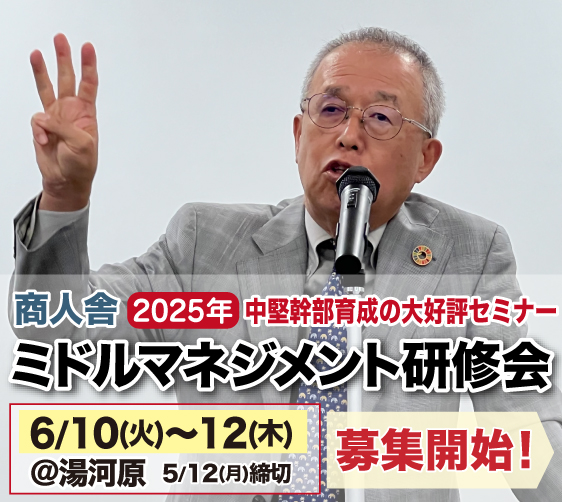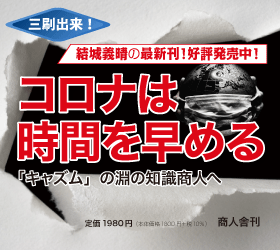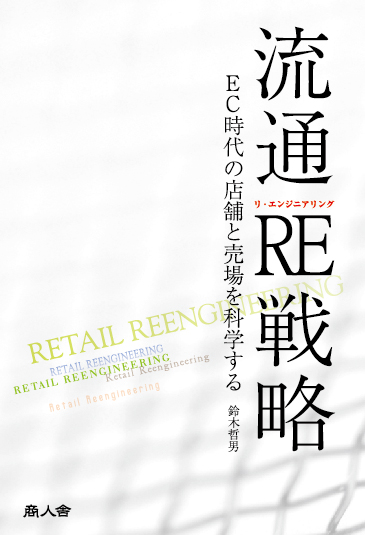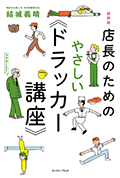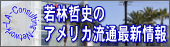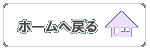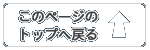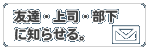二十四節気の「穀雨」
穀雨(こくう)は、
穀物の成長を助ける雨のこと。
田畑の準備が整い、
それに合わせて春の雨の降るころ。
そろそろ田植えの季節だ。
一方、欧米では、
「イースター」
キリスト教の「復活祭」。
イエス・キリストは処刑されたのは、
よく「13日の金曜日」と言われるが、
確かではない。
西暦30年の4月7日の金曜日という説、
西暦33年の4月3日の金曜日という説。
そして3日後に復活したとされる。
キリスト教では復活祭の日を決めている。
「春分の日の後の、
最初の満月の日の翌日曜日」
だから毎年変わる。
今年は4月20日、
昨年は3月31日だった。
来年は4月5日。
イースターの象徴は卵だ。
アメリカのスーパーマーケットでは、
卵が主役になる。
卵は新しい命が生れてくることを象徴している。
このイースターの日に、
ウラジーミル・プーチンが、
勝手に「停戦宣言」を発した。
モスクワ時間4月19日午後6時から、
21日午前0時までの30時間。
そして軍事行動を停止するよう命じたらしい。
しかしウクライナ側、
ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、
「信用できない」と表明した。
ロシア軍が砲撃を続けているようだ。
穀雨にしてイースター。
1日中、家にいた。
午後、二人の孫娘がやってきた。
姉娘にウォルマートで買ってきた、
アルファベット遊具をプレゼントした。

とても喜んで、
お風呂にまで持って入っている。
さてほぼ日の糸井重里さん。
今日のダーリン。
井上ひさしさんの言葉。
私もよく引用する。
「むつかしいことをやさしく、
やさしいことをふかく、
ふかいことをおもしろく、
おもしろいことをまじめに、
まじめなことをゆかいに、
ゆかいなことを、
いっそうゆかいに」
糸井。
「このことばの見事なところは、
○○を△△に、△△を□□にと
しりとりのようにつなげている技術なのだが、
○○も△△も□□のどれも否定せずに、
次々に衣装を替えて
別の姿にしているところだと思う」
その糸井さん。
『決定版 一億人の俳句入門』を読んでいて、
「俳句を詠むとき、大事なこと」に感心した。
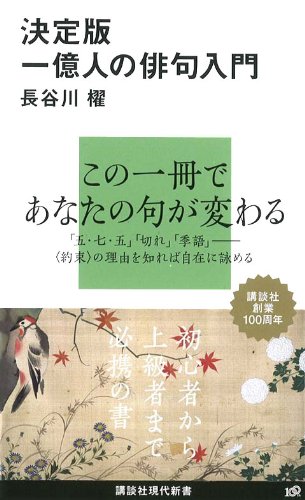
その大事なことは三つ。
一、わかるように詠む。
一、すっきりと詠む。
一、いきいきと詠む。
糸井さん。
「これは、わかりやすいし、
わかりやすくない」
「”きっとそうなんだろう”
という実感もあるが、
わからないとも言えるし、
もっとわかりたくなる」
「本のなかには、
これの説明もあるけれど、
そう簡単にわかったなんて
言えないことが書いてある」
そして言う。
「こういうのが、いちばん
“おもしろい”んだよなぁ」
ん~、よくわからない。
蛇足のように書いてあるのが、
「やさしく、つよく、おもしろく」
これも、「よくできているなぁ」と、
糸井は自画自賛。
「やさしく、つよく、おもしろく」は、
日刊イトイ新聞創刊25周年記念、
25の「お宝ことば」の一番目で、
ほぼ日という会社の行動指針を表すことば。
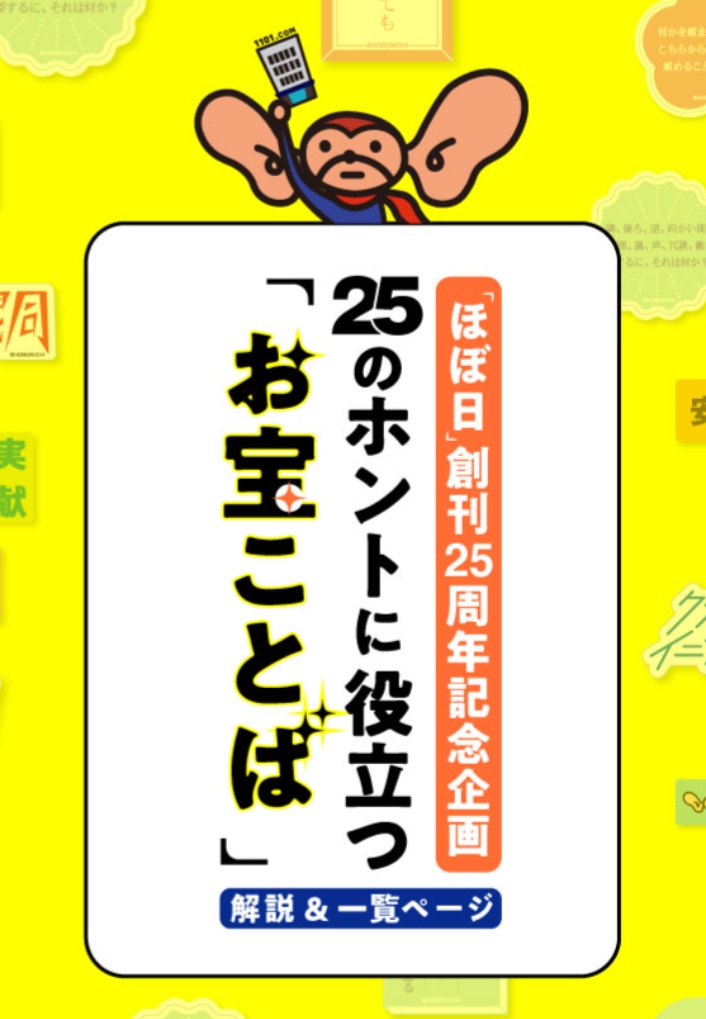
まず、「やさしく」は前提。
そして、「やさしく」あるために、「つよく」。
さまざまなことを実現できるように「つよく」。
そのうえで、「おもしろく」という価値を生み出そう。
商人舎と言うか結城義晴の信条は、
「今日も一日、優しく、強く」
糸井と似ている。
五番目は、
「正直は最大の戦略」
山岸俊男著『信頼の構造』の言葉。
「いちばん正直な人が、
いちばん生き残る」
八番目が、
「おちつけ、たのしめ」
いざ、なにかに取り組むとき。
いよいよここからが本番だぞ、
というようなとき。
ふたつの4文字。
「おちつけ」は、
「さんまのまんま」という番組のセットの
掛け軸に書いてあったことば。
もうひとつの「たのしめ」は、
矢沢永吉がコンサートに臨む直前など、
逃げ出したいくらいのプレッシャーがあるとき、
自分に言い聞かせることば。
明石家さんまの「おちつけ」と、
矢沢永吉の「たのしめ」。
セットにすると、とてもよい。
九番目。
「いいことをしているときは、
悪いことをしていると
思うくらいでちょうどいい」
糸井重里が尊敬する思想家、
吉本隆明が親鸞の善悪についての思想を、
消化したうえで生み出したことばらしい。
商人舎にも言葉はある。
徹底することは、
「きびしく、こまかく、しつこく」
戦略の言葉。
「小さく、狭く、濃く、深く」
孫娘たちがもう少し大きくなって、
わかりやすいというくらいに、
なってくれればいいのだけれど。
〈結城義晴〉