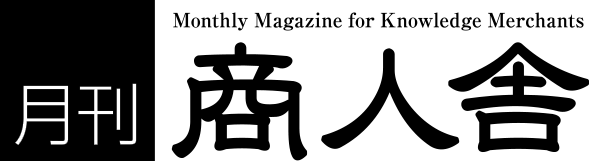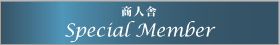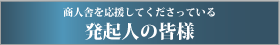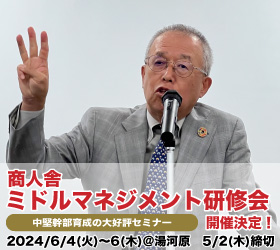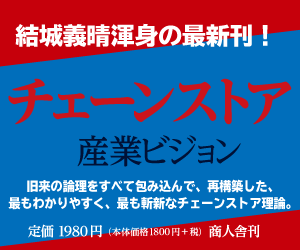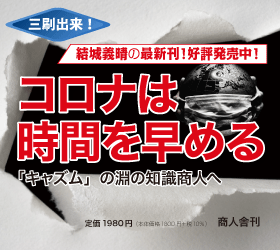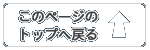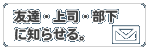滝沢秀一「ゴミ清掃員の日常」と「もったいない・ありがたい」

「折々のことば」
朝日新聞一面のコラム。
編著者は鷲田清一さん。
その博識と見識、
そして視野の広さ、貪欲さには、
毎朝、舌を巻く。
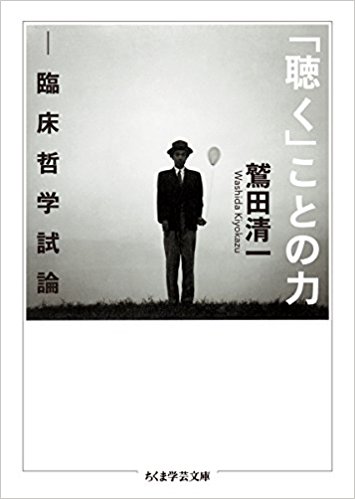
いまや、朝日の名物「天声人語」を、
完全に食ってしまった。
今日の第1561回。
管理されなければ
できない
恥ずかしい世代になんて
なりたくない。
(滝沢秀一)
お笑いコンビ「マシンガンズ」の芸人。
1976年生まれ。
1998年から「マシンガンズ」で活動。
「エンタの神様」などに、
ちょこちょこっと出ていた。
太田プロダクション所属だが、
売れっ子芸人では、もちろんない。
結婚して、子供もいる。
そこで定収入を得るため、
2012年からゴミ収集会社に、
正社員として勤めている。
つまり二足のわらじ、あるいは兼業。
そしてツイッターでゴミ清掃員の日常を、
赤裸々に綴り始めた。
鷲田さんの表現。
「悲喜こもごもの清掃作業にあたる中、
人びとの嗜好や消費行動の歪(ひず)みに
戸惑い、そして思う」
それらをまとめて、
昨2018年9月、エッセイ本を発刊。
それが思わぬ大ヒット。
『このゴミは収集できません』
サブタイトルは、
「ゴミ清掃員が見たあり得ない光景」
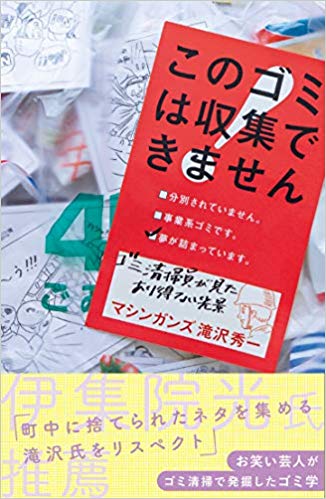
「有料化、罰則など、
ゴミ回収をめぐる規制の拡大も、
ゴミの仕分けや水切り、
物を買う前の要不要の一考などを
一人一人がきちんと
意識してやれば回避できる」
今年の5月には、
コミックス『ゴミ清掃員の日常』を発刊。
奥さんの滝沢友紀さんが漫画を担当。
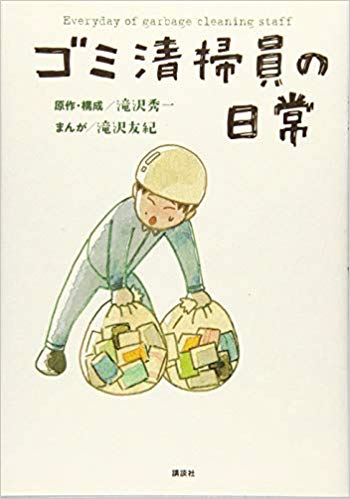
P+D MAGAZINEのインタビュー。
滝沢がゴミ清掃の仕事を始めてみると、
「居心地がいいので驚きました」
「もちろん肉体的には
しんどいときもあるのですが、
本当にどんな年齢・国籍の人でも
できる仕事だし、面白いんですよ」
この業界の人がよく言うそうだ。
「3年働いたらもう、
この世界から抜け出せなくなる」
滝沢の述懐。
「僕自身もゴミ清掃を6年続けてきて、
もう辞めたいとはまったく思わないです」
なぜだろう。
ちょっと流通業界に似ているか。
その理由は、
社会に貢献している、
実感があるからだと思う。
ゴミ清掃の仕事の中で辛いこと。
「しんどいのは、やっぱり夏と冬ですかね。
夏は暑いし、冬は雪が降ると、
道も渋滞するし……」
「夏のペットボトルのゴミの量の多さは、
一度みなさんにも
見てもらいたいくらいです。
ひとつの収集所で出るゴミの量が、
とにかく増える」
朝早くから始めて、
夜6時くらいになっても回収しきれない。
滝沢は分別の重要さを力説する。
「たとえば、分別が不十分で
可燃ゴミの中に不燃ゴミが
多く混じってしまっていると、
焼却炉でゴミを燃やすときに、
ゴミが入りきらないので焼却炉を
一度止めなきゃいけなくなるんですよ」
「燃えなかったゴミを手作業でかき出して、
また焼却炉に火をつけるわけです。
で、このとき、一度止めた
焼却炉に再び火をつけるという作業に、
だいたい250万円から350万円の費用がかかる」
そういった家庭ゴミの処理費用は
税金で賄われている。
滝沢。
「東京のゴミの埋立地は
あと50年しか持たないと言われている。
減量化や分別にまったく気持ちが
向かない人がいまだにいることには
心が痛みます」
そして将来の問題。
「リサイクルってやっぱり
習慣だと思うんですね。
だから、子どもが小さいうちから
絵本でそういうことを教えられたら、
自然とゴミを分別して
リサイクルできる大人になってくれるかな」
芸人としては売れなくとも、
ゴミ清掃員となって、
その観察力と発信力で、
社会に貢献する。
いい話だ。
最後に再び結城義晴のMessage。
月刊商人舎2017年4月号の巻頭言。

もったいない、
ありがたい。
「売れない」のではない。
「売っていない」のだ。
「売り損なっている」のだ。
鈴木敏文さんが言い、
故緒方知行さんが追従(ついしょう)した。
これは機会損失撲滅の本質を突いた。
だからセブン-イレブンは、
加盟店とスーパーバイザーに徹底した。
「売れ筋でロスを出せ!!」
しかし残念ながらこの時代は終わった。
値下げロス・廃棄ロスと機会ロスは、
本来、二律背反の関係にある。
だから戦略的に、組織的に、
もう1人・もう1品・もう1円の改善がいる。
そしてもう1パーセントの努力が望まれる。
フィリップ・コトラーが読みきった、
マーケティング1.0は、
製品中心の時代だった。
マーケティング2.0は、
消費者志向の時代で、
売り手市場から買い手市場に移行した。
そしてマーケティング3.0の今は、
価値共創の時代である。
ソーシャルマーケティングの時代である。
「売れない」のではない。
「もったいない」が足りないし、
「ありがたい」が少ないのだ――。
「もったいない、ありがたい」が広がれば、
ゴミもロスも格段に減っていく。
〈結城義晴〉