ニューヨーク初日の対比的なポジショニングと「普通の店」の進化

羽田国際空港から飛び立って
12時間ほどで、
夜が明け始める。

そしてジョンFケネディ空港に到着。
全員無事に入国を済ませ、
現地コーディネーターの
浅野秀二さんと合流。
ニューヨーク・ニューアーク地区では、
マーケットシェア1位が、
ボランタリーチェーンのショップライトだ。
115店舗16.9%。
米国のごく一般的なスーパーマーケット。
「コンベンショナル(伝統)型」と呼ばれる。
それでもトレンドの対面売場を設けて、
デリを強化する。

普通のスーパーマーケットを見ることで、
一つの標準ができる。
そのあとで際立つ特徴の店を訪れる。
するとイノベーションの本質が見えてくる。
しかしその普通の店が進化している。
それは当然のことだ。
どんな店、どんな企業もいつも、
イノベーションを志向しているからだ。
そのなかで本当に優れた企業は、
イノベーションを継続することができる。
イノベーションが止まらない。
それが強い企業、エクセレントな組織なのだ。
そのウォルマートの最強のフォーマット。
スーパーセンター。
衣食住薬のフルライン店舗。

このエリアに60店舗で10.4%。
コストコに次いでシェア4位。
ニューヨーク市郊外にある超繁盛店。
エブリデーローコストを標榜しながら、
デリ売場には対面販売コーナーを設けて、
顧客サービスを怠らない。

ロールバックの嵐。
EDLP価格からさらに値引いて販売する。

車中でも講義。
ウォルマートのPBを紹介する。
グレートバリューの、
「ツイスト&シャウト」。
NBの「オレオ」の完全コピー商品。
オレオと限りなく同じ味で3割安い。
そこにこの開発の価値がある。

車内で食べ比べする。
ターゲット。
ウォルマートと同じ業態のライバル。
ウォルマートは食品とハードラインに強い。
ターゲットは衣料のソフトラインに強みをもつ。

生鮮食品は絞り込んでいる。

「アウトドアショップ」と名付けられた、
園芸コーナーが新設された。

ウォルマートのコーポレートカラーが青なら、
タ―ゲットは赤。

あらゆることがウォルマートと対極にある。
バレンタインプロモーションも、
センス良い売場づくりで真っ赤。
ウォルマートとターゲットは、
一目で差異がわかる。
市場を二分して棲み分けている。
それがポジショニング競争だ。
1週間前にオープンした。
ドイツのトップ小売業、
シュワルツグループのボックスストア。

アメリカには2017年に進出。
大西洋岸南部を中心に展開。
ニューヨーク州のベストマーケット27店舗を買収。
1月現在183店舗。
青果に続くベーカリー売場に特徴がある。
焼きたてのインストアベーカリーで、
クロワッサンなど1個49セントで売って、
大人気だ。

アルディが1万平方フィートなら、
リドルは2万平方フィート。
アルディが98%PBなのに対して、
リドルは8割くらいがPBで、
ナショナルブランドも多い。
店舗中央の平台には、
ノンフードのポップアップ商品が並ぶ。
売り切れ御免のアイテムだ。

同じ商業施設の反対側に、
アルディがある。

牛乳売場は後部から補充できる、
リーチインケース。

ローコスト店舗なのに電子棚札導入。
リドルの価格変更に素早く対応する。
牛乳1ガロン(3.8ℓ)3.08ドル。
インフレが進む米国で1リットル81円。
購買力平価を考慮して1ドル100円で考えるのがいい。

マネジャーにインタビューした。
メイシーから転職してきたが、
待遇はとてもいいとか。
写真はノーグッド。
2階に水耕栽培の農場がある。
農産工場で生産した葉物を、
「ゴッサムグリーン」と名付けて販売する。
対面のシーフード売場も、
部門として位置づけられる。
アメリカのスーパーマーケットでは珍しい。

上から駐車場を望む。
くるくる回る風力発電、
駐車場の屋根の太陽光発電。
環境店舗ならではの設備満載だ。
ホールフーズを後にしてダンボ地区へ。
ダンボは、
「Down Under Brooklyn Bridge Overpass」の略。
ホテルに入って、チェックインすると、
すぐに4班に分かれて、
それぞれステーキハウスへ。
シュリンプカクテルに始まって、
シーザーサラダ、
そしてロブスター。

サーロインとヒレのステーキを、
レアとミディアムで味わう。
もちろん赤ワインをお供に。

最後はニューヨークチーズケーキとコーヒー。
大いに語り合って、よく食べた。
ニューヨークの夜。
地下から噴き出す蒸気。

長いながい1日が終わる。
それでもニューヨークの小売業は、
さらに進化を遂げていた。
普通の店のストップ&ショップが、
皮肉なことに全体の進化を示していた。
(つづきます)
〈結城義晴〉




















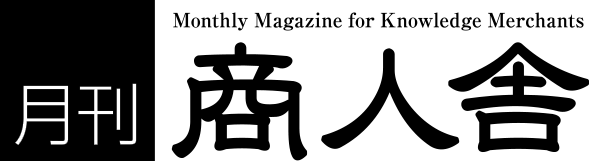
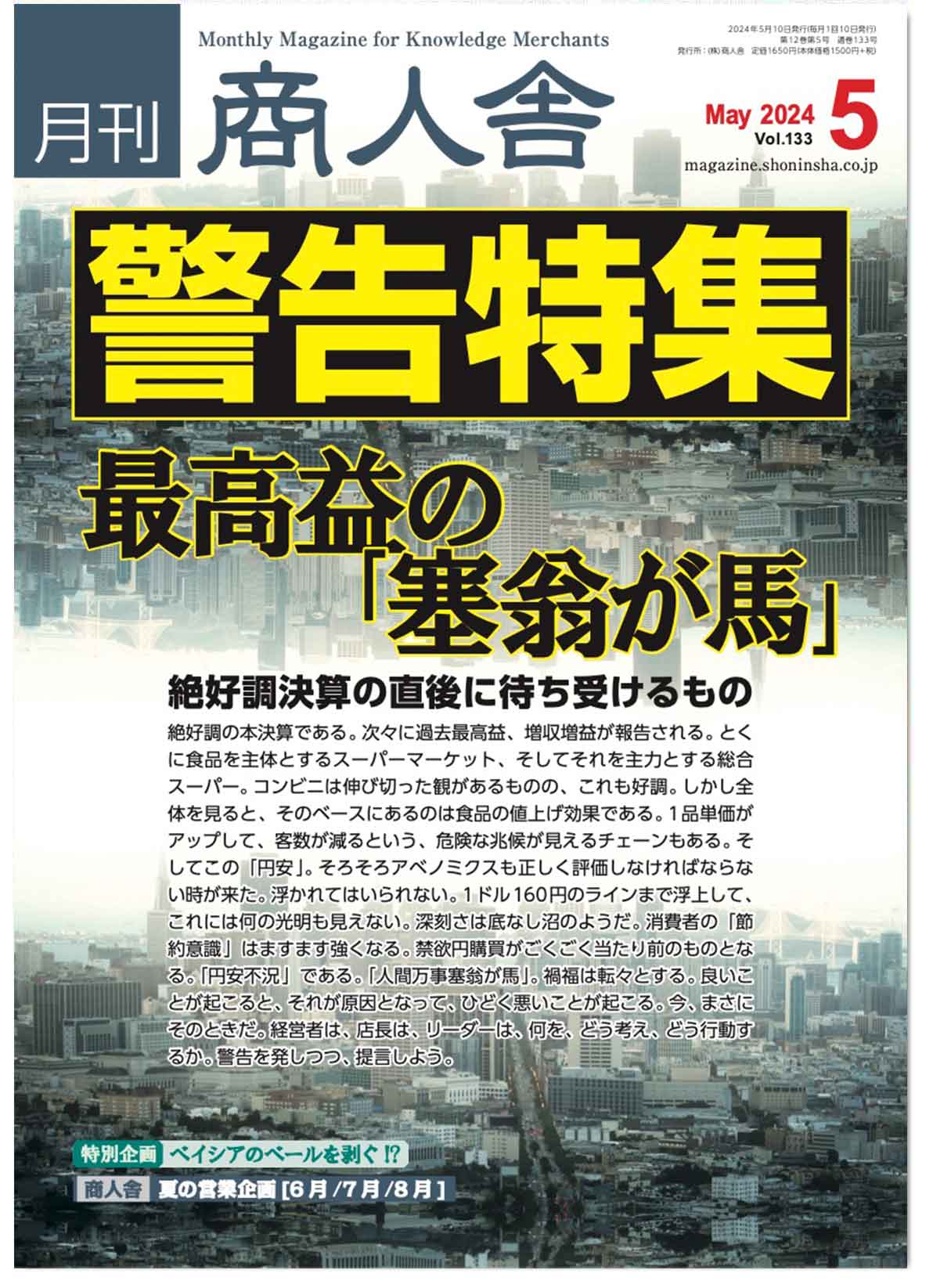









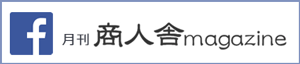

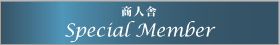
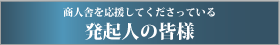
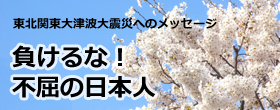
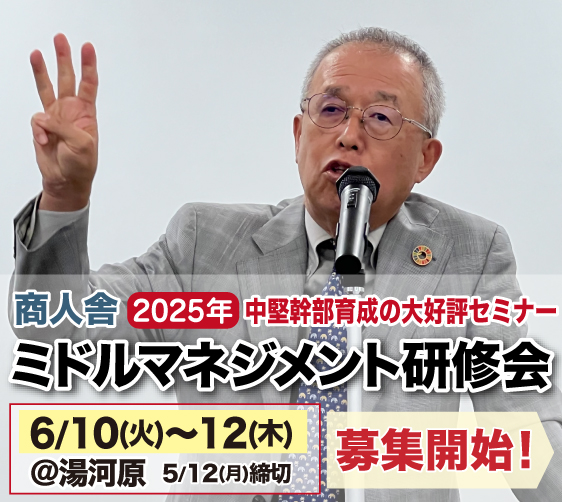




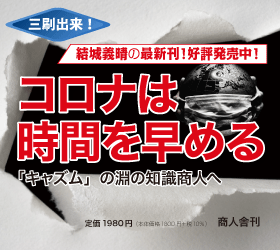
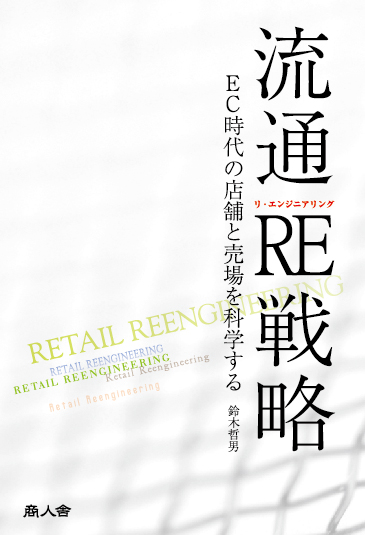
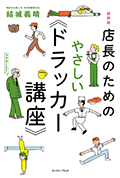
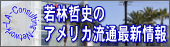



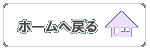
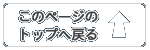
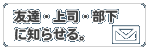

2 件のコメント
「普通の店のストップ&ショップが、皮肉なことに全体の進化を示していた。」は面白いです。残存者利益を許さないアメリカの自由競争社会の厳しさでしょうか。
加えて日本の場合、狭い平野に密度高く人が住んでいるので、近いというだけで店が選ばれることも多いように思われます。徒歩で行ける生活導線上にある店が、コンベンショナルな店でもまだ生き残っていける余地が、車社会のアメリカと比べるとまだあるような気がします。
ただそれも、人口減少の局面では大きく変わってきそうですが。
車社会のアメリカ小売産業では、
遅れた企業はすぐに舞台の外に追い出されてしまいます。
コンベンショナルな企業も必死で市場に残ろうとします。
それもイノベーションの原動力になります。
だから残っているチェーンにも、
最新の売場づくりのトレンドが採用されます。