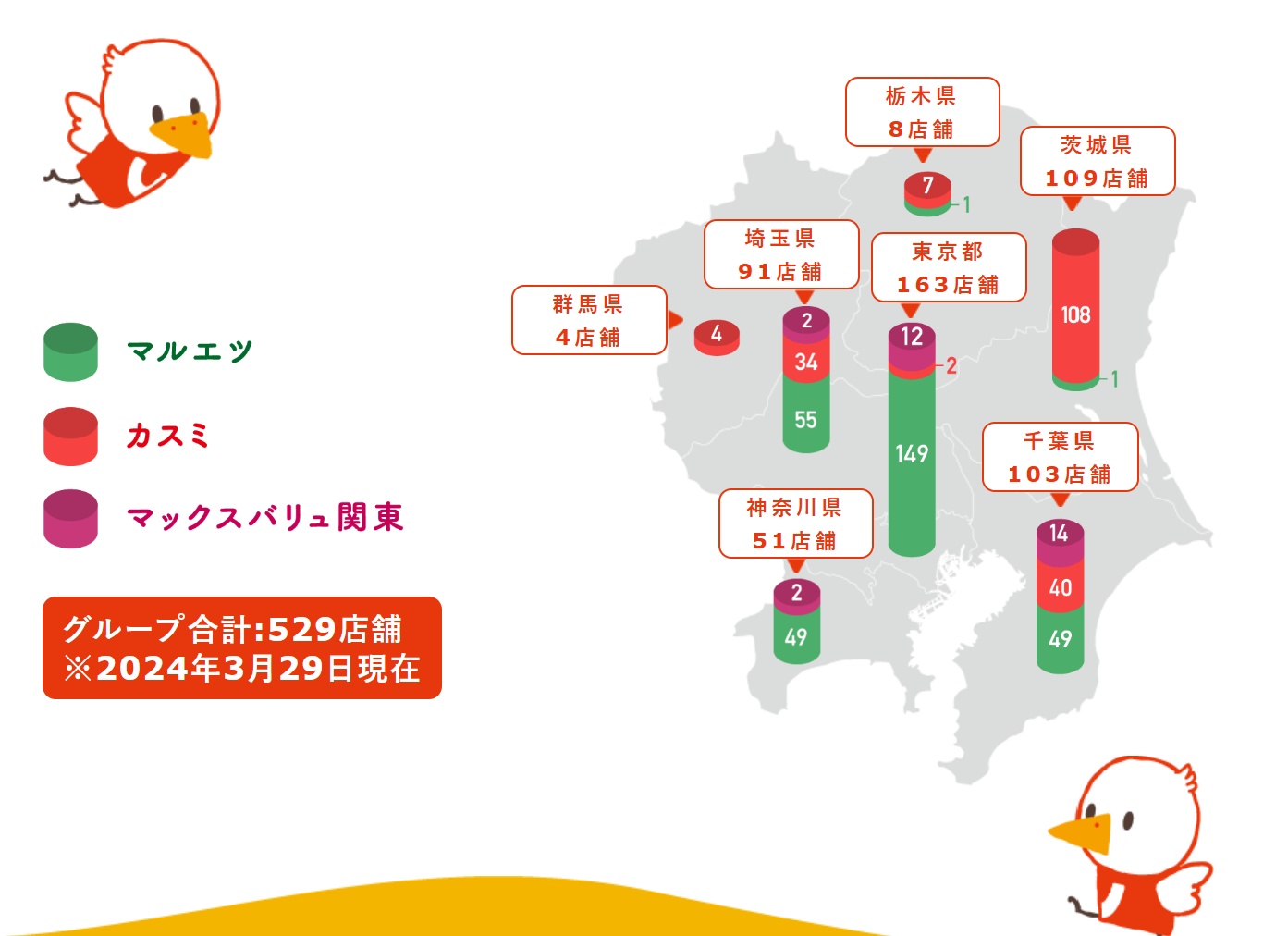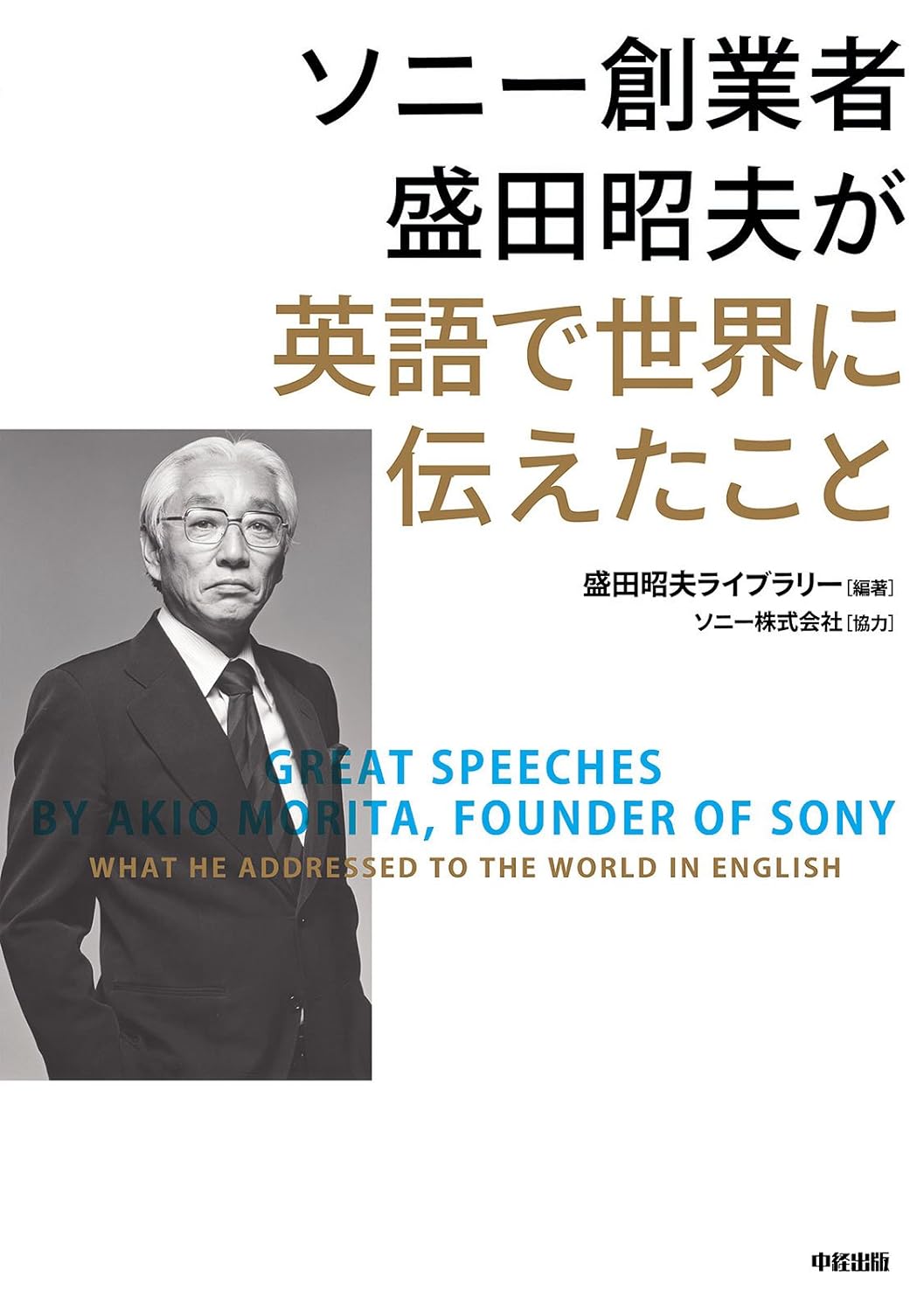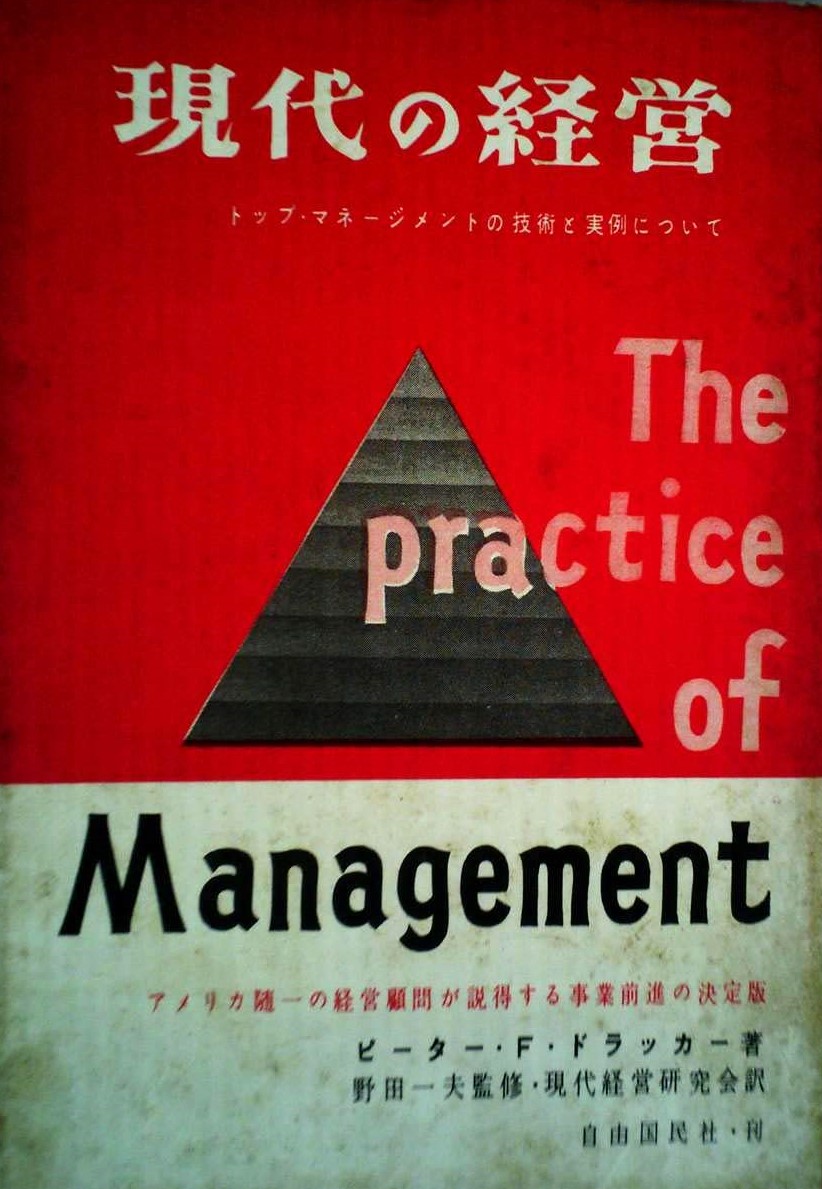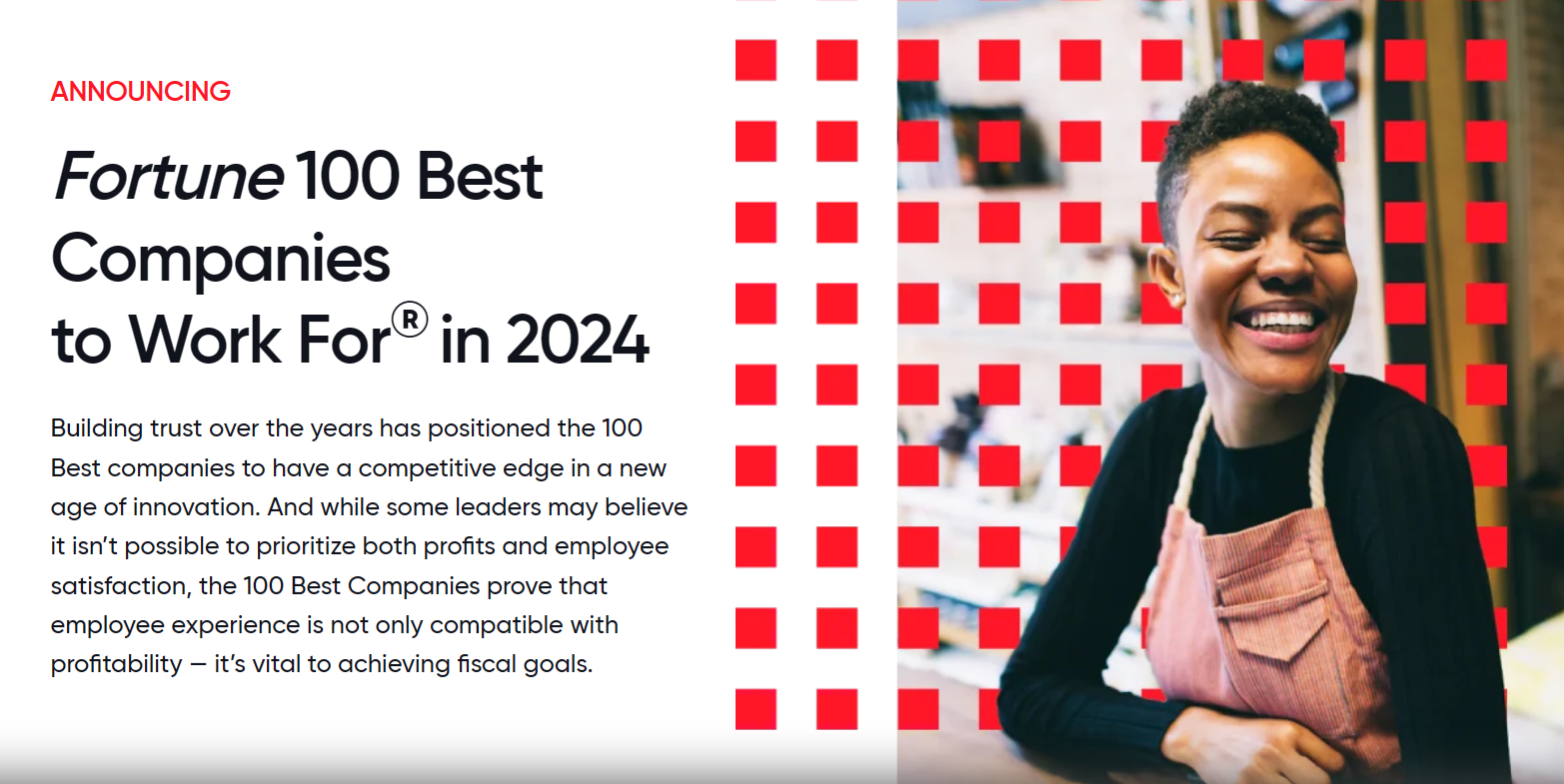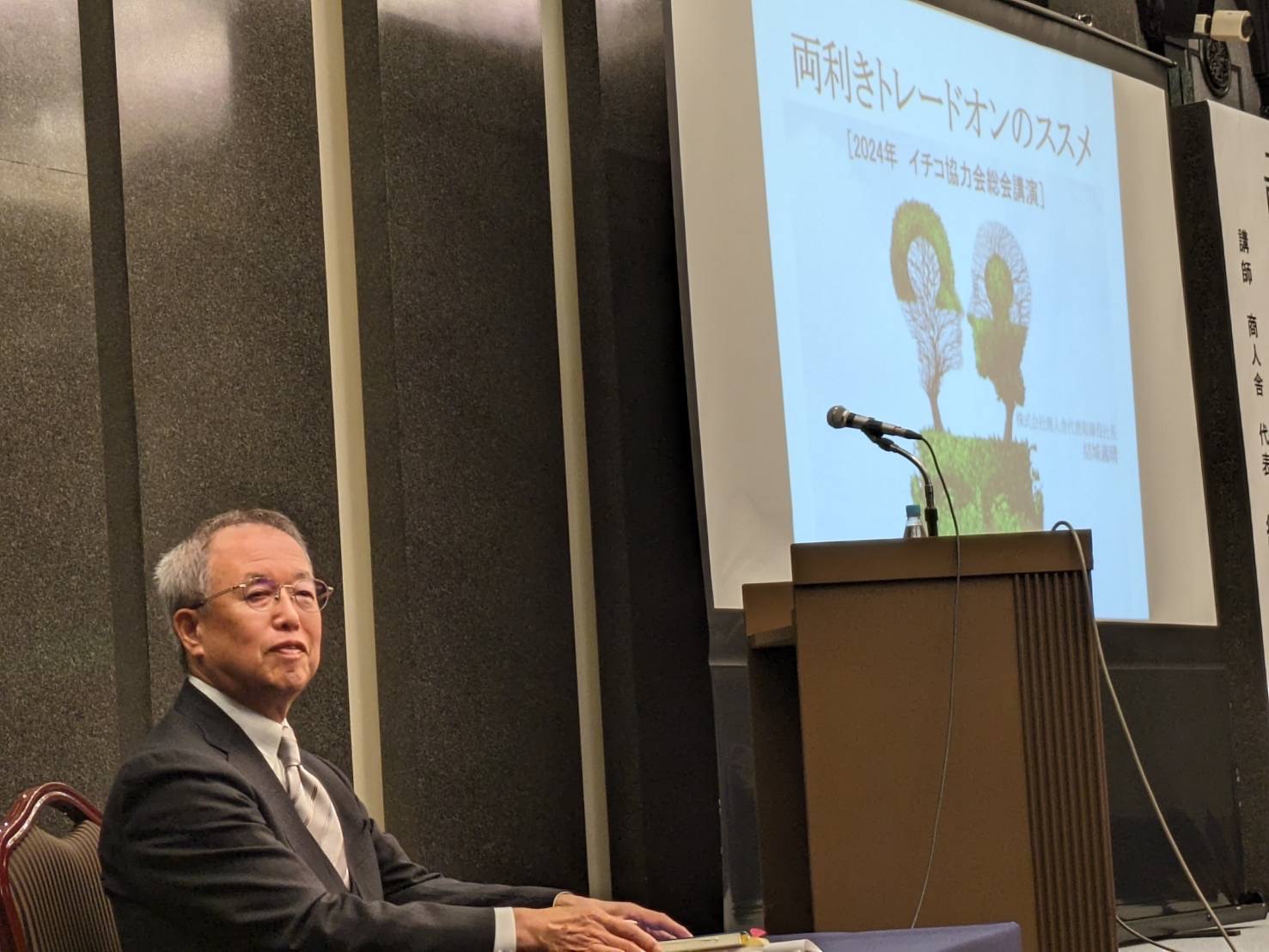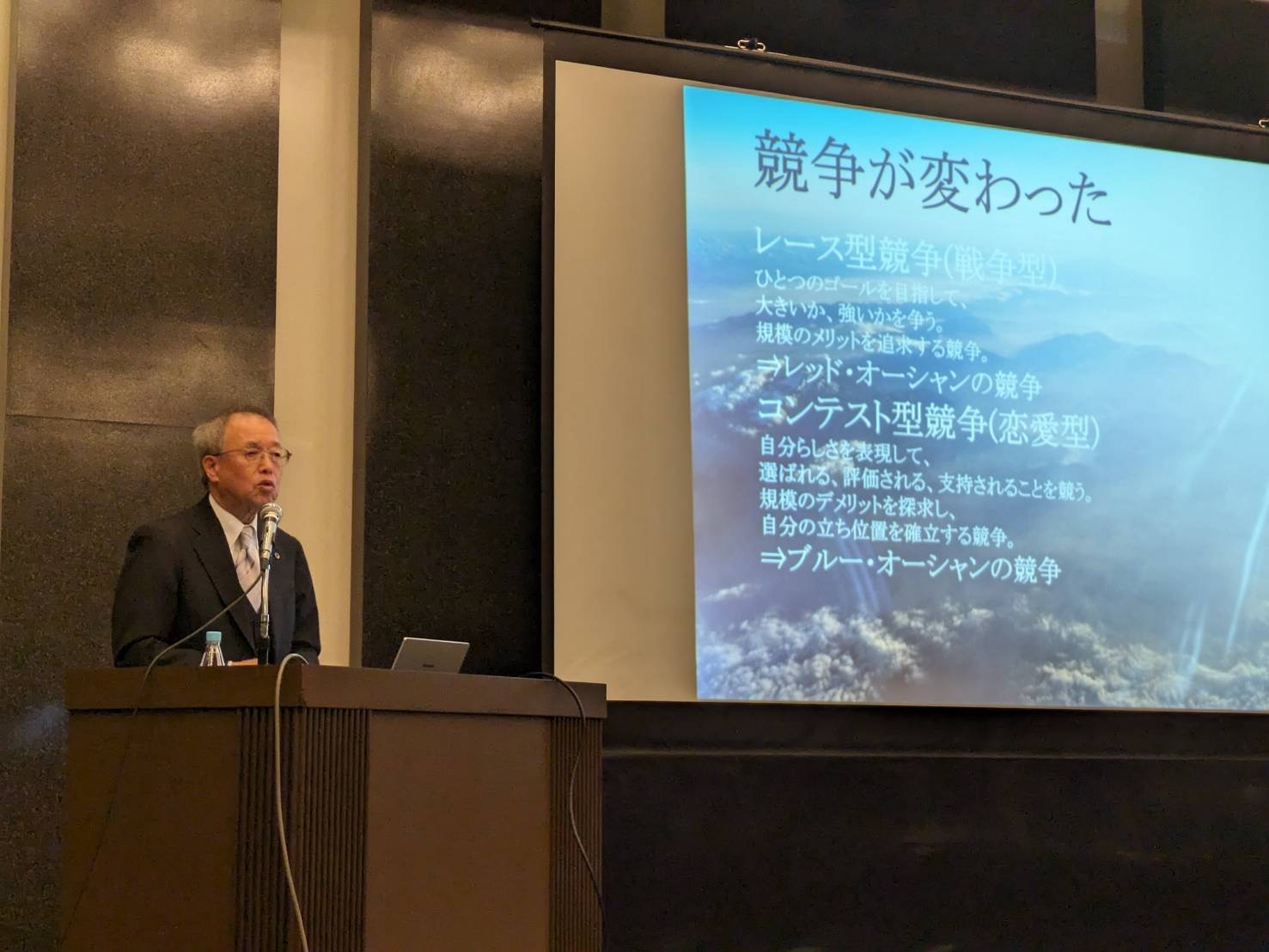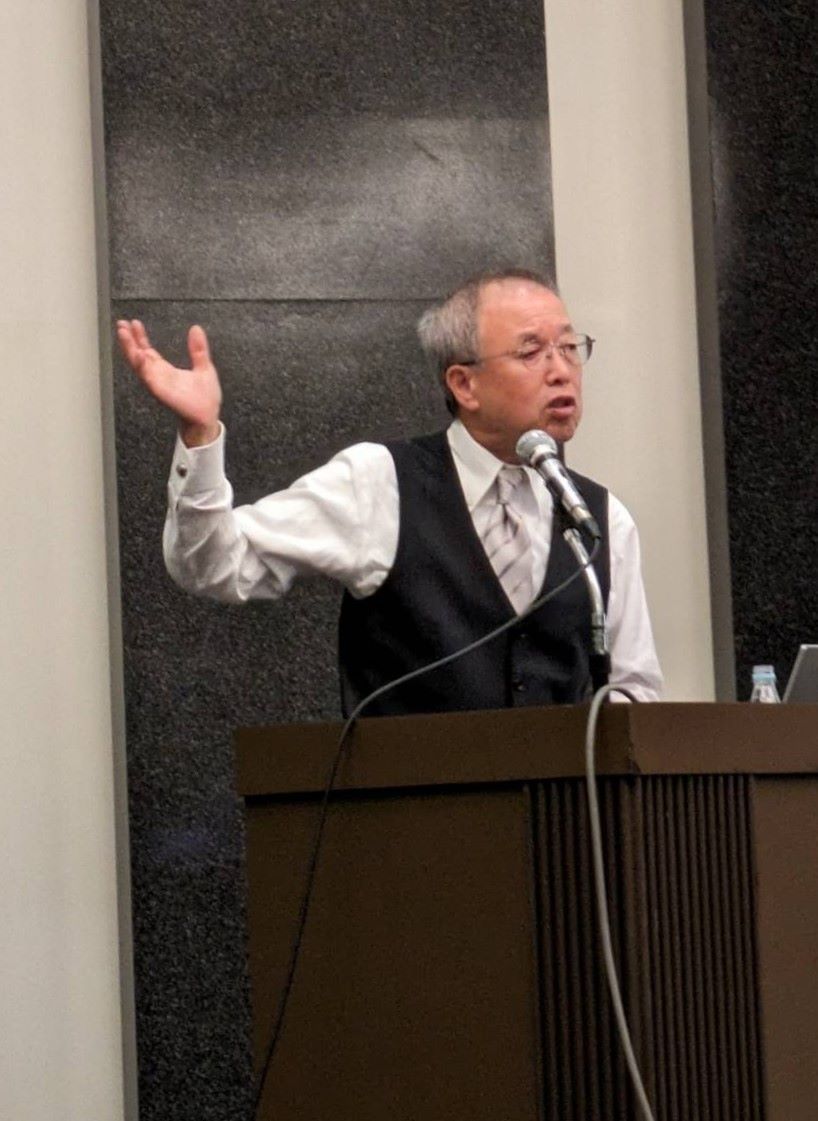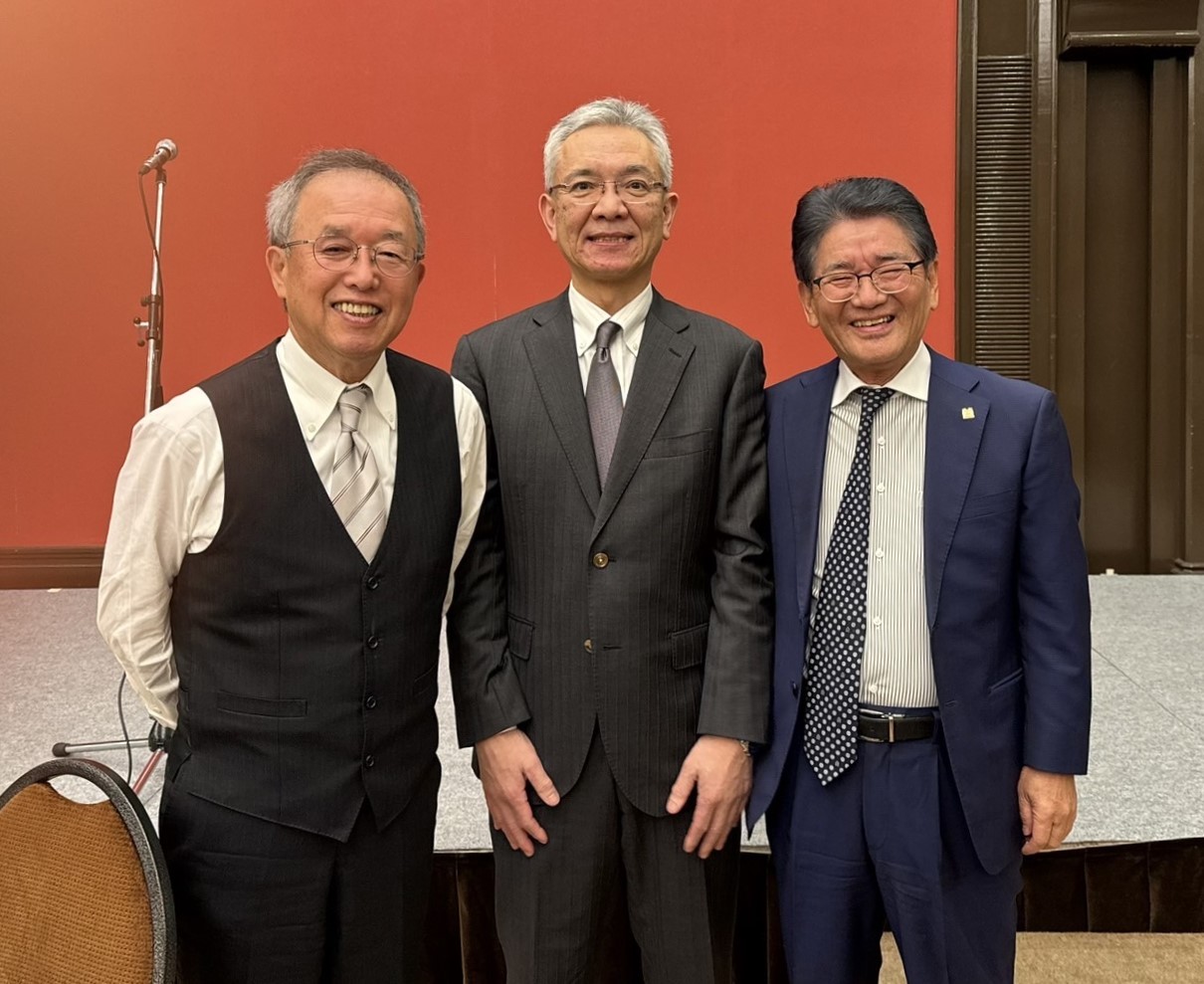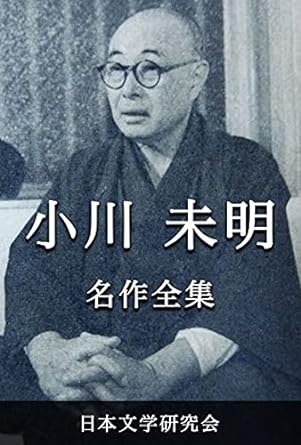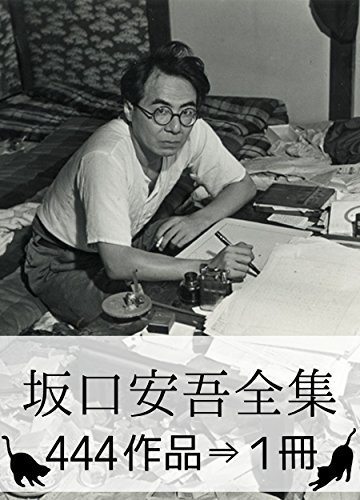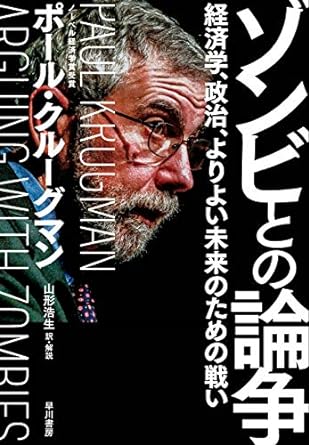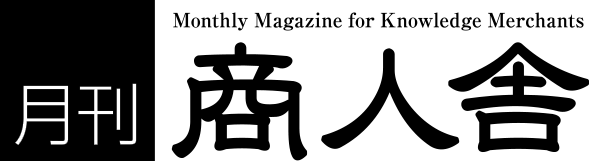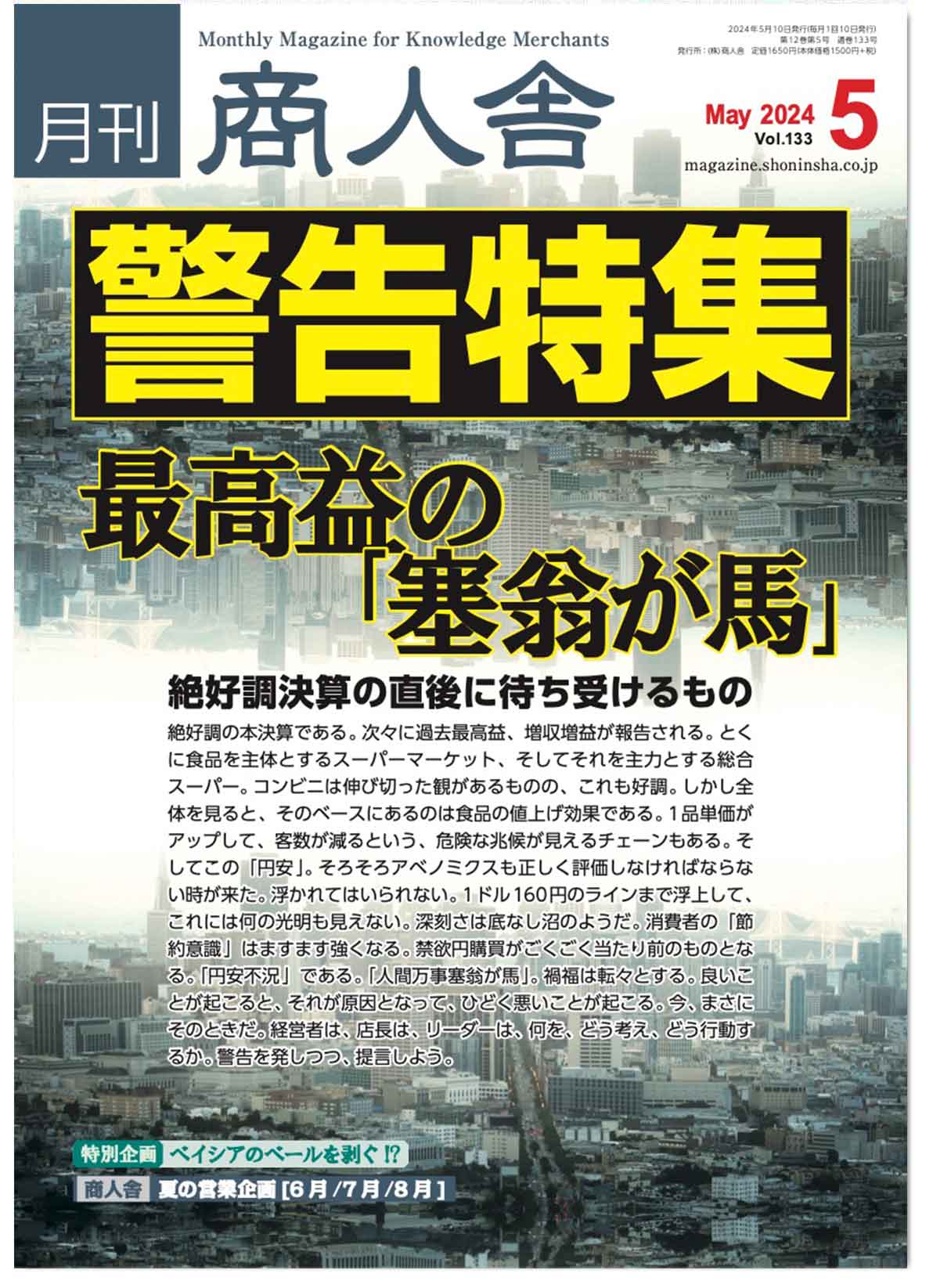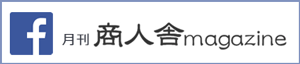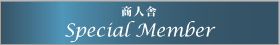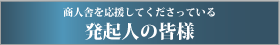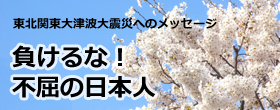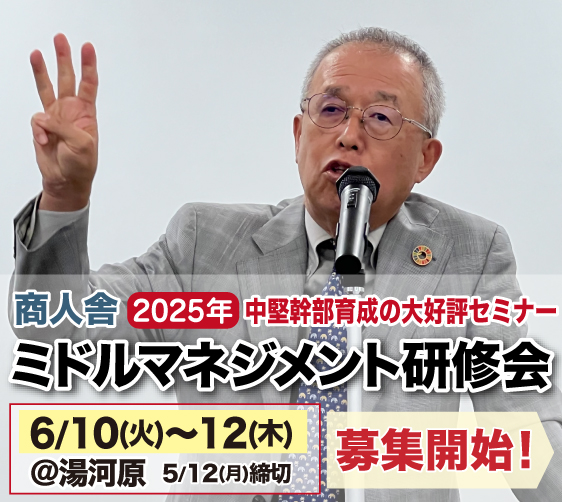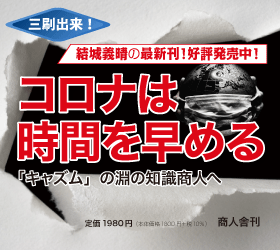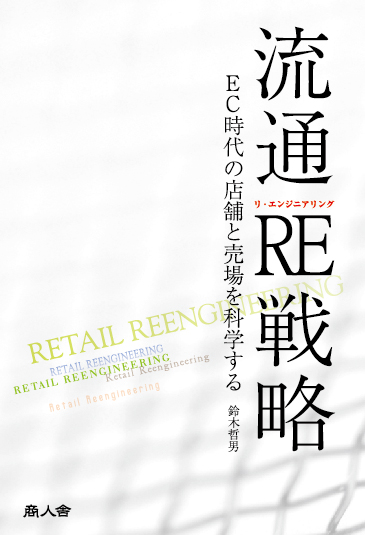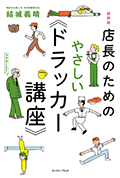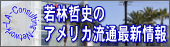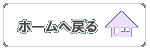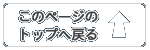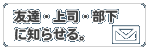結城義晴の毎日更新宣言ブログに、
毎日投稿してくださる。
吉本一夫さん。
USMHにいなげやが加わるブログに対して、
コメントしてくれた。
「求心力で成長する自力本願型と、
遠心力で成長する他力活用型。
その違いがどこで生まれるのか不思議です」
「ビジョン実現のためにどちらが
より確度が高いかという単に選択肢の問題なのか、
或いは創業時からのDNAの問題なのか。
そこがよくわかっていないと、
M&Aの失敗につながる気がしています」
素晴らしいご指摘。
「求心力の自力本願型と
遠心力の他力本願型」
M&Aは経営者の意思決定によって実行される。
したがってトップマネジメントが、
もともと独立独歩型なのか、
仲間とともに歩む共同型なのか。
それが基調になる。
しかし業界や業態の競争環境が、
影響を与えている場合も多い。
小売業は有店舗事業です。
有店舗事業は一に立地、二に立地、
三四がなくて五に立地などと言われる。
つまり立地争いとなる。
先にいい立地を抑えられたら、
あとから出て行っても商売はしにくい。
それから商勢圏も早い者勝ちです。
あるエリアにドミナントを築いてしまえば、
あとからそれを食い破るには、
大変なエネルギーが必要となる。
そこですでにある店、
すでにあるドミナントを、
買収、あるいは経営統合することになる。
小売業のM&Aの特徴。
チェーンストアとなった小売業は、
経営統合こそ成長の早道なのだ。
日経新聞の今月の「私の履歴書」は、
日本製鉄名誉会長の三村明夫さん。
製鉄業でも八幡製鉄と富士製鉄が、
1970年に合併して新日本製鉄となり、
さらに2012年に住友金属工業と統合して、
日本製鉄が生まれる。
店舗事業でなくとも、
企業の巨大化と競争状況によって、
M&Aは起きてくる。
こちらは産業の中で、
トップか、2位、3位かが、
営業上も経営上も意味を持つことが根拠となる。
私の言う寡占や鼎占、複占。
都市銀行はメガバンク三行となり、
製鉄は日本製鉄、JFEHD、神戸製鋼所、
そのあとを日立のプロテリアルが追う。
食品では食肉製造業が、
日本ハム、伊藤ハム米久HDが2強で、
そのあとにプリマハム 、スターゼンが続く。
ビール業界はずっと、
アサヒ、キリン、サッポロとサントリーの寡占だ。
産業が成熟してくると、
規模のメリットが追求されて、
どうしても上位集中となる。
日経新聞の「イブニングスクープ」
「セブン、本部主導で値引き推奨」

セブン-イレブン・ジャパンが、
5月から「値引き」を始める。
かつての鉄則が変わっていく。
システムによって商品の販売期限を店に知らせる。
仕様を統一した値引きシールを用意して、
本部主導で値引きを推奨する。
対象商品はおにぎりやサンドイッチ、弁当など。
約300品となる。
廃棄する数時間前に値下げシールを貼る。
ネーミングは「エコだ値」。
20円、30円、50円、100円の4種類の値引き。
パーセントではない。
各店の手書きするタイプも用意する。
値引きは最終的には加盟店の判断になる。
昨2023年に実験をした。
直営とフランチャイズチェーンの約220店。
店舗の廃棄額は1割程度減り、
店舗の1日当たり売上高は増えた。
現在は廃棄商品の原価の15%は本部負担だ。
廃棄が減れば本部の収益も底上げされる。
もちろん加盟店の利益も上がる。
セブンはながらく「値引き」や「見切り」を、
禁止してきた。
しかし現状は、
全体の約3割が恒常的に値引きする。
公正取引委員会が2020年に見解を示した。
本部による加盟店の値引き制限が、
独占禁止法違反に当たる可能性がある。
それが大きく変わって、
セブンは本部推奨となる。
他はまだ加盟店の判断で行う。
コンビニ産業も典型的な鼎占である。
セブン、ファミリーマート、ローソン。
そしてファミリーマートとローソンは、
積極合併の他力本願型で、
国内セブンは自力本願型だ。
『岡田卓也の十章』という本。
私が商業界社長を辞するときに、
残してきた本だ。

その第六章のタイトルは、
「企業の成長は合併の歴史である」
この章の最後の言葉。
「絶えず、社内に危機感を持たせ、
絶えず革新していかなければ、
企業は三十年たつと必ずおかしくなる」
「だから、わたしは、そうなる前に、
会社に大きな改革を促すために、
『変化』を選択してきた」
岡田卓也の経営の神髄。
合併は社内に変化を強要するものだ。
これは単純な他力本願の合併とは異なる。
他と力を合わせるときに、
その化学反応を変化の原動力にする。
商人の本籍地と現住所。
ビジネスマンの本籍地と現住所。
社会人の本籍地と現住所。
一定の規模を超えた店舗小売業の場合、
この本籍地と現住所の概念は、
不可欠のものとなってきた。
新入社員がすぐに辞めてしまう場合は、
本当の意味の本籍地にはならない。
それは残念なことだ。
〈結城義晴〉