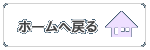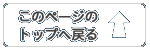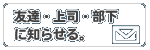第6話 転校2011年9月7日(水曜日)
やはり、不得意な英語は難しい。
上達もしない。チンプンカンプンだった。
教室の真ん中の一番前に座って、毎日、毎日、まばたきもしないで女の先生をじっと見ていた。
睨んでいたと言った方が、正確だったかもしれない。
2週間後、この女教師に「放課後、残れ」と言われた。
まだ25歳の太った白人の先生だった。デートに誘われるのかと思った。やるだけならまあOKか?などと勝手に想像した。
しかし彼女に言われたのは、「あなたは何を考えているの?これ以上見つめないで、恥ずかしい」
彼女は本気で迷惑している雰囲気だった。
「わかった」とは言っても、先生の顔を見ずに授業を受ける方法は知らない。
その翌日から、より一層睨みつけるようなまなざしで、見続けた。
とにかくジョージ君は一日も早く、英語学びたかった、真剣だったのだ。
一カ月ぐらいたつと、いろいろなことがわかってきた。
英語のクラスは9段階あるということ。
ジョージ君のクラスは、レベル3だということ。
4年制の州立大学に入ることができるレベルは8以上だということ。
しかし、3カ月も英語のクラスに通い続けている青山学院や日本女子大学の英文科の女の子でさえ、レベルは5~7だった。
寮費は食事・授業料込みで550ドル。当時の為替は、円が1ドル280円だったので、ジョージ君のサラリーマン時代の2カ月分だ。持ってきた金は3650ドル。この調子だと半年で食いつぶしてしまう。
3カ月、6カ月、9カ月滞在して、ほとんど英語が上達することなく、帰って行く友があとを絶たなかった。一部の金持ちの子弟を除けば、社会で働いてきた女性や青年たちばかりであった。
3年も、5年も、人によっては10年もひたすら金を貯めて、憧れのアメリカに英語を学びにきていた真面目な留学生が多かった。でも多くの短期留学は無念な結果に終わり、来た時と変わらないレベルの英語力で帰国した。
ジョージ君はすぐに悟った。
ここの英語学校は、英語を学ぶのには適さない。
当然である。先生以外の生徒は、英語のわからない外人ばかりなのだ。
辞めることを決意した。
しかしここを辞めるには、他の学校に移らないといけない。
授業料を取らない学校があると聞いた。
それはアダルト・スクール(成人学校)だった。移民者のために学校のことである。
ジョージ君は知り合いを通じて、サンフランシスコから1時間半ほど内陸に入ったストックトンにあるアダルト・スクールのF-1(学生ビザ)の申請書を手にいれた。
トランスファー(転校)しよう。
仲間達に話をした。それは無理だろうと誰もが言った。今まで何人も挑戦したが、誰も成功しなかったらしい。
英語学校の校長には、「書類にサインをしない」と言われてしまった。
「駄目だったら、結局アメリカに来た時と同じレベルの英語力で帰るしかないだろう。会社を辞めてまで来たんだ。それだけは出来ない。俺はやってみるよ」
そこで、すでに半年もいる英語レベル8の女子学生に、校長との交渉の通訳を頼んだ。
彼女は間もなく、州立大学に転校する予定だった。
2人で校長に会いに行った。彼女がジョージ君の考えを校長に説明し、書類にサインをしてくれるかと聞いてくれた。
返事はもちろんNOだった。
この時、ジョージ君は通訳を他人に頼んだことが、間違いだったと感じた。
意を決した。自分で言うことにした。
“I am different from students like her. I was a businessman in Japan. This school is not good for foreign student to learn English, I want to learn English with native speaking Americans. So I want go to Adult school and live with American family.”
(俺は他の日本人学生と違う、日本ではビジネスマンだった。この学校では実践英語は学べない。アダルト・スクールに行って、アメリカ人の家にホームスティをして、英語を学びたい。だから転校したい。)
校長は怒った。ケンカ腰だった。
「黙れ。今、駄目だと言っただろう。私ども学校のビザでアメリカに来て、一カ月で辞めてもらっては、元が取れない。最低、半年はいろ」
意味を理解するには、彼女の通訳が必要だった。
ジョージ君は繰り返した。
「半年経てば金は無くなる、俺は人生をかけてアメリカにやって来た。誰にも邪魔はさせない。ストックトンには、私の空手の友人でFBIの弁護士がいる。彼に相談して、外国人を食いものにしている英語学校のことを暴露する」
下手な英語でそのようなことを伝えた。
ジョージ君が部屋を出ようとしたとき、校長が言った。
「ちょっと待て。今、ワシントンのプレジデント(社長)に電話する」
彼は長い間、話をしていた。それは、わずか10分ほどだったかもしれないが、ジョージ君には非常に長い時間に感じられた。
運命を左右する時間だった。奇跡を信じて待った。
彼は受話器を下ろした。
「お前、勝手にしろ。俺はサインをしない。社長もそう言っている。アメリカの移民局に行って、強制送還でもされろ」
駄目だった。
しかしジョージ君は困難に当たると、俄然、ファイティング・スピリッツが出るタイプだった。
飯さえ食えれば、怠けもする。マンガの“ショージ君”のごとく、間抜けなお人よしでもあったが、敵が現れると、猛然とやる気が出てきた。
どれがジョージ君の本性なのか、彼自身、まだわかっていなかった。
やるしかない。
翌日、学校をさぼってサンフランシスコの移民局に向かった。
シスコに到着するバス停の前で、日本語がわかりそうな女性を探した。
運よく、あまり背が高くない日系2世の女の子を見つけた。
「移民局の場所を教えてください」
事情を話した。
彼女は時間があるので、連れて行ってやると言ってくれた。
移民局の前には、たくさんのメキシコ人や外人が並んでいた。
1時間半も待たされた。この2世の女の子は、親切にもずっと私のそばを離れなかった。
彼女は拙い日本語で言った。
「大丈夫よ。私のお父さんたちも日本から来て、頑張ったの。凄く苦労したのよ、応援するわ」
涙が出た。アメリカ人の親切さに感銘した。
私の番がきた。彼女が私の状況を説明してくれた。
「彼はアメリカの大学に入るために来たのに、英語学校の環境が悪く、英語を学ぶ状況にないそうです。ストックトンのアダルト・スクールに行けば、ホームスティが可能になり、英語がもっと学べます。だからこの書類にサインをしてください」
すると、なんと移民官は、「OK」と言って、サインをした。
ほんの数分のことだった。
「案ずるより産むが易し」
カルフォルニアの青い空が涙眼に射しこんできた。
目の前には、日系のエンジェルがいた。
ありがとう。涙が止まらなかった。
ああ、生き延びた。
彼女は「バーイ」と、名も告げず去っていった。
申し訳ないことをした。名前と住所くらい聞くべきだった。
翌日、校長に会って、転校のことを告げた。
すると、昨日とは打って変わって、彼は笑顔で私を褒め称えた。
「良くやったね。アメリカではそのようにして生きるのだよ。でも他の学生には言うなよ。言うと営業妨害で訴えるぞ」
ジョージ君はこれ以上の問題を抱え込むのはいやだった。
握手を求めてきた彼の手を握って、「Thank You」と言って、別れを告げた。