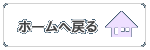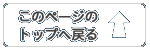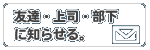第11話 初めてのデート2011年10月12日(水曜日)
シドニーと出会ったその夜、ジョージ君は辞書を片手に、生まれて初めて、英文の手紙を書いた。
ジョージ君から電話はしなかったが、シドニーからは一度電話があった。
相手の顔を見て話す英語は、なんとなくわかるような気がしたが、表情が見えない電話での英会話は、チンプンカンプンだった。
彼女との電話での会話は、しばしば沈黙せざるをえなかった。
1週間後、創価学会NSGのミーティングで再び、シドニーとキミさんと会った。
キミさんが「シドニーは、ジョージ君は英語がほとんど話せないのに、どうして英語の手紙が書けるのかと非常に驚いている」と言った。
日本の英語教育がおかしいからだと説明したが、理解できないようである。
「会話は幼児でもできるが、ジョージ君の文章はアメリカの幼児には書けない。なのにどうして会話はできないのか?」とキミさんに言われてしまった。
シドニーが自分に惹かれたのは、容姿(アメリカ女性好み?)と情熱的な英語のスピーチだと、ジョージ君は勝手に思っていたが、キミさんいわく、ジョージ君の英語のスピーチは、ほとんどわからなかったようだった。
ただ、素朴で、謙虚でやさしく、正直で親切。一緒にいたら安心できる。アメリカ人にないものをすべて持っているような、そんな気がしたらしい。
彼女の両親は離婚し、今、悲しみのどん底にいるとも聞いた。
シドニーにはやさしい大人の男友達が必要なんだと、キミさんは説明くれた。
とにかく、その日ついにデートの約束をした。
翌日、彼女の家に迎えに行った。
人生で初めて買った、ピカピカの中古車は、ポンコツだが、まだ動いていた。
シドニーの家に行くと、彼女はハサミを持ってきて、「髪をカットしてあげる」と言った。
彼女の父親は理容師で、彼女も美容師になる予定でいた。
ジョージ君はアメリカに来て2カ月間、一度も散髪に行っていなかったことを思い出した。
シドニーはそのボサボサに伸びたジョージ君の髪が気になっていたらしい。
うれしそうに髪を切り始めた。
ジョージ君は、女友達に髪を切ってもらうなど、初めての経験だった。
やさしい子だ。
ハワイで会ったオーストラリア人の女数学教師、ハワイからのフライトでハグをしてくれた2名のスチュワーデス…。
日本の女性以外はやさしくないと思っていたが、彼の常識は見事に覆された。
汚れたジョージ君の髪の毛をやさしく撫で、丁寧に刈りながら、時々目が合うと微笑し、口ビルに軽くキスを何度も何度もしてきた。
その無邪気で素直な愛情表現が、ジョージ君には新鮮だった。
素直にうれしかった。
生まれて初めて体験する、女性からの愛情表現だった。
髪は決して期待どおりの刈り方ではなかったが、気にならない。
ヘアカットは終わった。
さあ、景色の良いところ行こう。
ジョージ君の住んでいるストックトン市はサンオーキンデルタ地帯と呼ばれている。
ヨセミテ公園のあるシェラネバダ山脈のあたりから流れてくるサンオーキン川と、オレゴン州とカリフォルニア州の境あたりから流れ出るサクラメント川がこのあたりで合流し、デルタを形成し、やがてサンフランシスコ湾に流れている。
デルタ地帯にはたくさんの運河が掘られ、内陸にありながら、ストックトン港とサクラメント港には、当時ロシアや日本から1000トンを超す大型貨物船が農産物を買い受けるために入港していた。
ジョージ君たちは運河の土手に車を停め、芝生の上に転がった。
雲ひとつない青空で、360度、運河と農場しか見えない。
遠くにはヨット・ハーバーが見えた。
人気のない空間で、自然と2人は抱き合っていた。
やがてキスが始まった。
シドニーは、いきなり舌を入れてきた。
ジョージ君が体験したことない、ぶ厚い舌と唇であった。
ベテランの年増の女に襲われたような気がした。
初めは情熱的に彼女の唇を舐めまわし、舌を絡め、軽く噛みついた。
しばらく経った。
キスはまだ終わらない。
ジョージ君はキスがあまり長いので、空を見たり、横を向いたり、気もそぞろに義理キスを続けたが、いつまでもキスは終わらなかった。
信じられないくらい長い時間だった。
思わず時計を見た。
20分近く経っていた。
それでも終わらない。
しだいに脳が反応し始めた。
キスによって男の性感が反応した瞬間だった。
女のことは知らないが、男は射精でしか性感を感じないはずであった。
これは不思議な体験であった。
驚きであった。
アメリアは偉大だ。
アメリカは高校生でも、この感覚をすでに体験している。
アメリカ万歳!
尊敬の念が湧いてきた。
この間、ジョージ君は一切、手を使っていなかったことに気づいた。
シドニーの胸に右手を乗せた。
白いシャツには赤いボタンがついている。
それを片手で外そうとしたが、うまくいかない。
両手で、上から3つのボタンを一気にはずした。
日焼けしていない、雪のように白い乳房と2つのピンクがかった乳首が露出した。
無我夢中で左の乳首を口に含み、右の乳房をやさしく揉み始めた。
彼女が何か言っている。
「プリーズ テイク オフ マイ パンツ?」
「何言っているのだ?スピーク、アゲン、スローリー」
「パンツ オフ」
パンツが離れる?
それは脱ぎたいってことだ。
どうして、この場でトイレに行きたいのだ?
鈍感で初心(うぶ)なジョージ君には、その意味がすぐに理解できなかった。
やがてジョージ君は、その英語の意味が理解できた。
真っ青な空の下、穏やかな4月の太陽がまぶしい。
彼女の白い下腹部が見えてきた。
その下を、すぐ見る勇気はない。
いや、時間をかけたかった。
映画や雑誌で見た肌より、若い彼女の肌は、はるかに美しく輝き、眩しかった。
有名な写真家、荒木経惟や篠山紀信も体験したことのない被写体に思えた。
ギリシャ彫刻で見た、ビーナス(美の女神)のようでもあった。
西洋人は、なぜ古代から女性の裸を描き続けてきたか、よく理解できた。
美しい。
雲ひとつないカルフォルニアの陽光に輝き、風に微かに揺れた金色の毛が見え始めた。
これ以上は我慢できない。
しかし、ジョージ君の辞書には、「1度目のデートで手を握る、2度目のデートではキスをする、3度目は???をする」
そこまでは書いてあったが、初デートでここまでエスカレートするのは想程外であった。
瞬間的に逃げたい気持ちになっていた。
その時、犬が視界に入った。
「シドニー、犬がいる?」
「あ、あれはコヨーテよ!」
一瞬、二人の熱情に水が差された。
ジョージ君はとっさに言い放った。
「日本人は、太陽の下、青カンの習慣はない。人が来るかもしれないし、落ち着かない。君の家に行こう。」
いつも土壇場で逃げられるジョージ君だが、今回は自分から逃げた。
「この時間なら、パパはまだ帰っていない。いいわ、行きましょう。急いで!」
堰を切ったように、2人は彼女の家に向かって車を走らせた。
シドニーの家に到着し、ドアを開けると、そこにはいないはずの父親がいた。
仁王のようなドイツ系の大男が立っていた。
「ハロー」と、挨拶がやっとできた。
「シドニー、俺は帰る、さようなら」
逃げるように立ち去った。
泣きべそをかいている彼女を後にした。
それにしても東京の若者の性は悲しい。新宿や渋谷のわびしい密室での行為に比べれば、青空の下、太陽の下で、誰に気をつかうことなく、抱き合う行為は、古代からの人間の最大の楽しみだったはずだ。
数日後、キミさんを訪ねた。
「ジョージ君、シドニーとの仲はどうなっているの」
「どうなってって…」 とあいまいな返事をした。
キミさんは思わず、聞き返した。
「あなた、やっていないでしょうね?まさか、セックスをしていないでしょうね?」
「ええ、大丈夫です」
「ジョージ君に大切なことを言い忘れていた。アメリカでは成人が、18歳以下の女性と関係を持つことは、法律違反なの。刑務所にブチ込まれるわよ。いい、わかった?」
助かった。
アメリカの高校生は進んでいる。
危なかった。
こんなことで犯罪者になるわけにはいかない。
会えばお互いの熱情は止まらない。
シドニーとは別れることにした。
その日の夜、ベッドで天井を見ながら、キミさんが言っていた、シドニーがジョージ君を好きになった理由を思い出していた。
素朴で、真面目で、正直で、親切で、熱心。
これはすべて、日本人の特徴である。
そうか、アメリカ人に無いもので勝負をすれば、たとえ寸足らずでもアメリカ女性に通用する。
これはアメリカでもっとも成功した日本人の中の一人で、ライス・キングと呼ばれた国府田敬三郎の「アメリカで勝負をする時は、徹底的に日本人であれ。それしかアメリカ人との差別化はできない」という言葉に通じるものだった。
それはアメリカに住む多く日本人や日系人にとって、まさに生きる知恵となる言葉であった。
ところで、好色一代男のアメリカ版はまだまだスタートしない。
アメリカに来て、もう2カ月も経っていた。