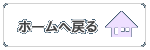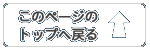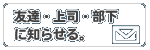第12話 バス・ボーイ2011年10月19日(水曜日)
渡米3か月、中古車に大金をはたいたジョージ君は、ホームステイをして当面の生活には困らなくなったが、将来の授業料を稼ぐために働かざるを得なかった。
もちろん、外国人留学生の就労は禁止。
見つかれば、強制送還だ。
しかし、背に腹は代えられない。
たくさんの外国人留学生が、それを承知で働いていた。
真面目にアメリカの法律を守り、金が尽き、志半ばにして帰る友もたくさんいた。
どちらかと言えば、彼らは日本で就職経験のない若者だった。
ようするに日本社会を知らない世間知らずの面々だった。
米国帰りで多少英語が話せれば、何かしら評価されるだろうという、甘い期待を抱く若者たちだった。
サラリーマンを辞めてきたジョージ君には、そんな期待はなかった。
最初に働いたのは、レアステアと呼ばれる、当時はやりのファミリー・レストランだった。皿洗いである。なんと、皿を機械で洗うことには驚いた。
当時の日本では皿はまだ手で洗っていた。
忙しい夕方のディナー・タイムが終わり、ジョーと呼ばれるシェフが近づいてきた。
「俺はギリシャ人、日本人野郎、仲良くやろうぜ。ところでジョージ、お前は何を食べる?」
雇用の条件は夕食付きであったが、彼が言っている意味が、よく解せなかった。
「何とは?何を食べてもいいのか?」
「そう、メニューから選べ。だだし、一番高い肉と、海老はだめだ。後は何でも食え」
当然2番目に高いステーキを食べた。
それがニューヨーク・ステーキだった。
これには本当に驚いた。
英語学校の寮の食事も食べ放題、飲み放題だった。
日本での学生時代、何度もレストランでアルバイトして来たが、日本では、従業員はサトイモの煮っころがしの仕出し弁当か、シェフが作る卵入りの味噌汁しか知らない。
メニューから従業員が食事を選んで食べるなど想像もつかなかった。
ジョージ君はステーキの夕食に感動した。
これなら毎日だだ働きでも良い。
アメリカは豊かだった。
2週間ぐらいしたある日、マネジャーがやってきた。
「おいお前、ゴミを捨てた後、必ず裏のドアの鍵を閉めているか?」
「もちろん」
「今後も必ずそれを実行するように」
「Yes Sir」
体育会系は返事がよかった。
これはアメリカでも好評だった。
どうも店内倉庫から物が無くなっているようだった。
ジョージ君がごみを捨てて戻る。
しばらくすると、一人のシェフが必ず煙草を吸いに外に出た。
注意して観察してみると、外に出たシェフがドアを開けて中に再び入り、持ち場に返る。
しばらくすると、知らない誰かがそのドアから入ってきて、倉庫の物を運び出していた。
次の機会に、ジョージ君はそのシェフが、煙草を吸って中に戻った後、ドアの施錠を確認しにいった。
やはりドアのカギは開けられていた。
「彼は泥棒の仲間?」
彼らはシェフとグルだった。
マネジャーに言うわけにはいかない。
仕返しが怖い。
ましてこちらは非合法で働く身。
内緒でギリシャ人のシェフ、ジョーに気づいたことを伝えた。
彼は知っていた。
「マネジャーも、うすうす感づいているから、関わるな」と言ってくれた。
ジョーは陽気な男だった。
「日本人は背が低い、ギリシャ人も背が低い。なにしろ、ギリシャには酪農がなく、NO ミルク。だから背が低い」と言っていた。
「ギリシャ、ローマ時代は、ギリシャ人ももっと大きかった。ローマの兵士は平均180センチ近くあった」と、誇らしげにも語った。
ジョージ君は、ずーっと後になってJACという会社で働くようになるが、その最初の仕事は、IHOPのレストラン創業者のセミナーでの通訳だった。
講義は、当時の全米一のファミリー・レストラン、サンボーズの倒産劇を語るものだったが、倒産にいたった直接の要因は、オーナーが変わった時に、マネジャーのボーナス制度を無くしたため、あちこちの店の店長が、翌日から売上金を猫ババしたからだという説明だった。
1200店舗の1100名の店長が猫ババをし、その彼らは首になった。
(自伝には関係はないが、その時の日本からの客は、四国・高松のスーパーマーケット・マルヨシセンターの佐竹社長だった。同志社大学ラグビー部出身。最初の仕事で忘れられない)
ダイエーがハワイでアラモア・ショッピング・センターを買収した時も、従業員のキャシャーが友人や家族が来ると、キャッシュ・レジスターを鳴らさなかったと後で聞いた。
アメリカ企業の損失・倒産の多くは内部犯行に絡むものであった。
さて、ジョージ君は皿洗いよりも、バス・ボーイが金になることを聞いた。
バス・ボーイとは、客が食べ終わった皿をかたづける仕事だ。
ウェイトレスが稼いだチップの15~20%をバス・ボーイがもらえるので、皿洗いより実入りが多かった。
新田君というアルバイト学生は、一日に給与以外に20~30ドルの現金を毎日稼いで帰った。
彼の紹介でジョージ君は、バイキング・スタイルの中華レストラン、サンパンで働くことになった。
日銭の20~30ドルはジョージ君にはうれしかった。
1ドル250円で計算しても5000円以上になる。
バス・ボーイとして一緒に働くメキシコ系の高校生がいた。
色は白く、白人のように背が高い。
180センチをゆうに越えていた。
その彼が、真面目に働くジョージ君に嫉妬した。
英語がわからないことを理由に、何かと難癖をつけてきた。
ジョージ君は何があっても笑って仕事をこなした。
このメキシコ系アメリカ人の高校生はますます苛立った。
ジョージ君が逆らわないので、途中から調子に乗って、命令までするようになった。
怠け者で常識もない18歳の高校生が、大卒で社会経験豊かな26歳の男に命令をして、ケンカまで売ってきた。
兄貴は厨房で働いていて、二人でジョージ君をからかい、言葉でいじめた。
その兄貴は、高校時代にはアメリカン・フット・ボールの選手で、やはり185センチ、体重は100キロ以上と大柄だった。
ジョージ君に向かって、「ファク ユー、アス・ホール、ユー ガッダメ、マザー・ファク」などと汚い言葉を連発した。
ジョージ君は、意味がわからないふりをして無視し続けた。
時々本当に意味がわからない単語が出ると、聞き返した。
わからない言葉はすべて汚ない言葉だった。
その言葉の意味をジョージ君に説明しながら、彼らは奇声をあげ、喜んで、ジョージ君を笑い飛ばした。
毎日言葉の暴力はエスカレートしていった。
肉体的暴力に繋がるのは必須の状態であった。
オーナーの中国人マネジャー、ジャックが心配してジョージ君を呼んだ。
「ジョージ、笑っているだけでは、彼らの行動はエスカレートするばかりだ。骨のある心を見せないと、バカにされるばかりで、問題は解決しないぞ。強く抗議するなり、ガツンと言い返せ」
彼は153センチ余りの小男、60歳過ぎの老人だった。
アメリカ社会の差別の中で、この体の小さい香港人が、いかに気迫をもって、アメリカで戦ってきたかを話してくれた。
同じ東洋人のジョージ君の行く末を案じていた。
「ジョージ、戦う意思を見せるのだ」
抽象的な表現であり、実際にジョージ君がこの場面で何をすべきかは言わなかった。
ただ、このままではいけない、とジョージ君も強く感じていた。
翌日は金曜日だった。
ランチというのに、チャイナ・タウンの祭りの前で、異常な忙しさだった。
皆疲れ果てていた。
従業員が集まって遅いランチを食べていた。
この高校生の兄貴がフォークを落とした。
それをジョージ君に拾ってくれと言った。
ジョージ君が腰をかがめた瞬間、彼の弟の高校生が、ジョージ君の尻を蹴飛ばした。
ジョージ君はもんどり打って床に転がった。
従業員たちは大笑いをした。
そこには3名の中国人の女子従業員と4名の白人とメキシコ系のウェイトレスがいた。
ジョージ君が意識している白人の可愛い子もいた。
女の前で恥をカカセラレタ。
冷静さを失うには十分な条件である。
それ以上にジョージ君を怒らせた言葉があった。
「Hey, little Jap. ついでに床でも舐めろ」
ジョージ君は頭で「Jap」を反芻した。
日本人をバカにしている。
血が逆流して来た。理性を失いつつあった。
日本人全体をバカにした言葉は見逃せない。
私憤では無くなったのだ。
怒れ、ジョージ!
ここのマネジャーのジャックならどうする?
彼の顔を見た。
無表情だった。
ジョージ君、これは、お前がアメリカで生きていくために試練だ。
自分で解決しろ、と言っているようだった。
「Get out、Let`s fight!」
ジョージは親指で外を指さした。
高校生は喜んで応じた。
「面白い。ブラザー、ジョージがやると言っているぞ」
ジョージ君は先に外に出た。
兄弟二人は肩を振りながらついてきた。
その後に、すべての従業員が続いたのである。
真昼の決闘のようなカッコいいものではないが、大人が年下の高校生と大学生相手とケンカするとは情けない気もした。
それより悲しかったのは、恵まれない少数民族間の戦いであること。
それも恥ずかしく感じていた。
相手が白人の大人なら不足はないとも思えた。
しかし、若いが故に、ほっておけば相手はますますエスカレートするばかりだ。
やるしかないのか?
外国でのケンカはできるだけ避けるべきだと思っていた。
しかし、人生を、青春を賭けて太平洋を越えてやってきたのだ。
相手が誰であろうと、邪魔する奴は許さない。
アラブ人との戦いや、その後のいろいろな体験で、喧嘩も恋愛も仕事も、本気な奴が勝つことを多少学んできた。
ジョージ君は覚悟を決めたのである。
やってやる!
兄貴の方が少しビビってきた。
ジョージ君の気迫がはるかに勝っていたのだ。
正直185センチの大男二人相手のケンカ経験も自信も無かった。
大学時代に、ガラの悪さで有名な関西の私学応援団の男たちが時々、ジョージ君の大学の日本拳法道場に遊びにきていた。
「ワシはケンカ10段」と自称する186センチの副応援団長もいたが、防具をつけての殴り合い。
蹴りの前に彼らは1分ももたず、ジョージ君たちの敵ではなかった。
でも今回は二人、しかも道場の練習ではない、ケンカだ。
ルールのない喧嘩が始まるのだ。
兄貴が殴りかかってきた。
へっぴり腰である。
こんなパンチが当たるはずはなかった。
腰をかがめ、狙った通りに彼の顎をひっぱたいた。
体力に勝る大男をむやみに殴ったり、蹴っても効果はない。
狙うのは人中、体の真ん中、目か、鼻か、顎か、ミゾ落ちか、キン玉しかない。
一番後遺症のない急所である顎を選んだのだ。
軽くたたいたつもりだったが、カウンターぎみのパンチを浴びて、兄貴は膝を折り曲げて倒れた。
簡単に勝負がついた。
自分のパンチ力にジョージ君は正直驚いた。
蹴りを使わないですんだ。
ジョージ君は自分の蹴りには殺傷能力があることを自覚していた。
それには安堵した。
弟の顔をから血の気が引いた。
当時、ブルース・リーの映画「燃えよ、ドラゴン」が異常なくらいヒットしていた。
中国人や日本人を見ると、ヘンな奇声をあげたり、カンフーのマネをする人が多かった。
そのせいだったかもしれない。
彼らは完全に戦意を喪失していた。
店のマネジャーのジャックの顔を確認した後、ジョージ君はすぐ車に乗って、ホームステイ先に帰った。
何かあれば、ホームステイ先に連絡がある。
彼のホームステイ先は、このストックトン一の名門ファミリー。
彼らが守ってくれるだろう。
彼らは本当のジョージ君は大人しく正直者であることを知っている。
ジョージ君は完全に居直っていた。
その日は何事もなかった。
翌日もレストランに行った。
逃げたと思われたくなかったからだ。
二人は最初、気まずさそうにしていたが、ジョージ君の呼び名は変わっていた。
「ボス、ジョージ、You are my Boss」
高校生は笑って叫んだ。
「ボス、I’ll do anything for you. ジョージのためなら、何でもする」
兄貴の方は手を差し出して、握手を求めて来た。
アメリカ人の現金な姿にジョージ君は面食らった。
でも非難できないと思った。
逆にそれはアメリカで生きる厳しさだと思えた。
フロンティアの気風が残っているアメリカでは、強い奴に逆らうと生きていけない。
政治もそうだ。
決まる前までは意見を言うが、決まれば従う。
日本は違う。
反対したことは、決まって後も、従わないで生きていける。
アメリカならそのような奴は排除される。
少なくとも尊敬されない。
日本は甘い社会だと思った。
このことを一番喜んだのは中国人のジャックだった。
噂が店内を駆け巡った。
「日本人を怒らせると本当は怖いのね」
しかし、ジョージ君が意識していた可愛い子ちゃんからは何の言葉もなかった。
ジョージ君は学んだ。
海外では謙譲の心や、控えめの心は、常に役に立つわけではない。
時には、戦う意思を見せないとアメリカや国際社会では通用しない。
これから何度戦いに巻き込まれるのか?
厳しいアメリカの生活の現実に身が引き締まる思いがした。