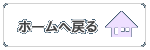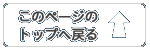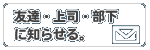第13話 アメリカン・ファミリー2011年10月26日(水曜日)
ホームステイ先の夫妻が2カ月のカナダ旅行から帰ってきた。
その間、近所では良からぬ噂が立っていたらしい。
夫妻がいない間、ジョージ君は何もしないで遊んでいたとか、
子供たちはめちゃくちゃな暮らしをしていたとか、
ベティーのクーガーのオープンカーを私用で乗りまわしていたとか。
でもジョージ君はスーパーに買い物に行く時以外は、一度しかクーガーを運転していなかった。
ベティーは、近所からすべて報告を受けていると、ジョージ君に文句を言ったが、ジョージ君は反論をしなかった。
もちろん、その噂のほとんどが嘘であったが、この2カ月で、このファミリーは普通のアメリカ人ファミリーではないとわかっていた。
言い訳は通用しないような気がしたのだ。
夫妻はお互い3度目の結婚。
ハイドン氏が連れてきた3人の男の子も、長男ジョンと次男ポールの母親は同じであったが、三男ハンクの母親は違っていた。
奥さんのベティーも子供が3人いたが、長女のマリーの父親と、長男のワグナーと次女アンネの父親とは違っていた。
ハイドン氏の長男ジョンは、平気で、「父の結婚の理由は彼女の資産と金だ」というぐらいだった。
ベティーは、アメリカで最初にトラクターを発明したイギリス系アメリカ人、フランクリンの孫娘であった。
有名なグレート・キャタピラー社の創業者一族であり、超大富豪。
今でもストックトン市にはフランクリン通りがあり、大学には彼の名前からとったフランクリン・センターまである
フランクリン氏の息子、アートン氏は弁護士で、カリフォルニアの弁護士協会会長まで務めた人であった。
このデルタの街・ストックトンにはたくさんの島があったが、その島の一つを買い取り、敷地6000坪の大豪邸を建てて住んでいた。
カリフォルニアの元弁護士であったニクソン大統領は、2度ほど、このアートン邸を訪問したことがあるらしい。
このアートン氏の一人娘が、私のホスト・ファミリーの奥さんのベティーであった。
一生遊んで暮らすのが仕事のような人たちだった。
ベティーの2度目の夫は医者で、退職後、カリブ海にあるグラネダ島に豪邸を買い、フランス料理の専属シェフを雇い、下男や女中などを使って暮らしていたらしい。
しかし夫が亡くなった後は、故郷のストックトンに戻り、3度目の結婚をして、この地に住みついたらしい。
グラネダ島にはまだ家もあり、シェフも使用人もいて、時々カリブ海に帰って行った。
この街から2時間半ほどのところにも、別荘を持っていた。
1960年の冬季オリンピックが開催されたレイクタホのスキー場、スコア・バレーにある別荘で、毎年冬場になると2カ月ほどスキーに明け暮れていた。
ジョージ君の父が松江城の絵はがきを送ってきたとき、「これはお前の家か」とからかわれ、戸惑ったこともあった。
あまりにも生活が違ったが、それでも日本人としての誇りを抱くジョージ君は、彼らにコンプレックスを感じたり、気遅れすることはなかった。
とにかく、彼らは週末になると必ず、山や川や海に遊びに行った。
信じられないほどにアクティブであった。
毎週金曜日の午後4時ごろからキャンプの準備をし、車2台でモーターボート2台を引きながら、出かけていく。
時々ボートの代わりに、飼っていた2頭のサラブレッドを馬専用の荷台に詰め込んで、野山での乗馬を楽しんでいた。
どれもこれもジョージ君が体験したことのない暮らしであった。
ゴルフ場は歩いて行けるほど、目の前にあったが、「あれは年寄りの遊び」と言って、軽蔑していた。
何度か奥さんにテニスに誘われたが、残念ながらジョージ君はテニスの心得がなかった。
友人、親せき、近所の人が集まれば、雑談はもちろん、歌や踊り、ピアノやクラシック音楽までをも楽しんでいた。
私が日本の中学生レベルの知識で、この曲はシューベルト、モーツァルト、確かこれはべートベン、ショパンだ、と言うと、彼らは大喜びをした。
日本の若者は教養があるというのだ。
当時のアメリカの学校教育ではクラシック音楽の授業がなかったから、彼らの子供たちは古典音楽家の名前を知らなかった。
さらに日本人は数学が得意で、計算ができ、しかも早い。
それが彼らにとっては驚きで、尊敬された。
ジョージ君はすぐに子供たちの数学の家庭教師役をも引き受けることになった。
またジョージ君がリンゴの皮をスルスルと剥くのを非常に珍しがった。
アメリカ人はリンゴも梨も、皮を剥かないで食べていた。
そもそも家庭では包丁は使わない。野菜を切ることもしない。
サラダを作る時は野菜を引きちぎって食べるか、料理用ハサミで切った。
特に子供たちはジョージ君のことを「NINJA」と呼んで、近所の子供を集めてきては、その前でリンゴの皮を剥かせた。
ジョージ君は得意になって、忍者の真似をして、たちまち子供達のヒーローになった。
ある晩、ホームパーティーがあった。
ジョージ君はベティーに「ギターは弾けるか?ピアノはできるか?」と聞かれたが、楽器は何の特技もなかった。
音楽ならピアノやギター、スポーツならテニスをやっていれば、アメリカで友人が容易にできただろうにと、本当に後悔したが、すでに遅かった。
「それでは、お前は何をして私達を楽しませてくれるんだ?」
意地悪な質問がベティーから出た。
とっさに「歌なら歌える」と答えてしまった。
英語の歌は歌ったことは無かった。
外は満月が出ている。
カリフォルニアで見る月は日本と同じだった。
感傷に浸っている場合ではなかった。
無理して、途中をごまかしながら、『ムーン・リバー』を歌った。
すると大拍手、大喝采。
「もっとやれ、アンコール!」の声が掛かった。
ジョージ君は次の歌を歌い始めた。
Stars hang suspended above a floating yellow moon
(天には星がぶら下がり、黄色な月が漂っている)
『Wonderland by Night』という曲だ。
「ワンダフル!」と一人のおばあちゃんが抱きついてきた。
ハイドン氏が大声で叫んだ。
「ジョージ、バリトンのいい声だ」
英語で何とか歌い終えた。
ほっとした。
台湾で買った、エンゲルト・フンパーディンクのコピー盤のLPレコードを何度か聞いていたおかげだった。
日本からの珍客に、近所の人や彼らの友人たちの興奮はおさまらない。
「やめるな、次は何が歌える?」
仕方がない、ジョージ君は叫んだ。
「Next Songは日本語の歌を歌います」
「That is fun, GO! GO! そりゃいいや、面白い、いけいけ!」
日本の月の歌を歌おう。
「月が出た、出た、月がぁ出た~。あ、よい、よい。三池炭坑の上に出た。あんまーりー、煙突が高いので、さぁぞやお月さん、煙たっかろ、さの、よい、よい」
多少の踊りをつけて、炭坑節を歌った。
この聞きなれない節が受けた。
皆大騒ぎになった。
「ジョージは面白い奴だ」
ジョージ君は調子に乗った。
もう止まらない。
坂本九ちゃんの『上を向いて歩こう(SUKIYAKI)』や『荒城の月』、『さくら』、『いつでも夢を』、しまいには中学校の校歌まで歌った。
そして最後は『愛の賛歌』で歌い終えた。
これ以来、近所のパーティーには、ジョージ君はいるかと、いつも声が掛かるようになった。
下手な歌でも、必死の思いでアメリカ人を楽しませようとした気持ちが、受けたのだった。
金持ちたちは人生を楽しむのに貪欲だった。
エンターテイメントが重要なのだと思い知らされた。
それを特技でも技術でもなく、心でカバーできることも学んだのだ。
ラテン音楽が流れてきた。
カリブに住んでいたベティーの得意な世界だ。
やがてダンスが始まった。
踊りが好きなジョージ君は、一人で自然と体を左右に動かしていた。
一番遠くに座っていた、ご婦人が近づいてきた。
紫のドレスを着て、大きな真珠の首飾りをつけた上品な人だった。
ジョージ君は『愛の賛歌』を歌った時、彼女を何度か見ながら歌っていた。
愁いに満ちた婦人が気になった。
年は40代後半かな?
彼女がジョージ君に話しかけてきた。
「貴方は踊れるの?」
「ええ多少なら」
ルンバの曲だった。
ジョージは両手を広げた。
キューバン・ルンバのスタイルである。
彼女はすぐにそのスタイルに気づいた。
二人は踊り始めた。
二人の呼吸の合った見事なステップに、皆が注目するまでに時間はかからなかった。
ベティーが声をかけた。
「ジョージ、彼女は未亡人の大富豪よ。まだまだナイスボディでしょう。二人でどこかに消えてしまいなさい」
そして笑ってウインクをした。
26歳になったばかりのジョージ君には、やはり大年増に見えたが、今となって考えれば、40代後半の女性など、女盛りである。
彼女は弁護士の妻だったが、2年前に夫を亡くしていた。
「あなたは日本人のようね。私の主人は戦後、京都に住んだことがあって、日本を愛していたの。私をいつか京都に連れて行きたいと、いつも言っていたわ。いつかあなたが代わりに案内してくれるかしら」
「大学時代、京都に住んでいました。ダンスも京都で習いました」
「それなら都合がいいわ、これから時々、ダンスに誘うわ。最近、社交ダンスは流行らないので、あなたみたいな若いパートナーは見つからないの。年寄りばかりでつまらなかったのよ」
その後、何度かダンスに誘われた。
会って話すとインテリで思いやりもあり、やさしく、尊敬できるタイプだった。
年齢を考えなければ、理想の女性であった。
ジョージ君は彼女にいろいろと身の上話をした。
英語を勉強するために大学に入りたいが、その資金がないこと、留学生には永住権がないので授業料が高いことなどを愚痴った。
「私と結婚すれば、すべて解決すると言うことね?あなたのビザのために数年間だけ、結婚してもいいわよ。でもたとえそれが打算の行為だとしても、女としては、やはり気になることがあるの。あなたは私を愛せる?」
正直なジョージ君は、すぐに返事はできなかった。
ジョージ君は知らなかったが、彼女の家に出入りするジョージ君のことは、近所で噂になっていたらしい。
“白人の未亡人の家にイエローの若い男が出入りしている”
彼女は仲間内では評判の美貌未亡人だった。
ホームステイ先の主人、ハイドン氏に言われた。
「同じ男として忠告をする。これは警告でもある。用心しろ、男たちが君のことを気にしている。彼女とのダンスにはもう行くな」
人種偏見とジョージ君の若さに対する嫉妬を感じた。
ハイドン氏は続けた。
「彼女には夫の弁護士仲間の独身男やプレイボーイの友達がたくさんいる。彼らは君のことを快く思っていない」
ハイドン氏はいやにしつこく、強く言い放った。
ベティーは敏感に何か感じたのか、ハイドン氏を睨みつけて、「あなたが嫉妬することではないでしょう」と食ってかかった。
「ジョージ、こんな老人たちの言うことや、世間のことなど気にするな。あなたたちの自由よ。男と女はお互い肉体のように無いものを補完するために神様が造ったの。彼女には金があり、市民権があり、人脈もある。あなたには若さや、いろいろな可能性があるわ。でもそれ以外は何も無いでしょう。あなたには彼女の助けが必要よ」
ジョージ君は小さな声で言った。
「彼女のことは嫌いでないが、結婚したらいつか子供が欲しい。でも彼女にはそれは無理だ」
「ジョージ、何を言っているの?今ない物を、特に永住権をとにかく手にしなさい。後のことは、後で考えればいいの。お互いに嫌いになる可能性もある」
金持ちに家に生まれ、自由奔放、刹那的に生きてきたベティーらしい忠告だった。
当時、多くの外国人留学生は、アメリカの永住権を欲しがっていた。
ジョージ君もその一人だった。
アメリカ人女性と結婚して、永住権を手にすれば、公立大学の授業料は無料か、破格に安くなる。
働く自由も手にはいる。
ジョージ君は思った。
“そこまで割り切れるほど、柔軟な頭があれば、こんな苦労して、アメリカで学生などしてない。日本で平凡なサラリーマンをしながら、逆玉でも探せばよかったのだ”
やがて電話が一本あった。
誰かわからないが、声は若くない。
「日本人野郎、彼女から手を引け、さもなくば、君を強制送還してやる」
凄く紳士的で丁寧な口調だったが、その言葉は恐ろしく、真剣さを感じた。
これで彼女との友人関係も終わったとジョージ君は悟った。
それ以来、彼女から電話はなかった。
ジョージ君も電話はしなかった。

つづく