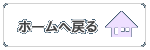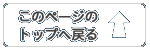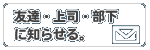第17話 クック(料理人)になる2011年11月23日(水曜日)
アメリカに渡り、最初に通った英語学校の寮の食事に、ジョージ君は不満はなかった。
ストックトンに移った後のアパートでの1ヵ月は、野菜炒めしか食べていなかったような気がする。
安いハンバーガー用のミンチ・ミートとキャベツ、ホウレンソウ、白菜、玉ねぎなど、野菜は変わったが、肉は一貫してハンバーガーミンチのみであった。
日本にいた頃、会社の近くや、葉山マリーナで食べた、ケンタッキー・フライド・チキンの味が忘れられず、時々、ケンタッキーのチキンを食べるのを楽しみにしていた。
マクドナルドも近くにあったが、金が掛かるので行かなかった。
やがて、ジョージ君はホームステイをするが、ホスト・マザーのベティーが作る食事は、毎日、肉料理であった。
牛肉のステーキ、鶏肉、羊肉、豚肉、ハム、時には七面鳥、子ブタのアバラ肉。
とにかく、主食が肉であり、付き出しが、パンであったような気がする。
野菜サラダも必ず付いた。
基本的にベティーの作る食事は、肉の塊、ようするにステーキやハムに塩とコショウで味付けをし、オーブンで焼くという、ごく単純な料理であった。
時々、イタリアンのラザニアを作ったが、日本のような多様なおかずはまったくなかった。
パンを主食、肉をおかずと考えると、おかずは毎日一品だけである。
なんと貧しい食事種類かと、感心するばかりであった。
外食は2週間に1回ぐらいのペース、1970年代後半は、まだまだ外食は頻繁ではなかった。
ジョージ君は、外食があまり好きでなかった。
残った食事は必ず持って帰り、それが無くなるまで、毎日テーブルに並んだからだ。
彼らは残り物がどんなにわずかでも、持ち帰った。
Doggy Bag(ドギー・バッグ、犬のための袋)と呼び、その残り物を家で食べるのである。
ジョージ君は一度冷めたピザやパスタ、ハンバーガーなど、とても食べる気はしなかった。
最初はなんてケチな人々なんだ、と思った。
しかし、たとえ大富豪でも、食べ物を無駄にしないためなのだとわかった時、ジョージ君は彼らの合理的精神に感心し、日本の無駄を思った。
中華には時々連れて行ってくれたが、開店したばかりの、ストックトン初の日本食レストランYONEDAには、行くことはなかった。
ベティーは強調した。
「自分達の子供の世代は知らないが、私が生きている限り、日本食レストランに行くことはない。もちろん、日本人の下で働くことも永遠にない」と目を剥いて言った。
日本食は下層階級の食べ物だと言わんばかりであった。
まだまだ、日本人蔑視の気持ちが彼女には強かった。
これは彼女の育った環境と時代のせいであったので、ジョージ君は特に彼女を責める気持ちはなかった。
ただ、事実として受け止めた。
ジョージ君は中華レストランでアルバイトをして米の飯を食べていたので、ベティーの食事に特に期待することはなく、不満もなかったが、日本食だけは食べたかった。
特にラーメンが食いたかった。
ラーメンとカレーは、いずれも外国が発祥の地にもかかわらず、無性に食べたくなる。
日本人にとって不思議な国民的食事のように思えた。
ある晩の夜、インスタント・ラーメンが無性に食べたくなった。
その気持ちが抑えきれない。
ラーメンを食べられないことが、ジョージ君のアメリカ生活、最大の不幸にも思えた。
深夜に起きて、台所に行った。
お湯を沸かし、インスタント・ラーメンを鍋に投げ入れた。
泡が立ち、袋から具やスープの素を流し込んだ。
香ばしい匂いが、深夜の台所に広がった。
生卵を1個入れた。
独身男の至福の一瞬でもあった。
次第に顔がほころび始めた。
ドンブリらしきものがないので、サラダ・ボールに移し、食べはじめた。
舌が鳴った。
満足感と愉快な気持ちが心に広がっていった。
深夜の階段から人の足跡が聞こえてきた。
幽霊ではない。
ベティーだった。
「ジョージ、何をしている」
「ラーメン・ヌードルを食べている」
「腹が減っているのか?」
「いや、腹は減ってはいないが、ヌードルが食べたかった」
「ああ、そう。ようするにジョージは私の作る食事に不満なんだね。わかった。これから夕食はジョージに作ってもらうことにする。明日、ミスター・ハイドンと相談をする」
ジョージ君に弁解の余地は与えられなかった。
彼女は怒っていた。
至福の時が一瞬にして惨めな時に変わった。
ホームステイはなかなか難しい。
100%の自由はないことを改めて思い知った。
翌日、夕食の時にベティーが口を開いた。
「ジョージは私の食事に不満のようだ。そこで、毎週金曜日は彼が夕食を作ることを提案する」
ハイドン氏は大喜びだった。
「それは良い考えだ。ジョージにやってもらおう」
子供たちも喜んだ。
あまりにも皆が喜ぶので、ベティーは自分の料理は人気が無いと知り、完全に不機嫌になった。
ジョージ君はたかだか、一晩ラーメンを作って食べたことが、このような問題を引き起こしたことに、理不尽さを感じていたが、もう引き返せない。
やがて、金曜日がきた。
「トウフ屋」と呼ばれる日本食料品店で、すき焼き肉や豆腐やこんにゃくなど、家族9名分の大量の食材を、自腹を切って、買って帰った。
$48かかった。
野菜、豆腐、こんにゃく、タケノコなど、様々な野菜を綺麗に切って、大きな皿に並べた。
それだけで子供たちが集まってきた。
「Neat! すごいぞ、整然と切られている、美味しそうだ」
台所にハイドン氏もやってきた。
本当にうれしそうに、「ジョージは我が家のクック(料理人)に昇格だ」
上機嫌で、子供のようにハミングまで始まった。
誰もが食事を楽しみにしていた。
さて、これが正真正銘、彼らが人生で初めて食べる日本食、すき焼きである。
最初に末娘のアンネが、薄い肉をフォークで持ち上げ、「これはナーニ?」
「牛肉だ、口に入れなさい」とジョージ君は叫んだ。
「美味しい、ママ、パパ!こんな柔らかくて美味しい牛肉は初めて!」
その後、肉を求めて家族9名が、鍋に箸やフォークなどを突っこんだ。
豆腐を初めて食べる人が多かった。
当然、こんにゃくも初めて。
竹の子も、「バンブーを食べるのか?」と言って不思議そうに眺めながらも、食べてくれた。
「竹の子とこんにゃくは、繊維質が多いので腸が綺麗になり、がんの予防になる」と言うと、冷やかな目で見ていた、ベティーもやがて食べ始めた。
一つも残さず、すべて平らげた。
肉がまだまだ足らない。
ハイドン氏は「もっと肉を買って来い」と言ったが、ジョージ君は「店は閉まっている」と答え、それは逃れることが出来た。
9名の一家団欒を久しぶりに取り返し、賑やかにすき焼きパーティーは終わった。
ハイドン氏は上機嫌だった。
毎晩でもジョージ君の食事が食べたいとまで言った。
皆があまりにも喜ぶので、ベティーは自尊心が傷つけられ、すごい不満があったようだが、それでもジョージに御世辞を言った。
「ミスター・ハイドンは喜んでいる。来週は何を作ってくれるの?私も楽しみにしている」
彼女は金曜日に夕食を作る必要が無いことを考え、心の中で高笑いしたように思えた。
ジョージ君にとっては、ハイドン氏と子供達が喜んでくれたことが、素直にうれしかった。
次の週は、作ったことのない、てんぷらに挑戦した。
たくさんの海老とさつま芋を買った。
ところが油の温度調整がわからず、日本人にとっては完全な失敗作だった。
てんぷらは素人には難しかった。
それでも、ハイドン氏は喜んで食べた。
3回目は、肉をふんだんに使った野菜炒めに、焼き飯と、みそスープを作った。
これには自信があった。
案の上、家族全員が満足をした。
しかし、4回目はなかった。
ジョージ君は4回目の夕食を作るのを拒否した。
立て替えた、合計$150あまりをベティーから返金をされていなかったのだ。
食住をお世話になっている人に、ジョージ君はお金の請求など、なかなかできなかった。
ジョージ君にとって、$150は大きな負担になっていた。
これ以上の出費はもう無理だった。
ベティーとの約束では、ジョージ君が立て替えてくれれば、ベティーが後で支払うことになっていたのだが、ジョージ君の方からはお金の請求は決して口にしなかった。
4回目の食事を作ることを拒否すると、ベティーはしつこくジョージ君の部屋に来た。
「なぜだ、なぜ作らない?ミスター・ハイドンは非常に楽しみにしているのに」
しかしベティーは、ジョージ君が食事を作りたくない理由を知っていた。
「きみが立て替えたお金を私が支払っていないから、食事を作らないのだね?」
そこまでわかっているなら、早く払えば良いのに…とジョージは思った。
ベティーは言った、「請求しなければ、アメリカでは誰も金など支払わない。請求しないきみが悪いのだ」
彼女はここまで言っても、金額さえ聞こうともしなかった。
日本人には自己主張が求められている。
それはわかった。
でも自己主張の程度がわからなかった。
もうひとつ気になったことがある。
ここでジョージ君が金額を知らせ、その返金を要求すれば、毎週金曜日の夕食はジョージ君が作ることが定着する。
返金してくれないことが食事づくりを断る最大の口実に思えた。
返金を要求することで藪蛇になる。
ジョージ君は返金の話題は意識して避けた。
その弱気な心に忘れてきた山陰人を思い出した。
ジョージ君の故郷、松江の人は、正面からの議論を好まなかった。
黙殺が得意だった。
弱気になると否定して生きてきた山陰人の習性がひょっこりと出てくる。
ベティーとジョージ君の間に、一瞬、気まずい雰囲気が流れた。
本当はきちっと話を付けないといけないと思った。
ジョージ君は、ベティーの家のホームステイにも、食事をつくることにも、すっかり疲れ果てていた。
自由になりたかった。
今考えてみれば、家庭に他人を入れ、家族9名とジョージ君のために食事をつくってくれていたベティーに、もっと感謝と同情をすべきであったかもしれない。
彼らは本当にジョージ君に良くしてくれた。
たとえ人種偏見があったとしても、それはジョージ君の心の持ちようで解決できる。
ジョージ君にこそ、オープンな気持ちが求められているように思えた。

つづく