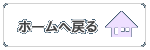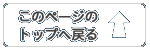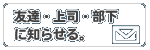第21話 YONEDAレストラン2011年12月22日(木曜日)
ジョージ君は日本食が食べたくて、中華のレストラン・サンパンのバス・ボーイをやめ、日本食のYONEDAレストランでバス・ボーイを始めた。
YONEDAレストランの創業者、米田さんはあの有名な辻料理教室の第一期生。
校長の辻氏に、「日本人の名を高めてこい」と言われ、さらにアメリカ日系人の実業家に招かれ、デンバーにきたのである。
デンバーでは、当時学生をしていたロッキー青木が食事にきていたらしい。
ロッキー青木は後年、「BENIHANA」という鉄板焼レストランチェーンを出した人物である。
ちなみに、デンバーにはロッキー山脈があるので、「ロッキー青木」。
米田さんはいつもロッキー青木を褒めていた。
「世間は、彼が金持ちの息子だから、成功したと言う。でもアメリカにきた金持ちの息子で、成功した人は少ない。ロッキーはすごい男だ」
ジョージ君から見ると、米田さんもすごい人だった。
戦後、中学校を卒後し、家業をつぐため大阪で板前になったが、若くしてアメリカのデンバーに渡った。
やがて、サンフランシスコの老舗レストラン「YAMATO SUKIYAKI」のチーフとなり、その後、自分の店を開店するためにストックトンに移住した。
ジョージ君がストックトンにきた時は、自分のレストランを持って、間もない頃だった。
この街で、初めてできた、日本食レストランだ。
1970年代の後半は、まだまだ日本食レストランは少なかった。
そもそも日本食などという言葉すら存在しなかったといった方が正しい。
坂本九の『上を向いて歩こう』という歌が、海外で『SUKIYAKI』というタイトルで大ヒットした時代である。
当時は、アメリカ人に日本食をアピールするため、YAMATO SUKIYAKI、TOKYO SUKIYAKI、NIKKO SUKIYAKIなどと、レストランの名前に「SUKIYAKI」を付けた。
SUKIYAKIが日本食を意味していたのだ。
やがて、TOKYO TERIYAKI、TOKYO TENPURA、TOKYO SUSHIと時代とともに日本食のイメージは変化した。
2011年の今なら、TOKYO SHABUSHABU、TOKYO RAMEN、TOKYO SOBA、TOKYO CURRYなどとなるだろう。
当時、ストックトンは牛島謹爾さんの開拓の歴史もあり、3000人近い日系の子孫たちがいたとされている。
その彼らにとって、日本食レストランの歓迎ぶりは異常だった。
それはストックトンの日本人と日系人の誇りであり、文化だった。
日本食がいかに優れているかをアメリカ人に紹介し、ご馳走できる場となった。
第二次世界大戦中、日系人が強制収容所に入れられていた。
しかし、戦後30年の歳月がながれ、勤勉で真面目な日系人は非常に豊かになっていた。
YONEDAレストランは、開店初日から大盛況、常に40~50名が外に列を作って待っていた。
あまりにもすごい盛況だったので、店はすぐに2倍に広げられた。
ジョージ君が働き始めた頃には130席ほどの大きなレストランになっていた。
母の日などには、親孝行の日系二世たちが日本生まれの両親を喜ばそうと、開店前から並んだ。
英語中心の二世たちが、日本語しか使わない老いた母や父を、大切にしたのである。
ジョージ君は自分の親不幸を嘆いた。
母の日は、夜だけで3回転以上する繁盛ぶりであった。
米田さんは、松ちゃんという弟子と、2人のシェフと、数人のヘルパーで仕込みをしていた。
ディナーだけで400食以上、作る日もあった。
これにまだランチタイムがあり、仏教会など催しものがあると、弁当を600個、800個、また大量に作った。
米田さんは毎晩徹夜のような暮らしで、店は連日戦場のようであった。
そのうえ米田さんは大工仕事もでき、店の内装・修理も自分でやった。
当然、料理の鉄人、道場六三郎のように、筆でメニューも書いたし、絵まで描いた。
従業員の支払いチェックは自分でつくり、簡単な経理もすべてこなした。
アーティストであり、そこらの大卒より、はるかに頭も良かった。
柔道で鍛えた体も鉄人そのものだった。
昔の日本人はこんなに凄いのかと、ジョージ君は感銘した。
自分を大卒だと思っていたことが恥ずかしく思えた。
米田さんは1年足らずで、日系人たちにとっての英雄、町の著名人、名士になったのだ。
ジョージ君はその後、いろいろな人に出会うが、アメリカで知り合った昭和16~19年頃に生まれ、戦後の食料の無い時代、アメリカ兵に「ギブ・ミー・チョコレート」と言って育った世代の日本人の勤勉さは、自分たちの世代はとてもかなわないと思った。
人間の限界を越えた怪物のように思えた。
特に身近で見る米田さんは、怪物を越えて、神々しくさえあった。
彼の下で働いたことは、ジョージ君にとって、いい経験になった。
日本経済発展の第一の功労者はこの世代だと思えた。
多分、同じ日本人でもジョージ君の世代とは明らかに違っている。
ストックトンに住んで2年目に入っていたため、YONEDAレストランで働きだすと、知り合いの日本人や日系人がたくさんやってきた。
知り合いが、皿をかたづけている時に「おい、ジョージ!」などと声を掛けられると、恥ずかしくて仕方がなかった。
“もう27歳になった皿洗い”と自嘲した。
大学院の苦学生なら多少格好がついただろうが、ジョージ君は短大生である。
4年制の私学であるUOP大学の学生なら、言い訳もできるが、この姿では本当に様にならない。
同じ年頃の若い日系人の女の子がくると、顔から火が出るような気がして、とてもまともに彼女たちの顔を見られなかった。
特に友人のスタンフォード大学に通うジニー山本と、UOP大学のデビーOHARAがきている時は、キッチンから一歩も出られなかった。
日本での大学時代、ジョージ君はさまざまなアルバイトを経験していた。
東京まで出稼ぎに行き、昭和女子医大で高層ビルの窓拭きアルバイトをした時は若い女子医大生に自分の姿を見られてもコンプレックスはなかった。
しかし、YONEDAレストランの時は、明らかに違った心理状態であった。
学生のころのあの爆発的なエネルギーはもうなかった。
米田さんやその弟子の松ちゃんは、ジョージ君によく言った。
「ハーバード大学や、スタンフォード大学にでも行っていれば、話は別だが、アメリカの大学など出ても、たいしたことはない。ジョージ君、早いうちに大学を辞めて俺の弟子になれ。永住権も取れる。ジョージ君ならすぐ店に一軒ぐらい持てる」
実は同じようなオファーを京都の大学時代にも言われたことがあった。
アルバイト先の越後屋のチーフに「俺の下で6年間修業をしろ。大卒の5倍の収入を約束してやる。この業界も頭が必要だ、大卒の弟子が欲しい」と言われた。
あの当時もそのような選択肢が確かにあった。
ストックトンでもまた同じような状況だ。
しかも永住権が取れるという話は魅力的に聞こえた。
しかし、ここでもジョージ君の決断力が足りなかった。
ジョージ君はまだ、自由と夢に浸っていたかったのである。
30歳まで好きなことをしてからでも遅くはない。
それにしても、バス・ボーイは早く卒業しないといけない。
それだけは分かっていた。
当時、日本食はデルタ大学の苦学生はめったに行けない場所だった。
ある時、仲間と久しぶりにYONEDAレストランに行った。
食後、おひつにご飯が残っていたのを見て、20歳ぐらいの留学生、新田君が手に塩をパッ、パッとふった。
何をするのかと思うと、彼は残ったご飯を手に取り、テーブルの下で握りはじめた。
握り飯を作って、持って帰るというのである。
それが米田さんの奥さんの目に入った。
彼女はすぐに別のおひつに、ご飯をたくさん詰めて持ってきてくれた。
「あなたたち、腹が減っているのでしょう。オニギリをたくさん作って、持って帰りなさい」
留学生とレストランの女将さんとの間に、こんな心の交流もあった。
精神的に豊かな時代であったような気がする。