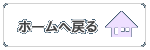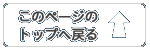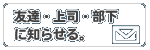第24話 日系の女性との出会い ~盆踊りの夜~2012年1月18日(水曜日)
アメリカにきたら、絶対に日本人女性とは付き合わない。
できれば、日本人学生とも群れない。
ジョージ君は最初、そんなことを考えていた。
ジョージ君の住んでいる田舎町ストックトンには、多くの日系人がいた。
数は少ないが、日本人も住んでいた。
気づくと、ジョージ君は日系社会にどっぷりつかり、日本人留学生との付き合いが多くなっていた。
それでもアメリカ人の家にホームステイをしていたので、アパート住まいの日本人留学生よりは、まだマシだったかもしれない。
ある日、留学生の後藤さんから「盆踊りがあるから、ジョージ君もきたら?」と誘われた。
彼はストックトンにあるお寺で、寺男(寺の小使いさん)をしていた。
そこは東本願寺系の立派なお寺で、日系社会の中心的な存在となっていた。
日系人・ボブ山田さんが、広大な農地からでた天然ガスの利益、当時で20億円近い金を寺に寄付したらしい。
下駄と浴衣は持ってきている。
懐かしい盆踊りをアメリカで踊れる。
一度、アメリカの盆踊りとやらに行ってみよう。
ジョージ君は楽しみにその日を待っていた。
盆踊りの日も暑い夕方だった。
午後5時近くなっても、40℃近くはあった。
ストックトンは盆地にあるため、夏は40℃ほどになる日が一カ月以上続くことがある。
夏は雲がまったくなく、周辺に山もないので、日系人は例外なく、日に焼けていた。
また、アメリカの食事のせいか、かなりの人が太っていて、鳩胸のように胸が厚く、首も太かった。
そのせいかどうかわからないが、日系二世たちは、心臓病が原因で亡くなる人が多かった。
戦前の、カリフォルニアの日系成年男子の平均身長は169センチ。
当時の日本人成年男子の平均身長は162センチ。
7センチの差があったが、ジョージ君が見たところ、日系人と日本人の背丈にはあまり差はなかった。
ただし、この田舎町では、日系人は農業出身者が特に多く、体はがっちりとしていた。
逆に、日本人は色が白く、体は華奢だった。
また、片言の日本語を使う日系人が多かった。
彼らの日本語は、父や母が使う言葉がすべてだった。
そのため、人によって、それは熊本弁であり、名古屋弁であり、広島弁であった。
なにしろ、日本語のテレビなどない時代に育ち、標準語の日本語を聞いたことのない人ばかりだ。
悲惨なのは、母親がおらず、父親に育てられた娘だ。
父親の使う男言葉になんの疑問もっていなかった。
「おい、おみゃ何をしているか?バカ」
「腹がへった、飯出せ」
「糞がしたい」
こんなことを女性から言われ、ジョージ君は面食らったこともあった。
もう一つの違いは“心”である。
日系人は、日本人が忘れてしまった明治・大正・昭和初期の古い価値観や美徳を失うことなく持っていた。
孝行、恥の文化、勤勉、正直、愛国心、義理人情、滅私奉公などの精神である。
「昔の日本人を見たければ、アメリカやブラジルの日系社会を見ろ」と言われる時代であった。
さて、午後6時ごろになると、ぞくぞくと人が集まってきた。
広い境内は600名ちかい人で膨れ上がっていた。
やぐらの上で、熊本出身の花屋の竹内さんが、ものすごい熊本なまりの英語で司会をはじめた。
やがて、三波春夫の演歌が流れた。
歌はすべて日本語だが、周囲から聞こえてくる言葉はすべて英語だった。
人々は浴衣こそ着ているが、肌は日に焼け、腰、胸、首は太く、会話は英語。
これは間違いなくアメリカ西海岸の盆踊り、異国の踊りだと思った。
じつに不思議な光景であった。
ジョージ君も輪の中に入って、踊りはじめた。
すぐに、目の前で踊っている若い女性に興味を抱いた。
この輪の中の誰よりも、踊りがうまかった。
すべてが様になっている。
うしろ姿は日本映画に出てくる女優さんと見違えるほど、美しかった。
大学時代、京都の仁和寺で映画のロケをしていた時に見た女優、山本富士子を思い出した。
演歌が数曲終わり、インターバルになると、彼女は後を振り返った。
ジョージ君と目があった。
美しい。
背は高いが、まだあどけない顔で、柳腰、明らかに日系人とは違う。
ジョージ君は思い切って日本語で声を掛けた。
「君はここにいる誰よりも踊りがうまいね。色も白く、美しい。どこからきたの?君はここにいる他の人たちと明らかに何かが違うようだ。純日本女性のように見える」
彼女は美しい日本語で答えた。
「私はジニー山本です。5歳から日本舞踊を習っています。私の母は東京出身ですから、言葉も他の地方出身の人たちとは違います」
正直、地方出身のジョージ君には、この回答に違和感があった。
でもこの回答は、彼女の答えというより、母親の影響だと容易に想像できた。
彼女には悪気はない。
それは純粋な眼を見ればわかる。
アメリカ生まれの二世でありながら、日本人として育てられているような気がした。
彼女はジョージ君が日本から来たばかりであることに、非常に興味を示した。
次の曲が始まりそうだった。
ジニーはすばやく紙とペンを取りだして、なにかを書き始めた。
電話番号と住所だった。
「絶対に電話して、家に遊びにおいで!私に日本人の男友達ができたら、お母さんは喜ぶと思うの」
このあたりの積極性はやはり、アメリカ女性だった。
話し始めて10分も経っていない。
ジョージ君の胸に、驚きと、喜びと、感動が襲ってきた。
長い間、意識して「ガールフレンドは金髪のブルーアイ」と決めていた。
その心に大きな変化が起こっていた。
なにをこんなに興奮しているのだろう。
白人女では感じることのない、本能の叫びがあった。
やはり日本女性がいい。
彼女と話したい。
そのあとは、一曲終わるたびに会話をした。
ジニーはこの春にストックトンの高校を卒業し、スタンフォード大学に入学が決まったばかりの18歳だった。
ジョージ君は27歳の短大生、コンプレックスを感じた。
しかし、彼女の方から電話番号と住所をくれた。
彼女はジョージ君に興味を持っているはずだ。
翌日、ジョージ君は情報収集をした。
ジニーの父親は日系二世、母親は一世。
そして高校3年生の時に、ミス・サンオーキン・カウンティ(郡)になっていた。
サンオーキン郡は、日本の県と同じくらいの面積で、ストックトンはその中心の町である。
ジニーのお姉さんも、実は以前、ミス・サンオーキンになっていて、白人以外では初めてだったらしい。
お姉さんもスタンフォード大学で生物学を学んでおり、ジニーは姉とまったく同じコースをたどっているようだ。
ストックトンの日系社会では有名な、才色兼備な姉妹であった。
両親も有名で、父親は郵便局長、母親はソーシャル・クライマーというあだ名がつけられているほど、上昇志向の強い女性だった。
誰でも、可愛い娘を二人も持てば、“シンデレラの母”となる夢を見ても不思議でない。
ジョージ君は3日待って、彼女に電話をした。
母親が出た。
「あなたは誰?年は?趣味は?なにを勉強しているの?目的はなに?どうして大学院に行かないの?」
20~30分話したが、娘に電話を取りつごうとはしなかった。
邪魔をしようとしているのは明らかだった。
母親は冷たく言い放った。
「また、遊びにおいでください」
最高に感じが悪かった。
忘れていた日本社会を思い出した。
ジニーには、鬼婆背後霊がいる。
もう二度と電話はかけまいと思った。
それでもジョージ君は、白人女性では得られない、魂の叫びを感じた。
日本人の子孫を残したい。
それは不思議な感覚であった。
やはり、日本の血が流れている女性を求めているのだと、この時はっきりと悟った。
後日談だが、ジョージ君はカリフォルニア州立大学サンノゼ校に行くことになり、近くにあるスタフォード大学の図書館を利用することがあった。
その際、ジニーを何度か見かけた。
やはり、あの時見たとおりに明るくて、素直で、美しい女性であった。
一度、ジニーがジョージ君に気が付き、追いかけてきた。
「あなたもスタンフォード大学にきているの?どうしてあの時、電話をくれなかったの?」
やはり、母親は何も伝えていなかったようだ。
本当のことを言ってやりたいという衝動に駆られたが、どうせ彼女は高値の花だ。
男らしく引き下がった方が身のためだと思った。
それが武士道とも思えた。
たとえジニーがジョージ君を気に入ってくれていたとしても、あの母親は苦手だ。
本音を言えば、自信がないだけだった。

つづく