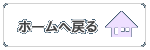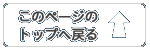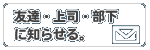第26話 日系女性 ~教会であった大原麗子~2012年2月8日(水曜日)
ジョージ君は、自分が本当に求めている異性は日本女性なのだと自覚した頃、思いがけないお誘いがあった。
大学で知り合った1世半のトヨコさんが、
「ジョージ君好みの女性がいるから、私のキリスト教会にこない?」
と誘ってくれたのである。
普通の日系2世や3世は、ほとんど日本人留学生とは話さない。
彼らには、“日本から来た日本人は同胞”という意識は、ほとんどなかった。
英語がしゃべれない、東洋の貧しい国から来た変わったやつ、と思い、留学生を避ける日系人も多かった。
彼らは白人と付き合い、われわれとは交流しなかった。
日系人は、見た目には黄色いが、中身は白いので、「バナナ」と言う人もいた。
それでも日本からお嫁さんをもらった日系人は、ワイフを通じて、多少は日本人との交流があった。
トヨコさんのような、日本人留学生と付き合う日系人は、必ずといっていいほど、母親は日本から来ていた。
24話で登場した、ジニー山本もそうだった。
ジョージ君は彼ら日系人が、どのようにわれわれ日本人を見ているか、ということなどほとんど関心なかったし、深く考える時間もなかった。
気持ちの上では、「本国から来た純・日本人は、日系人に尊敬されるべきだ」ぐらいの高いプライドと自意識を持っていた。
ところが、現実はそうではない場面に多く遭遇した。
後に気づいたが、戦争が終わって30年近い歳月が流れているのに、日系人の知っている日本は、敗戦後の廃墟だった頃の日本であった。
戦後、進駐軍でやってきた日系兵士は米兵の通訳や語学兵として日本にきていた。
その日系兵士が初めて見た憧れの日本は、食料は十分になく、廃墟と浮浪者が溢れている国だったのだ。
食べ物やチョコレート1枚で米兵と寝る日本女性もたくさんいた。
日本人としての自信もプライドも失い、父や母から聞いていた誇り高い日本はどこにもなかった。
そのイメージが30年以上経っても、いまだにあった。
それ以降、彼らは日本に来る機会がなかったのだから、イメージが変わらなかったのも無理はない。
テレビやラジオから聞こえてくる戦後の日本の高度成長よりも、実体験にもとづいた進駐軍時代の日本の方がイメージが強かったのだ。
ジョージ君が初めて日本に一時帰国した時、土産は何にしようかと、中年日系男性に話したら、「砂糖とノートと鉛筆を持って行ったらいい」と言われたことがあった。
日本には砂糖とノートがないと言うのだ。
これにはジョージ君も驚いたし、ショックでもあった。
ジョージ君の知らない敗戦後の日本がそこにあった。
余談だが、ジョージ君がその後、働き始めてから知り会った、10才年上の先輩、E氏から聞いた話を紹介したい。
E氏は愛媛の高校を卒業後、親せきを頼ってアメリカにきた。
終戦から10年くらいたった頃だ。
アメリカでアルバイトと学生を続けていた時、沖縄出身の日系2世女性と知り合い、結婚することになった。
もう嬉しくて、天にも昇る気持ちになったそうだ。
ジョージ君は思わず、「どうして?そんなに彼女は美人だったのと?」と聞き返した。
「そうではないよ。我々が来たころは、白人女はもちろん、日系人女性との精神的、経済的格差はひどくて、日本からの留学生が、アメリカ国籍を持つ日系人女性と結婚できる時代ではなかったんだよ」
正直、ジョージ君には、この話は違和感があった。
ジョージ君とE氏の時代、その間15年で、日本人もアメリカ人に対するコンプレックスが相当解消されたような気がする。
E氏が来た時代は、日系農業労働者でも、日本の労働者の30倍は稼いでいた。
東京と島根の格差の何十倍である。
そして語学のハンディもあった。
話を戻そう。
日系のトヨコさんに連れられて、ジョージ君は教会に行った。
トヨコさんは、デビーOharaをジョージ君に紹介した。
彼女は若手メンバーのリーダーの一人だった。
お年寄りや子供たちの世話をいろいろとしていた。
UOP大学の4年生らしい。
あのスタンフォード大学に次いで授業料の高い私学だ。
父親はストックトンで1、2位を争う缶詰工場を経営する、大農業経営者。
世界一の農業地、カリフォルニアの中心にあるストックトンの資産家は農業経営者が多かった。
初めて聞くキリスト教会の牧師の話は驚きと感銘があった。
高校で習った親鸞聖人の教えを唯円が書いた歎異抄の言葉、善人でさえ浄土へ往生できる、まして悪人はなおさら救われる、など、まさにその内容だった。
キリスト教でも、罪を犯した人こそ、深く懺悔することで救われる、罪を犯していない人は、そこまで認識がないので、なかなか救われない、という話だった。
ジョージ君は目立ちたがった。
仏教、歎異抄の話をつたない英語で説明した。
「キリスト教と仏教は非常に似ている、どうしてか?」
牧師に説明を求めた。
しかし、英語人間の日系牧師は答えられなかった。
ジョージ君は、この質問で注目された。
最後はデビーのオルガンで歌を歌った。
トヨコさんはウインクしながら、ジョージ君に言った。
「デビーがジョージ君を家まで送ってくれるって」
デビーは日本の女優、大原麗子にそっくりだった。
言葉のイントネーションもやさしく、上品だった。
いかにも育ちが良さそうだった。
彼女は赤いスポーツカー、ダットサン280Zフェアレディーに乗っていた。
車の中でジョージ君は一人で喋っていた。
彼女の美しさと、やさしさに興奮していた。
ジニー山本は、ぶりっこお嬢様だったが、こちらは本物のお嬢様だった。
ジョージ君に偏見をまったく持っていないように感じた。
彼女はジョージ君の身分や立場にまったく関心を示さなかった。
「お金、仕事、年齢、国籍、言葉などには関心はないの。私を本当に好きかどうかが、すべてなのよ」
ジョージは自信が湧いてきた。
彼女なら愛せる。
それこそ、天にも昇る気持ちになった。
2度目の教会ミーティングの後、ジョージ君はデビーを映画に誘った。
OKだった。
映画館でも、ずっと手を握っていた。
抵抗はされなかった。
別れ際にキスをした。
彼女は受け入れた。
ジョージ君は、この状況が信じられなかった。
白人では得られなかった不思議な感情が沸き起こってきた。
彼女とならどこまでもいっても後悔はない。
ところが、日曜日にアートン家の庭仕事をしないといけなくなり、日曜日の礼拝を1ヵ月ほど休んでしまった。
そして高卒で日本から来たばかりの留学生、七尾美と知り合った。
彼女はジョージ君にすべてを頼ってきた。
彼女は親戚のホームステイ先から3週間で追い出された、ジャジャ馬娘だった。
七尾美はジョージ君とアパートで同棲しようと言いだした。
教会に行かなくなって1カ月、その間、ジョージ君の2度にわたるデートの誘いをデビーは断った。
用事があると言うのである。
ジョージ君は自らが描くコンプレックスで、勝手に振られたと思い、七尾美との同棲話を進めた。
彼女は積極的であった。
親元を離れ、アメリカでは自由になんでもできると思っていた。
鉄砲玉のようにジョージ君の胸に飛び込んできた。
スタイルも良く、かなりの美人。
曲を聞くと、聞いた曲をすぐにピヤノで弾けるような才能を持っていた。
ジョージ君は悪い気はしなかった。
本当はデビーに惹かれながら、七尾美との同棲話を進めたのは、すべてジョージ君のコンプレックスからきていた。
27歳の英語のわからない皿洗いで、人生の方向性も定まってなく、金もない。そんな男をデビーが本気で相手にするはずがないと思っていた。
しかもデートは2度も断られている。
ジョージ君はホームステイを出て、七尾美との同棲に踏み切った。
2カ月後、街でデビーとすれ違った。
「ジョージ、どうして電話をくれないの?私ずっとジョージの電話を待っていたのよ」
「だって君は、俺のデートの誘いを2度も断ったではないか?」
「それは本当に用事があったの、あなたがいやで断ったのではないのよ。また電話して」
困った。
そんなバカな、本命からの告白に困惑した。
俺は将来のことを何も考えないで若い女と同棲をしている。
いまさら引き返すのか?
とっさ的に言い訳をいった。
「いや、俺は適齢期だから、結婚を考えられないような女性と時間を割くほど暇はないのだよ。」
「それは私も同じよ」
え、そこまで言ってくれるの?
どうしよう?
「俺は英語もわからないし、27歳で皿洗いをしているし、まだ人生になんの展望もない。車はボロい中古車。恥ずかしい男だ、君のようなお嬢様を経済的に満足させる自信はない」
「ジョージ、なにを言っているの。ここはアメリカよ。あなたのようにエネルギーに満ち溢れていて、やる気があれば、アメリカでは生活ぐらいできるわよ。皿洗いだって、永遠にやるわけでないでしょう?
私の周りには、日系3世の男の子がたくさんいるよ。彼らは紳士で、高学歴で、プロフェショナルな仕事も持っている。
でもね、ジョージ、あなたが持っているエネルギーは3世ボーイにはないの。あなたのやさしさ、芯の強さ…うまく説明できないけど、その頑固さは日本から来た、私のおじいさまによく似ているの。おじいさまは私をすごくかわいがってくれたわ。ジョージといると、おじいさまといるような、長い間忘れていた懐かしい感情が沸いてきて、故郷に帰ったような気がするの。
それともう一つある。
あなたのmaverick mentality(マブリック・メンタリティー、1匹オオカミや異端児という意味)にも興味があるわ。あなたとなら、いろいろ冒険のある人生を体験できそう。何の心配もしていないわ」
何としたことだ。
彼女はジョージ君のことをちゃんとした一人前の異性と見ていたのだった。
そんなもったいない、夢のような話を、とてもにわかには信じられない。
エキサイトしたジョージ君は走り寄って、デビーを軽く抱き寄せた。
涙が頬をポロボロと溢れでてきた。
それは後悔の涙であり、デビーをどうすることもできない。
複雑な感情の涙だった。
心の中でつぶやいた。
「デビー、ごめん、俺は他の女と容易に同棲をしてしまった。君を愛する資格はないよ。俺は情に流されるタイプ、きちっと人生設計ができない男だ。しかも、いまさら飛び込んできた女を捨てることはできない。かと言って、二股を掛けることもできない。君にはもう電話できないよ」
ジョージ君は黙ってその場を去らざるを得なかった。
高倉健の『網走番外地』が、頭に流れてきた。
「バカーを、バカを承知で…..アメリカでいー(生)きる。」
それはいつもこのような時に頭の中に流れてくるメロディーだった。

つづく