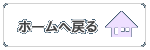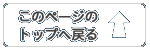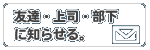第29話 天国だったストックトン2012年3月1日(木曜日)
夢のように楽しかったストックトンでの生活に終わりを告げる日がきた。
いよいよ、デルタ大学卒業だ。
ジョージ君の20数年間の人生の中で、一番燃焼した時間だった。
言葉もわからない、金もない、将来もない。
生きるため、目先の問題解決だけのために生きたのは初めてだった。
それが最高に楽しかったのだ。
何をしたわけでもないが、「命を生きる」。
そんな言葉がぴったりのように思えた。
勉強(言い過ぎか?)、仕事、恋愛、人生経験。
ジョージ君の人生に、これほどの愛らしい一瞬、一瞬は今までなかった。
親の反対、世間体、失敗や恐れ、不安はあるかもしれないが、短い人生で、絶対に一度は好きなことをするべきだと思えた。
ジョージ君も、もっと早い時期に勇気を持って挑戦し、壁にブチ当たるべきだった、と後悔した。
しかし、レベルの低いジョージ君にとって、「25歳過ぎ」というタイミングは最適なタイミングだったのだろう。
なぜこんなに、すべてに完全燃焼できたのか。不思議だった。
親元を離れ、故郷を離れ、祖国を離れる。
裸一貫の人生が一番だ。
若者はいつの時代も、好きなことをして、与えられた命を燃焼させるのが一番なんだ、と叫びたかった。
キャンパスでの昼食時、アメリカ人の学生が大勢いる前で、100キロ近いレスリング部の大男を腕相撲で負かした。
ストックトン仏教会の第一回カラオケ大会で3位になった。
何にでも挑戦した。
誰の反対も耳に入らなかった。
なにより、車を買ってから新しい世界が開けた気がする。
アメリカでは、車さえあればどこへでも行けた。
地平線を見ながら走ることが最高の快感だった。
地平線の向こうに見える満月を見ると、親や友達のことを思い出し、感傷的になったりもしたが、あとは笑って暮らした。
3年間過ごした、東京での生活とは天と地ほど違った。
日本でも「自由に生きたい」と思っていたが、目に見えない価値観や伝統、親の期待などに、知らないところで縛られていた。
日本の環境からくる社会的拘束も多くあった。
満員電車と会社の寮という住環境が特に合わなかったし、仕事で扱う「保険」という商品も大嫌いだった。
保証という後ろ向きな商品ではなく、夢を売りたかった。
東京では、汗水流して働き、マンションの一つでも買えれば成功だった。
しかし地方出身者のジョージ君は、庭付きの家があたりまえの環境で育っていた。
ストックトンはそれが実現できる町であった。
アメリカ滞在地が、ニューヨークやサンフランシスコだったら、そうはいかなかったかもしれない。
ジョージ君はしょせん田舎者で、ストックトンが、いや、広いアメリカが性に合っていた。
それにしても多くの人に本当にお世話になった。
アメリカ人は人懐こく、非常にフレンドリーであった。
偏見や差別意識を持つ人もたまにはいたが、総じて、善良で快活な人が多かった。
何といっても、彼らの前向きな思考には感動した。
国が広いので、後ろを振り向いている暇はない。
前はいくらでも広がっていた。
国の歴史が短いから、アメリカ人の人生に対する思慮は浅いのだ、と思う人が多かったが、とんでもないと思った。
「自由を尊重する」ことは、日本では時に、「行き過ぎた自由」という否定的なニュアンスで捉えられることがある。
しかしそれは、過去や呪縛、宗教からの「free from(~から自由になる)」、仏教用語で言えば「解脱」だ。
アメリカの移民者は、それぞれが出身国の伝統や芸術、歴史、哲学をもってきた人たちであり、突然大地から生まれた、無知の民ではない。
ジョージ君は東洋哲学クラスを取ったことがあった。
教授のギラオ博士は熊本大学に留学したことがあり、日本の歴史や哲学宗教に詳しかった。
初めて聞くインド宗教の哲学は、ジョージ君にとって非常に新鮮だった。
同じクラスのアラブ系留学生が「アメリカ人は宗教心が薄いので、尊敬できない」と発言すると、必ずギラオ博士はジョージ君を当て、「日本が明治以降の近代化において、宗教や道徳心を失わず、いかに西洋に対抗してきたか?」という話をさせた。
当時、アジアで唯一、先進国だった日本。
その国の留学生の言葉に、アラブ系留学生は真剣に耳を傾けた。
西洋の植民地化の犠牲となった彼らは、アメリカ人の言うことには激しい抵抗を示した。
まぁ、その彼らも白人女に全面降伏したことは言うまでもないが。
世界のアート史を教えていた、ハンガリー人の博士からは、いかにハンガリーと日本の関係が深いかを、個人的に呼びだされ、何度も聞かされた。
今でも憶えているが、ハンガリーでも「水」を「MIZU」と発音するらしい。
ハンガリー語と日本語の意味と発音が同じ単語は、少なくとも30語ぐらいあると言った。
この2つのクラスでは、成績はAをもらった。
成績は先生の好き嫌いで決まる。
これも人生勉強になった。
「ペルーでは、日系人は尊敬できた。だから日本人男性には興味がある」というペルー人女性がジョージ君に近づいてきた。
「日本人と結婚すれば、食いっぱぐれがない」というメキシコ人女性もいた。
レストランで一緒に働いていたメキシコ人のおばさんは、盛んに家に招待してくれた。
「娘のメキシコ人のボーイフレンドは怠けもので、酒ばかり喰らって、娘を不幸にする。娘に日本人男性を紹介したい」と言うのである。
香港からきたアシュリは卒業が決まり、帰国しないといけなかったが、「中国に返還される香港には帰りたくない。アメリカ人か日本人と結婚したい」と言っていた。
「ジョージ君しかアシュリを救えないよ」と別の女友達にまで言われた。
何が言いたいかって???
要するに、日本人だということだけで、得することが非常に多かったのである。
日本では女性にモテたことのないジョージ君にとって、ストックトンでの2年間は黄金の日々だった。
なぜモテたのかはわからない。
今考えてみれば、やる気のオーラが出ていたに違いない。
もうひとつ考えられる理由があった。
保険会社に勤めていた頃、上司である志田部長の義兄弟の六本木事務所を訪れた時の話である。
その事務所の社長、山本睦男氏が言った。
「ジョージ君、君は日本では1億2000万人の一人、何の特徴もない。海外に出なさい。もしどこかの国に行き、そこに日本人が一人もいなければ、君はオンリー・ワンの存在になれるんだ。私は若いころ、香港に渡った。あまり日本人がいない時代だったが、日本人であるということだけで信用を得られ、珍しがられ、その個性で真珠商人として成功した。今また、東南アジア全域で日本人観光客の受け入れをする会社を作り、成長拡大している。日本人は日本で努力したとしても、他の日本人以上の実力をつけて秀でることはかなり難しい。だとしたら、今すぐ日本人のいない海外に出て、挑戦するのと、どちらに可能性があるか?考えて見たまえ」
彼がジョージ君の海外渡航をそそのかした。
確かにアンジェラも、シドニーも、他の日本人を知らなかったからつき合ってくれただけだ。
異文化の中では自己主張をしないと生きていけない。
ジョージ君は外国人のなかでも、遠慮しないで本音で生きれたのだ。
異性にモテる、モテないは、肉体的美しさや金の魅力ではない。
「やる気だ」。
お金がなくても楽しかった。
ストックトンや隣の町、サクラメントは開拓史に出てくる西部劇の町で、ここを舞台にした映画『ビッグ・バレー』や、子供の時に非常に好きな番組『ボナンザ ~カートライト兄弟~』に出てくる牧場まで、わずか3時間半の距離だった。
ジョージ君は、映画の舞台の近くに住んでいるということに興奮した。
ここに住む日本人や一部の日系人も非常に親切と言うか、ジョージ君の田舎にいるような、素朴な人々が多かった。
それとも都会出身であっても生活に余裕があったのか?
留学生たちは電話も掛けず、突然彼らの家に訪ねることがよくあった。
それは決まって昼食、夕食の時間。
「何か食わしてください」、その一言で誰もが歓迎してくれた。
ジョージ君はデルタ大学の先輩で、UOP大学で柔道を教えていた、渡辺さんの家に頻繁に行った。
渡辺さんと奥さんは、日本の大学を卒業と同時に夫婦でアメリカに留学をしてきた人たちだった。
渡辺さんはデルタ大学を卒業後、ダイヤモンド・ウォールナッツというクルミ生産者組合に就職し、経理を担当していた。
就職して5年後には立派な庭付きの家を買い、ジョージ君たちが遊びに行くようになった時には、すでに子供が2人いた。
渡辺さんはジョージ君にとって、人生の相談相手であり、気が休まる場所であった。
食後、奥さんが弾くピアノが好きだった。
特に『エリーゼのために』というピアノ曲を聞くと、ロマンチックな気持ちになった。
理想の夫妻に見えた。
ある日、渡辺さんが「実はここストックトンには、戦前から有名なストックトン柔道クラブがある。二世の吉村先生という8段の凄い先生がいて、弟子にはメキシコ系のマーティンというオリンピック選手がいる。モントリールオリンピックの78キロ級で4位だった選手だ。とにかく、生徒は年寄りと子供ばかりで、打ち込みの練習相手がいなくて困っているらしい。私も以前はそこで教えていたが、今は時間がないので行っていない。君が暇なら、友達を作るためにも、顔を出してみなさい」
ジョージ君の柔道は小学生レベルだが、中学1年の時の松江市の大会では2位になったこともあった。
そこで、好奇心で出かけてみた。
吉村先生は当時60歳ぐらいで、背丈は中肉中背で、175センチぐらい。
怒り肩で、体は大きく見えた。
ジョージ君の柔道は小学生レベルだったが、「大学拳法部で、高校で番長、柔道部キャプテン、3段です」という新入部員を簡単にノックアウトした。
打撃系には破壊力があった。
柔道の打ち込み程度なら、簡単にできると思った。
マーティンは、まだ当時22歳ぐらいで、高校では野球部の4番でピッチャー、フットボールは攻撃のクウォーター・バック、100メートルは11秒フラット、プロ野球やプロのフットボール・チームからスカウトがくるような、超一流のアスリートだった。
マーティンはそれをすべて断って、好きな柔道を選択した。
ところが柔道では食っていけない。
当時、オリンピック強化選手ということで、一応所属している会社から給与をもらってはいたが、オリンピック以後は会社も首になり、生活に困る日もあった。
その後、吉村さんのはからいで、レーガン大統領のボディーガードになった。
マーティンは178センチ、78キロ。
特別に大型の選手ではない。
しかし、柔道着の下からは金剛力士のような隆々とした胸が見えた。
打ち込みの練習を申し込まれた。
彼はジョージ君の柔道着を握った。
いやな予感がする。
鉄のワイヤーで握られた感じだ。
恐怖が走った。
マーティンはジョージ君に技を掛けた。
もちろん本気で投げたわけではないが、突風が起こった。
ものすごいスピートで、背負い投げを繰り返し掛けてきた。
十分な時間をかけて合計50回~100回するというやり方ではなく、5分間で何回できるか?というような、スピードとパワーの訓練であった。
あまりの激しさに耐えきれない。
ジョージ君が今まで経験したことのない、腕力、スピート、破壊力だった。
「ジョージさん、一度投げてみましょうか?」
思わず、「どうぞ」と答えた瞬間、畳の上に激しく打ちつけられた。
受け身をとる暇などなく、投げられた。
記憶はまったくない。
一瞬、気を失っていたらしい。
オリンピック選手ぐらいになると、本物の格闘家だけがもつ野生の世界だ。
恐ろしい強さだ。
練習が終わった。
「ジョージさん、今日はすみませんでした。日本から来ているので、あなたはもう少しエキスパートと思っていました。お詫びに飲みに行きましょう。メキシコのセニョリータがたくさんいるバーを案内します。今日は私のおごりです。酒も極上のセニョリータも好きに選んでください」
「どうも腰の骨にヒビが入ったかもしれない。腰が使えないので失礼する…」と言いかけたが、可愛いセニョリータがいるなら、這ってでも行こうと思うジョージ君だった。
彼のような強い男を知ったことで、ジョージ君には、もう二度と武勇伝は起こりそうになかった。
しかもアメリカは容易に銃を使う社会だ、肉体的な強さなどは役に立たない。
逆にリスクを招く。
日本の大学では、空手部や応援団が我儘顔でキャンパスを闊歩していたが、アメリカの大学では、フットボール選手が、そこのけ、そこのけ、と闊歩する姿はない。
蹴っ飛ばされたら、銃で反撃する人がいる社会だ。
実際、そのような事件は多く起こっていた。
コンフー(中国拳法)の中国人先生が銃で殺された新聞記事も目にしていた。これは拳法でやられた仕返しだった。
アメリカにきて、いかに日本は安全だったのかと思い知った。
やはり、アメリカはいろんな意味で、天国に一番近い国だったのかもしれない。

つづく