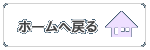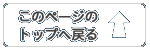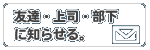第38話 犬猫か、奴隷か、それとも中性か?2012年5月9日(水曜日)
キャサリンは人づかいが荒かった。
彼女は常に仕事に追われていたので、めったに顔を合せることがなかったからまだ我慢できたが、いくら忍耐強いジョージ君でも、常に一諸にいたら、一カ月で飛び出していたに違いない。
とにかく、キャサリンが家にいる時は大変だった。
窓枠を触ってホコリのチェックをする。
どんな小さな汚れでもキャサリンは見逃さなかった。
週末は、じゅうたんの汚れを落とすため、ジョージ君はいつもブラシと洗剤を持ち歩いていた。
ジョージ君の仕事範囲ではなかった。
しかし放っておくわけにはいかない。
結局手伝うはめになるからだ。
銀食器も常に光っていないと、機嫌が悪かった。
週末は二人でそれを磨くのである。
銀食器専用の薬品があるということも知った。
今までジョージ君は家庭の雑用については何も知らなかった。
キャサリンは「ジョージがいいハズバンドになるために教育をしてやるわ」と張り切っていた。
プールの管理人が掃除をした直後でも、プールの中に木の葉が一枚でもあれば、必ずジョージ君に取らせた。
週末の庭の散歩には必ずジョージ君を同行させた。
週末は何も仕事をしないという契約であったが、それを承知でジョージ君はお手伝いをした。
確かにバカなことかもしれない。
しかし、ジョージ君がこの2年間のアメリカ生活、特にベティー家のホームステイ生活で、「言われたことだけをしていては、それ以上の関係にはならない」ということを学んでいた。
ハンディキャップのある外国人が人並みのことをしているようでは、アメリカ人に負けてしまう。
だから、ジョージ君は常に決められた以上のことをしてやろうと意気込んでいた。
しかし、それも2カ月で精根尽きた。
やがて、ジョージ君は週末のお手伝いから逃げる、絶妙な知恵を身に付けた。
土曜日は朝からホームワークを持って、スタンフォード大学の図書館に行くことにした。
スタンフォード大学は家から15分だった。
キャサリンは、「勉強をするなら、それは結構なことだ」と、喜んでジョージ君を送り出した。
図書館は朝の8時ごろから開いていた。
スタンフォード大学の学生以外の人にも解放されていた。
都心の大学ではないので、卒業生でもない限り、一般の人はめったに来ないところであった。
ある日の日曜日、ジョージ君は学校の近くで夕食を食べてから家に帰った。
家に帰ることがそこまでストレスを感じることだったのかと、あらためて思った。
その後、ジョージ君は週末は終日、スタンフォード大学で時間を過ごした。
昼寝は図書館、食事はカフェテリア、いろいろな催し物もあった。
一番楽しかったのは、日本の巨匠、黒沢明、溝口健二、小津安二郎などの古典映画をひんぱんに上映していたことだ。
ジョージ君は当然、『七人の侍』などの黒沢作品を一番楽しんだ。
溝口健二の『雨月物語』を初めて鑑賞した。
中国の清時代の小説からヒントを得てできた『雨月物語』は、若者が野心をもって故郷から都に出たものの、夢かなわず挫折し、故郷に帰るに帰れず、故郷を夢見る、というストーリーであった。
昔からどこの国でも人間社会は変わらないらしい。
ジョージ君はいつの日か日本に帰ることはできるのか?
『雨月物語』は自分の境遇と重なり合うところがあり、感銘した。
ここの大学生や、周辺の住民に日本映画のファンが、たくさんいることに驚き、非常に嬉しかった。
日本人客はジョージ君以外にも数名はいたが、ジョージ君はスタンフォード大学のエリートに話しかけることはなかった。
スタンフォード大学に終日いても、退屈することはなかった。
なにしろキャンパスは2800ヘクタール、日本で一番広い北海道大学の100倍もある。
それも田舎ではない。
キャンパス内を歩いていると、広大な公園の中にいるようで、豊かな気持ちになれた。
スタンフォード大学は世界中の大富豪の子弟や政治家、高級官僚の子供たちが通う、超エリートの学校だ。
その図書館で勉強できるだけでも、劣等生のジョージ君はその時間だけは
エリートになった錯覚でいれた。
週末にジョージ君がいなくなってしまったので、キャサリンは不機嫌だった。
かと言って、キャサリンは会社の社長、契約以上の労働を押し付けるのは遠慮していた。
ましてジョージ君が勉強のために彼女の母校であるスタンフォード大学の図書館に行っているのである。
渋々協力せざるをえない。
そのかわり、平日は会社から帰ってくるなり、次から次と用を言いつけるようになった。
ジョージ君が2階にいようが、深夜であろうが、朝が早かろうが、まったく遠慮をしなかった。
ある晩、真夜中12時過ぎにキャサリンが声をあげた。
「ギャー、ジョージ、ジョージ」と叫んでいる。
窓の外から強盗でもきたのかと思ったが、犬はほえていない。
静かな夜だった。
キャサリンはシャワーから出てきたばかりであった。
そこにクモがいると言うのである。
ジョージ君は探したが、なかなか見つからない。
「そこにいるじゃないか、早く殺せ」と言う。
よく見れば確かに小さな、小さなクモだった。
気がつくと、彼女なんと全裸だった。
まったく恥ずかしげもなく、前をタオルで隠すそぶりも見せず、堂々したものであった。
恥じるべき状況なのに平然としている女主人に、ジョージ君は正直、少し頭にきた。
ジョージ君は視線をそらさず、好奇心も見せず、動物の裸をみた程度のそぶりで部屋に戻った。
日本だったらここまで、あっけらかんとしていられないだろう。
異人種というものは、こういうものなのだろうか?
大学の男友達、韓国人のリー(李)の話を思い出した。
リーは、西ドイツの女子大学生から、お互い1人旅をやめて、相部屋でホテル代金を節約しようと誘われた。
リーは何かを期待したが、何も無かった。
彼女は平然と彼の前でパンツを抜ぎ、裸で寝た。
それが一カ月も続き、リーには拷問のような日々であった。
最後は「バーイ、さよなら」で終わった。
そのビジネス・ライクな態度に心から驚き、同時に、自分の男としての存在価値に絶望したと言っていた。
彼は背も高く、男らしい容姿を持っていた。
しかし、その彼を白人女は中性として扱ったのだ。
「ジョージ、俺たちアジアの男は、白人女から見ると中性らしい」
ある日、キャサリンが疲れ果てて帰ってきた。
ジョージ君が作った食事も十分に食べず、「ジョージ、お前は指圧はできるか?」と聞いてきた。
「指圧はできないが、理屈は知っている。ただのマッサージではなく、ツボを強く指で押さえる、それは日本人の特技でもある」
そうは言ったものの、母親の肩や先輩の腰で指圧のまねごとをした程度だった。
「とにかく、指圧をやってくれ。30分後に部屋までこい」と言われた。
キャサリンはシャワーを浴びて、中国製の赤い薄い絹のガウンを着て、ベッドに横たわっていた。
ガウンを脱がせろと言われたが、さすがのジョージ君も躊躇した。
おそるおそる、ガウンを下におろした。
キャサリンはジョージ君に言った。
「日本の侍は女のガウンも脱がせられないのか?めんどくさい奴だ、見ていろ」
キャサリンは一気に全裸になり、「さあ」と命令した。
「最初はゆっくりと、その掌で全身をさすってから指圧しろ」と指図をした。
うつ伏せから、仰向け、左右に体を横たえたかと思うと、今度は太ももまで揉めと言う。
ジョージ君はできるだけ、息を荒げないように気を付けた。
いや、息もしないそぶりで、全身をたっぷりと時間を掛けて、マッサージした。
ジョージ君の額から汗が噴きだしてきた。
やがて彼女はゆっくりと膝を立てた。
ついにパンツの中身が見えた瞬間だった。
これにはさすがに、ジョージ君もドキドキしたが、キャサリンは眉ひとつ、動かさなかった。
不思議な光景だった。
42歳の独身女が29歳の男の前で全裸になり、膝まで立てている。
見るなと言われても、自然と目に入ってくる。
心臓が激しく鼓動し始めた。
彼女もジョージ君も無言だった。
なんと彼女の秘部から蜜がシーツまで垂れていた。
ジョージ君はここで何か行動しなければいけないと感じていた。
しかし、誇り高い女主人がアジアの下男のような男に、マッサージ以上のことを求めているとは思えなかった。
手を出せば、必ず「勘違いをするな」と、ほっぺにビンタが飛んでくるのは間違いなかった。
しばらく、お互い無言の長い、長い時間が過ぎた。
もうこれ以上、緊張に耐えられなかった。
ジョージ君はやっとの思いで「部屋に帰る」と小さな声で言った。
彼女は相変わらず無言だった。
結局、何も起こらなかった。
何もできなかった。
これはリーが言っていたように、キャサリンにとってジョージ君は中性か、犬か、猫のような存在だと考えた方が、気が楽だった。
男性としてまったく意識されていない。
いや、そうではないかもしれない。
いや、そうに違いない。
繰り返し、繰り返し、あの時の情景を思い起こしては、何をすべきだったか?これで良かったのか?と、反芻してみたが、結論は出なかった。
この時、日本男性のアメリカでの不名誉な地位を感じざるを得なかった。
アメリカの奴隷史の中で、白人のプランテーションのオーナー達は、黒人の前で、平気で裸になり、セックスもしたと何かの本で読んだことがあった。
彼らは奴隷を家畜と同じように扱い、人間として見ていなかった。
だから羞恥心を感じる必要がなかったのだ。
黒人はアメリカが繁栄の頂点を迎えた1960年ぐらいから、セックス・シンボルとして、白人女性に持て囃される時代を迎えた。
しかし、不名誉なアジア人男性の立場は、いつ解消されるのか。
それを考えると、ジョージ君は夜も眠れなかった。
これは経済力でも知能でも解決できない、人間の根本的な問題だと思えた。
100年かけて修正しないといけない、大事業に違いない。
日本男子の課題はたくさんある。
まずは体格、それに自己主張をする力。
これは経済的なキャッチ・アップより難しそうだ。
ジョージ君は個人的な体験をいつも日本全体の問題とすり替え、一般化して考えたがる癖があった。
個人主義のアメリカ人から見ると、ジョージ君の個人的な体験にもかかわらず、ジョージ君が「日本人は・・・」と総合的に表現するのことが理解できないようだった。
要するに、ジョージ君の男としての魅力がない、勇気がないだけという個人的な話だと考えるべきだった。
日本人全体の話ではないのだ。
その夜は、あの時のキャサリンの姿が夢に何度か出てきて、ジョージ君を苦しませた。
シェークスピアの『マクべス』では、「人は生きるべきか、死ぬべきか?」と悩んだ。
ジョージ君は、「やるべきだったか?無言で立ち去って良かったのか?」と一晩中、悩んだ。
次の日の朝、ジョージ君は普通に起きて紅茶を飲んだ。
キャサリンはコーヒーを所望した。
彼女は元気な声で昨夜のマッサージのお礼を述べた。
笑顔だった。
ジョージ君は安心した。
やはり、あれで良かったのだ。
ジョージ君の判断に、狂いはなかった。
犬猫ならその方がずっと楽だ、悩まなくてすむ。
だんだん奴隷根性が身についてきた。
しかし、この発想はジョージ君の危機である。
いや、これが日本人の危機の始まりである。
防衛をアメリカに依存するような奴隷根性では、アメリカの白人女は抱けない。
そんな思いがした。
早く日本を自立させ、対等に白人女を抱く、この大げさな認識がジョージ君の特技だった。
日本の話ではなく、自立するのはジョージ君ではないか?
そろそろ生活を依存したホームステイは潮どきだ。
キャサリンの家を出よう。