〈第2話〉 大阪黒門市場と祖母
第1章 ―――― My Sweet Hometown(愛しき我が街)
私のルーツ、大阪黒門市場へ
幼い頃に母を亡くした私は、父方の祖母に育てられた。父にとって、仕事をしながら男手ひとつで娘を育てることは容易では無かったのだ。母の死後、同居していた祖母が私の面倒をみることになった。そして、私が十九歳になった春に祖母は他界した。
2年前、祖母と一緒に暮らした思い出深い大阪の黒門市場へ、久し振りに訪ねてみた。

色々な食べ物の匂いがする市場には、魚屋、肉屋、かしわ(鶏肉)屋、八百屋、豆腐屋、お菓子屋、乾物屋、漬物屋、味噌屋、鰻屋、卵焼き屋、手作りカレー屋が立ち並ぶ。早速、私が大好物である揚げたてのコロッケを昔から知っている店で買い求め、舌を火傷しそうになりながら食べた。アツアツの衣を冷ますために息を吹きかけ、香ばしいサクッという音を立てて口に含むと、柔らかなジャガイモの食感と玉ねぎの甘みにピリッとした胡椒の刺激がたまらなく絶妙だ。私はいつもこのコロッケを食べると、思わずニターと微笑んでいた子供時代の自分を思い出していた。それから果物屋さんの店先で売られている、新鮮な果物を目の前でカットしたものに、氷と牛乳を入れてミキサーにかけて作る一杯100円のミックスジュースを何十年ぶりかに飲んでみた。冷たく、程よい甘みだがそれでいて濃厚な味は、昔とちっとも変わらず、どんな上等のジュースよりもおいしいと思う。もっとゆっくりと味わいたと心では思っているのだが、どうしても途中でやめることが出来ずにごくごくと飲んでしまい、あっと言う間に無くなるのが少し悲しくなってしまうほど美味なのだ。
これは余談だが、実はそのミックスジュースを飲む前に、私はメロンジュースも味わう羽目になったのである。ミックスジュースを一杯買うつもりで店先に並び注文しようと思った矢先、私の前列で先にメロンジュースを注文して、それを一気に飲み終えた見知らぬ中年の女性が、次の番である私に話しかけてきた。
「あー美味しかったわぁ、このメロンのジュース!お姉ちゃん何飲みはるの?あんたメロンジュースがめちゃくちゃ美味しいから、今日はミックスジュースにせんと、メロンジュースにしとき!」
彼女はそう言って私をじっと見詰めた。その熱い視線に押されて、思わず、
「メロンジュース下さい。」
と口に出してしまった。
私に無理やりメロンジュースを勧めた彼女が、満足したように立ち去ったのを見届けてから、一部始終を見ていた店子の若いおねえちゃんに
「あのう、悪いねんけど、ミックスジュースも一杯貰えますか?」
と注文した。
店子はケラケラ笑いながらジュースを作ってくれた。まるでコントの一場面の様である。
このお節介なおばちゃんのことを関西では“でしゃやきなおばちゃん”と呼ぶ。私は、そんな地元ならではの“でしゃやきなおばちゃん”に遭遇し「ああ、ほんまに大阪に帰ってきたなあ」という実感が沸いてきて、なぜだか嬉しくなった。
確かに、おばちゃんのおっしゃるとおり、メロンジュースも美味しかった。
冷かし客の如く、八百屋や魚屋に並ぶプラスチックの薄いカゴに盛せられている商品を値踏みしながらゆっくりと歩いてゆくと、子供の頃、度々晩御飯のおかずにのぼった屋台で売られている天麩羅屋を見つけた。その店先に並ぶ、ちょっと身体に良くなさそうな程の鮮やかな色をした紅生姜(しかし、癖になるほどおいしいのだ)イカやサツマイモのてんぷらを眺めていたら、不思議に胸がキュンと痛んで、懐かしさが一気に込み上げてきた。
賑やかなオーケストラさながら
あちらこちらで配達の自転車が急ブレーキをかけるキィーという摩擦音
店先や魚を洗うためにホースから流れるジャバジャバという大量の水音
ガマ蛙の鳴き声の如く地面のそこから“安いで、安いで” と繰り返しながら
魚屋のおっちゃんがバリトン声で唸る客寄せの声と
高音ソプラノで歌うようなおばちゃんの笑い声がシンクロナイズする
魚の生臭さと、鱧とうなぎの醤油だれが程よく焦げた香ばしさに
色んな食べ物の匂いがごちゃごちゃに混ざった空気が
市場中に漂う
多少はきれいになったけど
基本的には昔と殆ど変わらないこの空間に佇むと
私はたった一秒で子供時代にタイムトリップする
母代わりの祖母は、不屈の精神を持つ明治生まれの女性

私の祖母は“ハナ”という名前だった。幼い私の母代わりとしての責任を担った、明治生まれの祖母は、愛情をもって私を厳しく育ててくれた。彼女はその名の如く花が大好きで、家の物干しに小さな花壇を造り、四季折々の草花を植えていた。お転婆で叱られてばかりいた私は、祖母に褒めてもらいたくて、学校から戻ると漏斗に水を一杯汲んで、土や花に与えた。
その花壇に、祖母と二人で植えた黄色いフリージアの花が咲いたある日、彼女と話した事を思い出す。
「おばあちゃん、今年もまたフリージアの花が咲いたね。キレイやなあ」
白く粉をふいた擦り傷だらけの膝小僧を両手で抱いてしゃがみ、黄色い花びらを指先で突きながら花を覗き込んでいる私に祖母が言った。
「また咲いたんと違うで、新しゅう咲いたんや。今年の花は去年とおんなじように見えるけど、去年の花は去年の花で、今年は今年の花や。去年のとは一緒にせんといて!今年の方がもっときれいやろって言うてはるわ。花の商売はきれいに咲くことで、それなりに努力してはんのや。」
祖母のウイットに富んだ発想が面白く、子供心に納得したものである。
しつけに厳しく、怒る時は徹底して恐かったが、常にユーモア一杯で色んな事を知っていた祖母。若い頃は新聞記者になることを夢見ていた彼女は、毎朝欠かさずに日本経済新聞、朝日新聞と毎日新聞を大きな虫眼鏡で片端から読破していた。昭和四十年代には、まだ珍しかったマクドナルドのビッグマックとビーフステーキをたまに食べるのが楽しみで、ズボンを履き、ショートヘアーで銀縁めがねをかけ、いつも急ぎ足で颯爽と歩いていた祖母。
商人の町である大阪の道修町で、沢山の奉公人や女中を抱える大店に若くして嫁いだ祖母は、我が子のオシメさえ自分で代えた事が無かったと言う程の奥様暮らしをしていたそうだ。しかし、彼女の伴侶である祖父が戦死し、大阪大空襲で3回も焼きだされて、財産の全てを失い、父の妹で私の叔母にあたるべき人であった娘を交通事故で亡くすという不幸が続けざまに起こった。
けれども、どんな困難に襲われても、いつも前向きにしっかりと背筋を伸ばして笑顔を忘れずに祖母は生きた。子供時代の私は、母がいないことで悲しい思いをした事もあったが、この祖母に母代わりとして育ててもらった経験があったからこそ、どんなに辛く大変な出来事に直面しても、それを乗り越えて強く生きていかなければ祖母に恥ずかしい、と思う精神を養うことが出来たのだ。
私が誕生したという知らせを聞いた時、 一人娘を亡くしてから女の子の孫を待ち望んでいた祖母は、病院に喜び勇んで駆けつけたそうだ。生まれたての私を見るなり
「まあ、なんと鼻べちゃな娘!」
と大声で言って、周りの看護婦さんを爆笑させたらしい。
そんな私に、
「女の子の色白は七難隠すから、表へ出るときは日焼けをしないために帽子を被るように」
と厳しく言いつけ、週に一度は卵で髪を洗い、洗顔は石鹸を使わずに鶯の糞で出来た粉で、そして身体は糠袋で洗うように教えてくれた。
泣き虫だった私に、
「アホやなあ、泣いたら不細工やで。あんたは別嬪やないから、いつも笑ときなさい。あとはおいしいご飯が作れること、そうすればきっと幸せになれる」
と言っては、幼い頃から料理の手解きをしてくれた。
子供の頃から大人になるまで続いている私の放浪癖と極度の方向音痴は、ずいぶんと祖母に迷惑をかけたらしく、彼女の買い物に付き添っては、いつの間にかふら~とどこかへ逸れてしまうので、私は迷子の常習犯であった。交番で保護され、平気な顔をして警官に差し出されたジュースを飲んでいた私のことを、「人に心配掛けて」と叱りながら、祖母は何度も迎えに来てくれた。プロレスと相撲が好きで貴ノ花関(亡き二子山親方)が勝つと、普段は滅多に食べられない天麩羅うどんをご馳走してくれた。
従って、幼い私にとっての大相撲は、その内容よりも祖母の贔屓力士の勝ち負けの結果がかなりの重要度を占めていたので、貴ノ花関以外の力士の名前は殆ど覚えていない。
祖母は七十歳を過ぎて、大阪万国博覧会の区画整理で立ち退きとなったビジネス旅館をたたみ、黒門市場の傍でお好み焼き屋を始めた。彼女は小さなビルの模型を買って、それを神棚の隣に置き、いつかお好み焼き屋でビルを建てるのだと言っていた。私はそんな祖母を愛し、心から尊敬していた。
五十嵐ゆう子
JAC ENTERPRISES, INC.
ヘルス&ウエルネス、食品流通ビジネス専門通訳コーディネーター

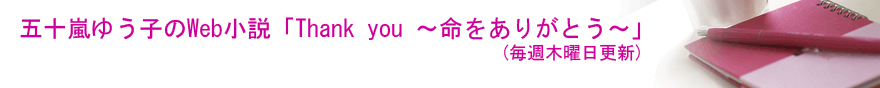

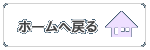
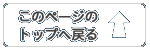
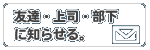
2 件のコメント
大阪のおばちゃんの何気ない日常のおもろい会話や行動が目に見えるようです。また、天ぷらやうなぎ、喧騒した市場の様子が目に浮かびます。また、お祖母さんとの日々の会話も聞こえるようで楽しいブログですね。
匂う、感じる、聞こえる文章に感動です。
ありがとう御座います
皆様に出来る限り体感していただけるような
文章を今後も心がけていこうと思っています