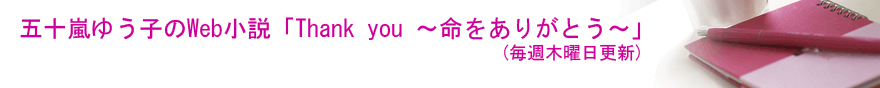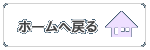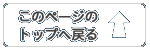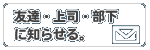〈第3話〉 下町人情に育まれた少女時代
第1章 ―――― My Sweet Hometown(愛しき我が街)
下町人情に育まれた少女時代
関西の台所と言われる黒門市場は、どこよりも新鮮で高級な食材が手に入る。特に魚屋と活けふぐ専門店が多く、年末になると買い物客でごった返し、猫の手も借りたいほど忙しくなり、今でも東京のアメ横と並んでテレビ中継されるほど、歳の暮れの賑わいぶりは大阪名物のひとつでもある。大晦日の2日前になると、商店主らに頼まれ、近所の子供達は売り子として店を手伝う。これは30年以上前でも破格の高級アルバイトで、1日1万円と御祝儀をプラスした3万円以上の報酬をたった2日間で貰った。当時そんな大金を稼ぐことが出来たのは、北新地にあるクラブのホステスさん位だったと思う。それを中学生になったばかりの子供が、数日で手に入れることが出来るのだから断る理由が無かった。
大晦日の店じまい後には、活ふぐや鯛の塩焼き、刺身の盛り合わせ、ブリの味噌漬け等と、店の残り物を欲しいだけ頂けるので、我が家の正月三が日はかなり豪華な食卓になった。私は売り子だけでなく、股がると足が地面に届かない大人用の自転車に乗り、千日前や染衛門町の料亭へ配達をしたり、時には、早朝に大型トラックへ乗せられて、仕入れをする為の中央卸売市場に連れて行ってもらった。そこでとびきり新鮮な魚と、暖かいご飯でにぎった立ち食い鮨をご馳走してもらったことは大人になっても忘れられない。柔らかな酢飯と、歯ごたえがあり脂がのった生魚を、プラスチックの皿に注いだ醤油に浸して一口頬張れば、口の中で溶けていくようで、湯気で目の前が霞むほど熱くて濃い味の赤出し味噌汁を飲めば、極上の幸福感に包まれた。何を食べても抜群にうまくて、寿司はどんどんお腹の中に収まっていく。
「おっちゃん。めちゃくちゃおいしいなあ。あー私いままで生きてきて、ほんまに良かったわ。」
「面白いこと言う子やで。あんたはまだたいして生きとらんやないか。ええからお腹一杯になるまで仰山食べて、もっと大きなり。ほんでしっかりおっちゃんの店手伝ってや!」
と言うと、おっちゃんは自分の分も私に差し出してくれた。早朝から、あんなにたくさん食べた事は後にも先にも無いだろうと思う。仕事用の防水ジャンパーを着た人々の、肩と肩がぶつかりあう混みあった店内は酢の甘い匂いに包まれて、真昼間みたいな活気だった。客の出入りが激しいため、ほとんど開けたままの入り口から、時折流れ込む外気は身を刺すように冷たかったが、そんな事も気になら無い程、本当においしい寿司だった。食いしん坊の私は、様々な場所で名物だといわれる味を探し、ずいぶん色々と食べてきたと思うのだが、あの立ち食い寿司に勝るほどの寿司に出会ったことが未だかつて無い。

私はこのアルバイトのおかげで、既に中学2年生で魚を3枚に下ろす技術を身につける事が出来た。それでも手や体には魚のにおいが染み付き、凍えるように冷たい水を始終使うので両手はアカギレだらけになり、中学から高校まで、毎年このアルバイトを自ら望んで引き受けていたのは、女の子で私ぐらいだったかもしれない。昼の賄いは、出前のうどんと寿司の盛り合わせに、店でさばいた新鮮なお刺身と、毎日が豪勢な献立だった。私はそれらをパクパクとお腹一杯食べて、残りは必ず家に持ち帰った。いつもやせっぽちのくせに大食いな私を周りの人が見れば、家で十分に食べさせてもらえてないのでは?と勘ぐられていたかも知れず、無知な子供とはいえ、今思い出すと恥ずかしい。もう少しお上品に振舞い、たまにはご飯のお代わりもやめて、時には遠慮すべきだったかなと、ちょっぴり反省するが、後の祭りである。
アルバイトで稼いだ大金は、貯金もせずに洋服や自転車等を買い、全て自分のために使った。けれども、小さい体で一生懸命働く私を見て、これも又、家計を助けていたのだと誤解した人も居たらしい。とすれば私は黒門市場中の人から、ドラマのおしんの如く、家族のために幼い頃から苦労をしてきた健気な少女と、噂されていたのだろうか?
小学校・中学校と同級生だった友人の親で、今も元気に魚屋を営む清水のおばちゃんを尋ねたら、ついでに幼い頃からお世話になった隣の漬物屋のおばちゃんも出てきて大歓迎をうけた。
「あんたはお母ちゃんを幼い頃に亡くして、ほんまにここでは苦労したなあ。おばちゃんらは、いっつもあんたのこと可哀想やな、幸せになって欲しいわって話してたんやで。
いやあアメリカに住んではんの、美容家と通訳さんやってんねんて。英語も話すん?
ええ、あんた、立派なお仕事して、結婚して、子供にも恵まれて、良かったねえ夢がかなって。この町を出て行って、とうとう幸せになったんやね。ほんまにおばちゃんは嬉しいわあ。」
と言って涙ぐみながら、私が話を差し挟む一瞬の隙も相手に与えない、見事なまでの猛烈スピードでしゃべり続けていた。
そのおばちゃんの言葉を聞きながら、心の中では ”エー!そうなん?” という疑問の言葉を投げかけていた。子供時代に私の夢の話などおばちゃんに語ったことは無く、悲しみや、嫌な経験が全く無かったとは言えないが、まわりが想像するほど不幸な子供時代だったなどと考えた事も無い。
喧しいほどの賑やかさと、有り余るほどの優しさで私を包んでくれるこの黒門市場が大好きで、だから今でもホームシックにかかるくらい帰りたい場所なのである。

他人の思い込みとは勝手なものである。
まあ、おばちゃんらが長年そう思い込み、今の私を見て喜んでくれているのだから、例え一方的にでも「良かったわ、おばちゃんも嬉しいわ」と朝の連続ドラマの最終回を見た時のような感動に似た気分を味わってくれるのなら、まあそれも“エエヤン”という気持ちになった。
そやけど、おばちゃん。あんとき話せへんかったけど。(というか、おばちゃんの話に入る事が出来なかったという方が正しいかな)ほんまはもっと色々あってんで。おばちゃんが聞いたら、もうちょっとだけ『良かったなあ』って言うてくれはるかも知れへん、私の夢探しのお話を、今から聞いてくれる?
五十嵐ゆう子
JAC ENTERPRISES, INC.
ヘルス&ウエルネス、食品流通ビジネス専門通訳コーディネーター