〈第4話〉 母の死
第2章 ―――― Beginning of My Journey (旅の始まり)
母の死
私が5歳の誕生日を迎える前に、母が亡くなった。母の命を奪ったのは進行性の子宮癌だった。娘の私が言うのもおかしいが、母は美人だったそうだ。私の勉強机の上に立てかけられた、涼しい瞳で微笑む母の写真がその片鱗を物語っている。享年たったの33歳。歳よりもずいぶん若く見えたらしい母の死に顔は、まだ少女の面影を残していた。

元々病弱だった母は、出血がなかなか止まらないという病を生まれつき抱えていたので、私を身篭った時も危険を覚悟しての出産だったらしい。母は私を随分と可愛がり、片時も傍を離れなかったそうだ。
しかし、物心がつき始めたばかりの幼かった私に、残された母の記憶はほとんどない。母はどんな香りがしたのだろうか、母のことを私はなんと呼んでいたのだろうか?
「ママ?お母ちゃん?お母さん?」悲しいかな、それさえも覚えていない。ただ一つ記憶に残っているのは、薄化粧を施され、たくさんの白や黄色の花々に囲まれて棺の中に横たわる母が、ディズニーの絵本に出てくる“眠れる森の美女“さながら美しかった事である。その透き通るように白く柔らかな最期の表情だけは、今でもはっきりと瞼に浮かぶ。
近年に父が心臓発作で没した折、母を弔って頂いたお坊様と再会する機会を得た。彼もまた、棺の端を小さな両手で掴み、母の死を理解できずにその死に顔を覗き込んでいた幼い私の姿を、ずっと心に留めていてくれたそうだ。
「何が悲しいて、ちっちゃな子供を残して死ななあかん仏さんと、親を亡くしたことの意味をわからへん無垢な子供を見るときほど辛いことないな。そんでも職業柄、若うして病で苦しんで逝った仏さんを仰山見てきたけれど、あんたのお母ちゃんほど安らかで綺麗な死に顔はめったに見いへんからよう覚えてるわ。」
とおっしゃった。
その言葉を聞いて、私の幼い記憶は決して誇張されたものではなく、見たそのままの母の顔を覚えていたのだと確信出来て嬉しかった。
現在よりも一層『死』に近い病と闘い抜き、相当に苦しんだはずの母の死に顔が、なぜ印象に残るほどまでに美しくありえたのか?
私が成長したある日、母代わりとなって育ててくれた祖母が伝えてくれた母の言葉がある。もはや為す術がなく、死が目前に迫り、モルヒネ注射で痛みを抑えなければならないほどの状態で、母はこう語ったそうだ。
「体中が耐えようもなく痛い、こんな酷い苦しさを味わうくらいなら、ただただ早く終わって欲しい、もう死んでしまいたいと幾度となく思います。でも、幼い娘を残していかなければならないことは、その痛みの何十倍もの力で私を苦しめます。私がこのまま死んでしまって、まだ幼いこの子はどのくらい私のことを覚えてくれるのでしょうか?母がいたということすら、忘れてしまうのではないでしょうか?何よりも辛く悲しいのはその事です。」
彼女のそんな思いが天に伝わり、最後に奇跡を起したのだと私には信じられる。母は、幼い私が決して怖がることのないよう、そして美しい母の面影を心に刻むことができるよう、その最期の瞬間を穏やかに終えることが出来たのだ。
そして、更なる母の願いも叶えられた。それは私が大人になって随分後に気付くのだが、生涯私の魂に寄り添い一心同体となって私の人生の道しるべとなり、私が生きる限りGuardian Angel(守護天使)として、私の傍らでいつも守り続けてくれているのだ。今の私にはそれがしっかりと感じられる。

そして成人した私は、留学の為に米国ロサンゼルスへ渡った。そこで今の主人である在米日本人の彼と出会い、3年間の付き合い後に結婚して、子供に恵まれない5年が経ち、不妊治療と3度の流産の末、ようやく一人息子を授かった。
『奇跡』と言うものを、もし形で現すとすれば、私は『命の誕生』こそ、まさしくそのものであると思う。
母体から取り出されたばかりの、まだヌメヌメとした体液で覆われた産まれたばかりの赤ん坊は、輝く光の衣を纏ったように神々しかった。それを見た瞬間、産みの辛さも痛みも全て消えてしまい、今まで味わった事の無い幸福感を感じた。
看護婦さんに体を拭いてもらい、真っ白なコットンのおくるみに包まれて、私の腕に手渡された時、息子は泣くばかりか、私の顔をみてニターと微笑んだ。
私は驚いて、産科の先生に問いかけた。
「先生、今 この子今笑いましたよ。見えているんでしょうか?」
「産まれたばかりの赤ちゃんは凄く近視なのですが。ぼんやりとなら見えているのではないかな。外の世界へやっと出てこれて嬉しいんだね。“ハイ、マミー宜しくね”と貴方に挨拶してるんですよ」
私はその愛おしい笑顔に、心からこう返した。
「うちへ来てくれて本当にありがとう。大切に、大切に育てるからね。」
我が子をこの手に抱き、一番最初に願ったこと
“せめてこの子が私の事を、母と呼べるまで生きていたい”
我が子が初めて私を『マミィ』と呼んだ時、心から願ったこと
“私をそう呼んでいた事を、この子がずっと覚えていられるほど
成長するまで生きていたい”
そして、我が子が6歳だった2002年の4月16日
癌を宣告された私が、天を仰いで誓ったこと
“決してこの子を母が無い子にさせはしない
私は死なない
いつまでもこの子の為に、生きていくんだ”
五十嵐ゆう子
JAC ENTERPRISES, INC.
ヘルス&ウエルネス、食品流通ビジネス専門通訳コーディネーター

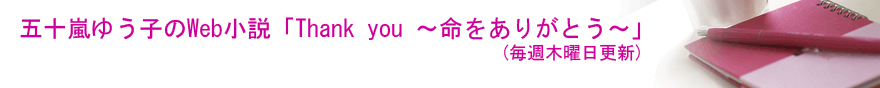

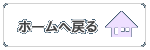
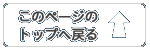
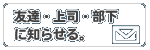
4 件のコメント
読み続けるうちに、涙は嗚咽に変わりました。
でも、その涙は、悲しみの涙。というよりも、
悲しみから感動、勇気へとつながる涙へと変化していきました。
今、ココにある幸せ。わたくちたちのご先祖様へ。
感謝です。
そして、ゆう子さんの半生をここで知れました。
今のゆう子さんがあるのは、お母様そして周りの方々の
たくさんの助けもあるのですね。すばらしいみなさんです。
コメントありがとう御座います。
日々生きてきて、母の存在を感じない日はありません。
先日、お会いした印象とまったく違う五十嵐さんの一面をみたようです。幼少のころの悲しい惜別の状況が目に浮かびます。この涙せずにはいられない状況を客体化して表現されていることにまた、感動します。人生の中で、時間を越えて人が存在する(お母様)ことの意味や力を感じます。
今、日本では人情や愛情が不足して悲しい出来事が多い中で、深い感動と勇気がでるお話に魅せられました。ありがとうございました。
お心のこもったコメントを頂きまして非常に感謝致します。私もこういう形で私の母や祖母のことについて語らせていただくことになった事が嬉しく、また自分自身が彼女達に再会したような気になれました。そして皆様とこうしてその感動をシェアーできることに喜びを感じます。本当にありがとう御座います