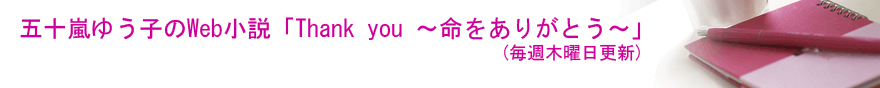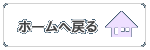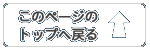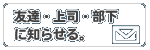〈第9話〉 奇跡はこの場所で毎日のように起こっている
第3章 ―――― Open the Door of Health Opportunity (健康を得るために開く扉)
奇跡はこの場所で毎日のように起こっている
癌宣告を受けて以来、自らの状態にタイムリミットがある事を心のどこかで感じつつも、私はかたくなに西洋医学以外の治療法を模索し続けた。
そして数週間が過ぎたある日、私のその後の人生に大きな影響を与えたOptimum Health Institute―オプチマムヘルス協会 (www.optimumhealth.org)、通称O.H.I.の存在を知る事になった。そこは、カリフォルニア州サンディエゴ市のレモングローブという小さな町に、1976年に創立された米国で初の本格的ホリスティックセンターである。

私が告知を受けた時から色々と親身になって相談に乗ってくれていたヨガのインストラクターの女性から、もし興味があればとO.H.I.のウェブサイトが書かれたメモを手渡された。そこでは最低1週間滞在して行なう徹底的なデトックス(デトキシケーションの略。体内に残留する様々な病気の根源となる毒素や老廃物を取り除く事)と、食事療法のプログラムが行なわれている。彼女自身が重い子宮筋腫にかかった時に、ボーイフレンドからそのプログラムを是非受けるようにと勧められたそうだ。そして彼女はこの施設に入所した結果、手術の必要もなくなり、筋腫も消えてしまったそうである。このオプチマムヘルス協会には全米から深刻な病を抱えた人が集まり、癒され、中には医師に見放された患者までも奇跡的に助かった症例が沢山あるのだという。
毎週日曜の午後、この施設に興味を持つ人々の為に、施設とプログラムに関する一般見学ツアーが無料で行なわれている。それに参加する事を彼女は提案してくれた。
早速、その週末に行われる見学ツアーに主人と一緒に行く事にした。
施設のあるレモングローブ通りへと続くマサチューセッツ街で高速を下り、賑やかな商店街を抜けると静かな住宅地に入った。少し前方に進むとスペイン様式の建物の屋根が見えた。錠が外されている大きな鉄の門をくぐると、丁寧に芝を刈り揃えてある広大な庭に沢山の草花が咲き誇っていた。その庭の中央には何名かの見学者が既に集っており、夕方の4時になったところで、内部の建物からスタッフが数名現れ、ツアー開始の声を掛けた。

最初に施設内の簡単な説明を行い、屋外にジャグジーがある中庭から食堂、内部に瞑想ルームがある図書室、施設で出される有機野菜や果物を栽培する畑や”ウイートグラス”と呼ばれる小麦草を栽培する温室と保管室、その草を搾って飲むための専用ジューサーが設置されている部屋等を見せてもらった。それらを通り過ぎると、別の中庭にトリートメントセンターと呼ばれる白いプレハブの建物が並ぶ場所に案内された。
各建物には、外部から招いたプロのセラピストによるマッサージやレイキ療法、そしてコロンハイドセラピーという特殊な器機の使用と腹部へのハンドマッサージで腸の宿便を吸い出す療法等、様々なトリートメントルームが設けられていた。これらのセラピーは通常の価格より低料金で入所者に提供していると説明された。
ツアーの最後に大きなスクリーンが設置された講堂に通された。そこで20分ほどO.H.I.に過去入所して、健康を取り戻すことが出来た人々が出演するフィルムを観た。終了後、既に没された創立者であるミスター・ニースの未亡人であり、州立サンディエゴ病院の元婦長である、現在のO.H.I.代表、ミセス・ パム・ニースが登場し、簡単に挨拶の言葉を述べた。
「奇跡はこの場所で毎日のように起こっています。そして起すのはあなた自身です。
私たちの使命は、ここに入所しておられる人々の心と肉体がピュアーな状態になり、
結果的に最善の健康を勝ち得るための手助けをすることなのです。」
その言葉を聞いた時、内なる声は再び私に語りかけた。
「ここに入所し、体内を解毒する事が先決だ。化学治療はそれから考えても遅くない!」
その後、主人と相談を重ねO.H.I.に1ヶ月間入所することを決めた私は、家族の世話を手伝ってもらうために、彼の母を日本から呼び寄せる事にした。実は義母も1985年に直腸がんを患い、大手術の末に一命を取りとめ、現在人工肛門をつけてはいるが、術後20年以上経った今も元気に暮らしている、癌の生還者である。100%西洋医学によって命を助けられた義母に、アメリカに来て頂く事となった私の事情を話したら、
「そんな大病をしているのに何故すぐに医者の言うことを聞いてきちんとした治療を受けないのか? 幼い子供を置いて、そんなところへ1ヶ月も入って本当に良くなるのか?大体そこは信用できる施設なのか?」と問われた。
未だ、代替医療やホリスティク療法に対する認識が一般的に浸透していない日本で暮らす義母にしてみれば、当然の意見であった。けれども、私と共にツアーへ同行し、施設の内容をある程度把握した主人が、「とにかく私の思うようにやらせてやってくれ」と彼女を説得してくれた。
それから義母が来ることになり、その準備や空港への出迎え、アメリカの家事に慣れない義母への説明や食料等の買い物やらで、施設に入るまでの数週間はあっと言う間に過ぎた。
O.H.I.への入所を待つ間の約2ヶ月間、インターネットで探したロサンゼルス市内の代替治療クリニックに通った。そこで処方された漢方やサプリメントのおかげか、体の不調は多少改善した様子だった。
出発する前日の土曜日は、子供が週末に通う日本語幼稚園で毎年開催される春の大運動会だった。早起きをして、子供の好物が沢山入ったお弁当を重箱に詰めた。私の体調もそこそこ良好で、運動会では親子参加の障害物競走を息子と手を繋いで走り、競技に参加する息子を声が嗄れるまで応援した。
翌日、自宅を出る間際に息子を呼んで、私は思わず彼の体を強く抱きしめた。
「いたいなあ。もうやめてえ、ストップ!」息子はキャッキャと笑いながら、大袈裟に体を捩じらせて叫んだ。当時6歳の我が子はユウキと言い、関西弁と英語のちゃんぽんで喋る様があどけなく、まだミルクと甘いキャンディーの匂いがして、ずっとそのまま抱きしめていたい衝動に駆られた。“柔らかで愛おしい、命より大事な私の宝物。”と、心の中で呟いた。
ユウキは、私が1ヶ月間家を離れる事の意味を全て理解するには幼な過ぎた。私が戻る時に現地で会い、彼を大好きな遊園地へ連れて行くという約束をとても楽しみにし、絶対にそれを忘れないようにと出掛ける私に指切りをねだった。
扉を開けたままの玄関でユウキの目線と向き合うようにしゃがみこみ、その小さな指に絡ませた私の指をそっと緩めて言った。
「おばあちゃんの言うこと良く聞いて、賢うしとかなあかんで」
「うん。ぼく、かしこうするよ…なあマミー?」
「何?」
「マミーはキャンサーなの?キャンサーってなに?」
一瞬心臓がドキンと鳴った。しかし冷静を装い、静かに問いかける。
「誰が言うてたん?」
「おともだちのサミー。サミーのダディとマミーがそういうてたんやて。」
サミーの父親は医者であり、以前私の病気について相談したことを思い出した。
その短い合間に、様々な思いが頭に浮かんだ。
“私はこの子に自分の病気の事を伝えるべきなのか?それとも・・・、このまま黙ってやり過ごしてしまうの?それは息子を騙すことにはならないのだろうか・・・。しかし幼い彼にとって、この現実は余りにも残酷過ぎないのか? それでも息子がそれを知りたいのなら、それを知る権利はあるのかもしれない。でも・・・”
私は迷っていた。しかし、もうそれ以上考えている余裕も無かった。息子の目を真っ直ぐに見つめて、動揺を隠しながらこう問いかけた。
「ふーん、そうか…ユウキ、キャンサー(癌)って何の事か知ってる?」
「しらん!」
と無邪気に言って、おもちゃで遊ぶために2階へ駆け登って行った息子の後ろ姿を見送ったら、不意に肩透かしを受けたように体から力が抜けた。と、同時に母親の置かれている現状について、何も理解出来ていない息子を思うと胸が痛み、喉の奥が喩えようもなく熱くなって泣きそうになった。
“あかん、ここで泣いたらもう行かれへんようになる。”そう思った。湧き上ってきた感情を一気に飲み込んで、義母に家の事を宜しくお願いしますと頼んだ。それから後ろ手で扉を閉め、急ぎ足で主人の待つ車へ乗り込み、努めて明るい声で言った。
「じゃあ、行こうか!」
私の気持を察してか、主人の片手が私の手の上に重なり、ぎゅっと力が込められた。
6月初旬のロサンゼルスはカラッと晴れた清清しい天気が続く花盛りの季節で、フリーウェイの路肩にまでタンポポやポピーなど、様々な色をした花が咲き乱れる。その頃は丁度、ジャカランタという桐の花に似た藤色の花が木々に満開で咲き誇る時期であった。
おそらく、車内から見た外の景色は素晴らしく美しかったと思うが、車の助手席側の窓にもたれた私の視界に景色は一つも入ってこなかった。
息子を産んでから、こんなに長く家を離れることは初めてだった。残してきた我が子の笑顔を思い出すとまた涙が溢れそうになった。私は深呼吸をして気持を静め、一粒の涙も流すまいと自らを奮い立たせた。
“今は泣いている場合ではない。愛する息子の為に、そして私の為にも、もう引き返すことは出来ないんだ。”と思った。
自宅から目的地であるO.H.I.までは車で2時間程かかる。車内では主人が常にカーラジオの周波を合わせているクラッシックロックが流れていた。それを私が普段好んで聞くバラードやスロージャズがメインのFMラジオ局「94.7 WAVE」に切り変えると、その頃流行っていた映画“タイタニック”のテーマ曲、セリーヌ・ディオンの“My Heart Will Go On” の前奏が流れてきた。哀愁を帯びた旋律の中、彼女の歌声がさんざめく小波のようなメゾピアノから、力強く波打つ大海原の爆音のようなフォルテシモへと変調していった。
私は、自分が見知らぬ海に漕ぎ出る一艘の小船に思えた。
けれど、どんな嵐が来ても、例え氷壁にぶつかっても、この船を沈ませる訳にはいかない。自分に押し寄せる大きな波を必ず乗り切って見せる!
私はそんな思いを抱いて、流れる曲に耳を傾けていた。
Near, Far, wherever you are
近くても、遠くても、どこにあなたがいても
I believe that the heart does go on
この気持ちは続いていくと信じている
Once more you open the door
再び、その扉を開いて
And you’re here in my heart
そして、あなたは私の心の中にいる
And my heart will go on and on
そして、私の心はどんどん前に突き進む
(Celine Dion “My Heart Will Go On” より歌詞を一部抜粋)
そして、不安に心を震わせながら、健康を手に入れるために開かなければいけなかった最初の扉を私はノックした。“トントン”真っ白な扉が開くと、そこにはオープンハウスで出会ったスタッフ達が温かな笑顔で私を迎えてくれた。
「ウエルカム トウ O.H. I. ! 」
この瞬間、私の新たなる人生の扉も開いた。

五十嵐ゆう子
JAC ENTERPRISES, INC.
ヘルス&ウェルネス、食品流通ビジネス専門通訳コーディネーター