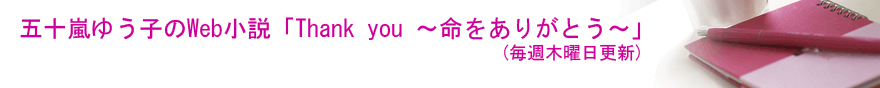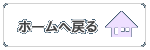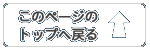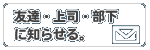〈第12話〉 神から与えられた最初のレッスン
第5章 ―――― The Story about Johanna ヨハンナさんのお話
自宅に戻り、オプチマムヘルスでヨハンナさんから渡された彼女の闘病記を、幾度か繰り返し読んだ。日本に住む癌患者にヨハンナさんの体験を役立てて欲しいという彼女の願いは理解できたが、あの頃の私は自らの病を克服するためのスタートを切ったばかりで、先がはっきりと見えていない状態だった。そのため、すぐ彼女の原稿を訳すという気持ちには到底なれなかったし、翻訳をするにしても、その頃の私には技術も経験も無かった。
しかし今、やっとその時が訪れたと思う。書斎の奥に仕舞った彼女の原稿を取り出して、7年振りに読み始めたら、再びヨハンナさんの透き通った歌声が聞こえてきた。
*************************************
神から与えられた最初のレッスン (ヨハンナさんの闘病記)
1999年9月。定期的に行っている健康診断のためのレントゲン写真を撮るまで、私は自分の肺の80%が癌で侵されていたことに気付いていなかった。
しばらくして、以前切開手術を受けた右胸の下に大きなしこりが見つかり、右腕リンパ節の数箇所にもその影響は広がっていた。
その事実を知る直前の私は常時疲れを感じ、呼吸をするのさえ困難だった。すこし前にもそんな症状が起っていた。けれども花粉の発生が多いアーミッシュの農業地帯に位置するランキャスター郡に引っ越した頃から咳き込む事は度々あったので、ずっとアレルギーのせいだと思っていた。
予期せずに、突然、死の宣告を受けることは言葉にし難いものがあった。
まず、全身が麻痺するような感覚が起こり、続いて疑いの感情が生まれた。
“もしかしたら、目の前にあるレントゲン写真は私のもので無く、誰か他人の肺を写したものではないのか?それとも機器が故障して変な影が現れたのかもしれない。”と考えた。
しかし、その直後に事実が私とその家族に伝えられた時、有りのままの真実が私の中に浸透し、恐怖は絵に書いたようになった。
あの頃の私にとって、“癌”という言葉は恐怖や死を意味していた。
「大変だ!」と心の中で叫んでいる私は、まるで台風の目の中にいるようだった。
周りにいる全ての人たちが私を気に掛け心配し、沢山のアドバイスを与えてくれ、そして恐れた。
出来る限り早く、適切な処置を受ける必要があった。しかし様々な検査を受けている間に、感謝際やクリスマスの時期と重なってしまって、専門の医師を探すのが困難になった。けれども主イエスが私をすぐ傍に引き寄せてくださったお陰で、平穏が心の中に沁み込み、この病が私と家族を脅かし引き裂いてしまう恐怖と憤りの感情から、私を守ってくれていた。
私は1997年に患った初期乳癌の闘病後、健康管理を怠った為に再発という事態に陥ったのだと考えた。6ヶ月から8ヶ月、もしかしたら1年しか生きられないかもしれないと自ら予想し、打ちひしがれた。神様は、そんな私に最初のレッスンを与えられた。
「けして恐怖から、結論を出してはいけない。」
そんな状況にも関わらず、私は自らが働いていた「サイト・アンド・サウンド司教連盟」の婦人たちと、以前から計画していたクリスマスパーティの準備をすることに決めた。 “仮に地獄の果てからやってくる恐怖の怪物が、私の命を奪うことが出来たとしても、私に残された時間まで奪い去ることは出来ないのだ。”と思った。
友人のクララと、義理の娘であるサンディが私の元へ来て色々と手助けをしてくれた。私はクリスマスツリーを買った。彼女達は私の自宅を掃除し、飾り付けをしてくれた。
パーティは本当に素晴らしかった。私は、そこに集まった婦人達に自分が置かれている窮地について打ち明ける勇気を持たなかったのだが、仲間の一人であるリネルが、彼女達に打ち明けるように私を促した。
「そうすれば貴方の為に祈ることが出来るからよ」
と言ってくれた。
晩餐の後、私の主人であるロバートと私の回りに彼女達が集まって、多くの祈りの中で一番最初の祈りを、病の為に大きな声を出すことが出来なかった私に代わり、天まで轟くような声で捧げてくれた。これらの親愛なる女性達は、信仰をもって私が主に癒されることを祈ってくれたのだ。
その後、部屋を見渡すと、私の友人や家族の優しい顔と、背後には実際には居る筈も無い何百という祈りの行列が浮かんだ。
「これらは私が地上に創造した最も美しい者達で、私からそなたへの贈り物なのだ。」
まるでジーザスがすぐ隣に立ち、私にそう囁いてくださっている様だった。
後に、それがどれほど喜びに満ちて貴いものであったかを私は理解した。“仮に私が、神様に愛されている事実を少しでも疑う事があるとすれば、再びそのような思いを抱かないようにしなければいけない”と思った。
しかし暫くして、肉体的には“悪い”から“最悪”という状態になった。
2000年1月、酷い状態の流行性感冒と内臓感染のため、私はランキャスター病院へ救急車で運ばれた。1月11日の夜、私は神様に召されていくのだと確信していた。

死への恐怖は無かったが、一方では沢山の心配事を抱えていた。何よりもまず、連れ合いのロバートに関して苦脳した。彼は最近になり、物忘れが頻繁になってきていた。私が死んだら、誰が彼の面倒を看るのかと途方に暮れた。子供達のことも心配だった。自らの健康管理を怠った過ちを彼らに許してもらいたかったし、この悲しみの全てを共に分かち合いたかった。
主に私への許しと、再びチャンスを与えて欲しいと請うた。私はしっかりと目覚めていた。そして、主への感謝と賞賛の気持ちで一杯だった。私に寄り添っておられる主のために歌いかった。私の歌声は殆ど声にならなかったが、心は高く舞い上がり私は深い眠りに落ちた。
目覚めた時はまだ明け方だった。私の病室は7階の東側に面し、ベッドのすぐ傍に窓があった。外は凄く素晴らしい夜明けだった。
「なんと輝きに満ちた色なのかしら」
と思わず口に出して言った。本当に信じられないほどの美しさだった。その光景は私に沢山の希望を与えた。主が、私のために新しい始まりを用意されていることを心から知った。
やがて、私の病室に担当の看護婦が血液を採取するために入ってきた。彼女は聡明で信仰心のある女性だった。私達は、“如何に人間は全てを降伏することが出来るのか?“について語りあった。
「私達は降伏を口に出し、真摯な気持ちで我々の重荷を取り除いてくださいと主にお願いしますよね。しかし私の経験では、人は自らの背を壁にもたれ掛かるようになるまでは、全てを完全には降伏しないのです。」
と彼女は言った。その言葉は私の胸の奥を突いた。
私は、今自分が置かれている状況を新たなる光に照らして見つめてみた。
ここで、私は自らの背を平らにして横たわり、癌によって死んでいこうとしている。自分以外の人どころか、自分自身のことすら世話することも出来ず、ロバートや子供達や金銭問題、その他もろもろのことについて不安を抱えている。自らの背を壁にもたれ掛ける瞬間が主に降伏する時だとするのなら、この状態こそがそれなのだ。
“汝は、如何に降伏し、確りと意思を持つことが出来るのか?”
ジーザスが両手を広げ、私の重荷を取り除こうとしている姿を頭に描いた。既に失うものも得るものも無かった。ロバートや子供達のこと、その他の心にかかった暗雲についてもだ。
「主の御手にお任せします。」
と声を大にして言った。主の寛大さは私を喜びで満たした。多くを諦めれば諦めるほど、喜びはより大きくなった。
その日の午後、私は病院の忙しい廊下で次の検査を受けるために待たされていた。車椅子に座り、左手には点滴が打たれ、顔全体はマスクでしっかりと覆われていた。しかし、私は疑う余地も無く、主ジーザスは自分と共にその場におられたことを知っていた。人々は足早に私の車椅子の横を通り過ぎて行き、誰も私の事など気に掛けてはいない。
私はクックッと笑い出した。なぜなら、その瞬間にはっきりと私の癒しが始まったと知ったからだ。主の歓喜は私の力となった。
五十嵐ゆう子
JAC ENTERPRISES, INC.
ヘルス&ウェルネス、食品流通ビジネス専門通訳コーディネーター