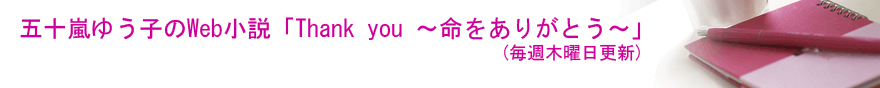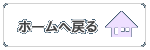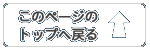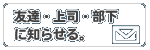〈第16話〉 最善(オプチマム)の方法 (前編)
第6章 ―――― The Story of How I Fought My Illness (私の闘病録)
最善(オプチマム)の方法 (前編)
聖ジョセフ病院に入院して、尿検査に始まり、血液検査、CTスキャン、背中の後ろから細いドリルのような棒を差し込み腫瘍の一部を採取する等の様々な検査を受けた後、ドクター・ケヴィンからこう告げられた。
「腹水が肺にまで拡がっており、かなりの量の水が肺の中にも溜まっています。よくこんな状態で我慢していましたね。呼吸するのも辛かったでしょう? 至急、専門医に再度の検査をしてもらい、肺と腹部の水を抜かないと危険です。」
言われてみると、入院する3~4日前から息をするのが少し苦しいような気がしていた。そして、腹部と心臓の間がタプタプと音がするような感じがあった。けれどもその時は、入院出来るか否かという不安の方が先立っていたので、それほど深刻な状態だったとは思ってもみなかった。それから数時間、専門医による検査の直後に、肺とお腹に穴を開けてストローのような管を通して水を吸い出すことになった。この処置は私が今まで味わったことの無い、想像を絶する苦しみだった。それまでは、子供を生んだ時の経験が人生の中で最も大変な苦しみだと思っていたが、肺から水を抜く事はその倍以上の辛さだった。
最初、肺の近くに穴を開けたのだが、局部麻酔が効いているので何も感じなかった。最悪な状態は管を差し込んだ直後にやってきた。それは水を吸い出す時だ。一瞬、肺を思いっ切り誰かの足でぺちゃんこになるまで踏みつけられたような感覚を覚え、痛いというより強烈な圧迫感で息が詰まりそうで苦しかった。水を抜いていたのは僅かな間だったと思うが、こんなことが1分も続いたらきっと死ぬなと思った。
吸い出した直後、思いっきり咳込んだ。その後はお腹の水を吸い出したが、これは肺に比べると全く楽であった。
「ハイ、終わりました。」と専門医の声がして前を見ると、カルピスをもう少し黄色くしたような液体が1リットル瓶の上まで入ったものと、その半分ほどが入った別の瓶、合計2本の瓶が台の上に並んでいた。“うわあ、凄い!こんなに水が入っていたのか”と驚いた。それでもお腹の水は腫瘍の腫れが邪魔をしており全て吸い出すことは出来ないのだと言われ、放っておけばまた肺に水が溜まることもあるのだよと脅かれた。あれをもう一度繰り返すのかと思うだけで、心底恐ろしくて震えを感じた。

そして、また尿検査、血液検査と、検査、検査の連続であった。
入院してから3日目の夕方、遂に、翌朝から抗がん剤投与を開始すると告げられた。緊張と不安が体中に駆け巡り、興奮して眠れない私に睡眠剤が与えられた。
そんな私の元へドクター・ケヴィンが訪れ、ベッドの傍らに腰掛けてこう話し始めた。
「デアンジェロ先生と僕は、君のことについて真剣に話し合いをした。何故、今まで君が抗がん剤治療を拒んできたのかという事も含めてね。その副作用や毒性について考慮すれば、抗癌剤投与が100%正しい道なのか、どうなのか?と、迷う患者さんは沢山いるんだ。だから君は不安で、誰かにその気持を理解してもらいたかったのではないのかな?僕も多少ではあるが統合医療について理解を示しているんだ。だってデアンジェロは僕の親友で、僕は西洋医学を実践するドクターとしても彼の良き理解者なのだから。但し、今の君を救うには、今僕が行おうとしているこの治療が最善(オプチマム)の方法だと思う。でも安心して欲しい。僕はこの道の専門家であり、必要以上の抗がん剤投与は決して行わない。きちんと君の状態をコントロールしながら治療を続けるから。さあ安心して眠りなさい。」
そして先生は私にウインクし、「TRUST ME (僕を信頼して)」と言った。それはずっと私が待っていた言葉なのだと、理解した。私は「YES」と声に出して返事をすることが出来たのか、もしくは頷いただけだったのか、今でもはっきりと思い出せないのだが、その後、一瞬にして安らかな眠りの海に落ちていった。
翌日から始まった抗癌剤とリンパ腫の治療薬であるライトキシン(リンパの腫瘍核のみに的を絞って攻撃する新薬)の投与は、驚くほど良く効いた。まず、1日目に抗癌剤を、そして2日目にライトキシンの点滴を受けた。
このライトキシンを投与した翌朝から、腹部で15cm近くに拡大し、石のように堅かった腫瘍の塊に触ると、それがボコボコと割れて分裂し、ゼラチン質のように柔らかく変化していた。まわりの医師や看護婦でさえもその効果の速さに驚いた。
但し、抗癌剤の副作用のせいか、私の状態は酷かった。発熱と滝のような発汗があり、髪から全身に至るまでぐっしょりと濡れ、1時間毎に、衣類、枕カバー、シーツを交換してもらった。さすがに夜中は申し訳ないと思ったが、一刻も早く替えてもらわないと悪寒を感じて唇がガタガタと震えだし、肺炎を引き起こしそうな予感がしたので、遠慮せずベッド横の呼び出しベルを鳴らした。真夜中でも看護婦さん達は嫌な顔一つせず全てを交換し体を拭いてくれた。時折、激しい辛さが波の様になって全身に押し寄せた。よくドラマで俳優が瀕死の病人を演じている時に“ウンウン”と呻きながら頭を左右に振っているが、あれと同じ状態になった。身体中が鉛のように重く、呼吸をする事さえ大変で、思わず頭を振ってしまうのである。そんな状態の時は、頑張るとか、生きたいとか考える余裕も無かった。ただ早くこの状態が終わる事を祈っていた。夜はほんの短い時間しか眠れず、やっと朝方眠りに落ちると、今度は数々の検査や薬の投与などで無理に起こされるのが辛かった。私の少し腫れぼったい奥二重の瞼はボコッと落ち窪んで完全な二重になった。おしゃべりな口は顎に力が入らず1cmも開かなくなり話すことが出来ないので、必要な用件は紙に書いた。主人や友人曰く、これが一番辛そうに見えたという。
しかし、一旦その状態が通り過ぎて落ち着いた状態が訪れると、私の身体を征服しようとしていた病が、少しずつではあるが後退しているような感覚を覚えた。

五十嵐ゆう子
JAC ENTERPRISES, INC.
ヘルス&ウェルネス、食品流通ビジネス専門通訳コーディネーター