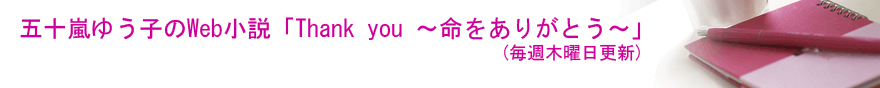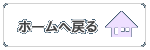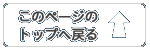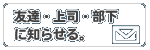〈第19話〉 砂漠の町、ラスベガスへの引越し
第7章 ―――― QUALITY OF LIFE
砂漠の町、ラスベガスへの引越し
やがて2年の月日が流れた。
カリフォルニアでエステティシャンとして働く私にも顧客が付き、なんとか人並みに稼げるようになってきた矢先、ラスベガスへ引っ越さなければならないという事実を突きつけられた。
主人が仕事を失い、新しく始めようとしていたビジネスも上手くゆかず、色々職探しをしたが給料やその他の条件が合わず、結局はラスベガスでの職に就かなければならない状態になったのである。
私の治療費やビジネスの失敗などで、家を担保にして借りた借金は4000万円以上に膨らんでいた。最終的に家を手放し、借金を返すことになった。
その当時のアメリカは、サブプライムローンの破綻問題が起こる以前の不動産バブル時で、ロサンゼルスにあった家の値段は購入時価値の倍以上に跳ね上がっていた。家を売り払い、借金を全て返しても、手元にはラスベガスの家を購入出来る頭金が残った。幸い、ラスベガスの家の値段は、高騰しているとはいえ、ロサンゼルス物件の半額だった。
街の景色が見渡せる高台にあり、1年中豊かな緑と花が咲きレモンやぶどうや苺が生ったロサンゼルスの家からすると、次に住む家は以前よりも小さく、砂漠の中にあり、緑が少なかったが、家族3人が暮らしていくには十分だと思った。
私はロサンゼルスの仕事を辞め、一から新しい土地でやり直さなければならなかった。
ナンシーのサロンでは、私のもとへ通うお客様達が私が居なくなることを残念に思ってくれ、「1ヶ月に1度でも良いからロスへ通うことは出来ないのか?」と打診してくれた。その言葉を聞いて本当に涙が出るほど嬉しかった。
私はその時から今に至るまで、月に1度、ロサンゼルスにあるナンシーの店まで往復約900キロの砂漠道を車で通っている。ラスベガスには日系大型食料品マーケットが無いので、仕事でロサンゼルスへ出向くついでに日本食材の買出しもしている。
余談ではあるが、ラスベガスへ越した直後、この砂漠道を家族3人でロサンゼルス出張から戻る途中、横転事故に遭った。深夜の雨の中を夫が140キロの高速で運転していて、水溜りに滑り、私達を乗せた車は路上を3回転半したのだ。車は路肩に激突し全損するほどの大事故だったが、家族3人は奇跡的に無傷だった。それ以来、事故に遭った場所では異常なほど慎重に運転して通っている。
引越しが落ち着いてからは、エステティシャンの仕事を探して、新聞の求人広告と毎日にらめっこした。フルタイムの従業員として給料制で雇い入れる店は少なく、殆どがスペースのレンタルだった。これはある程度の顧客が付いていないと毎月のレンタル料が払えなくなるので一から始める私には非常に不利であった。カジノホテルにはいくつかスパはあるが、マッサージ師の空きはあってもエステティシャンの空きは殆ど無かった。
ラスベガスのホテル王であるスティーブン・ウイン氏が新しくオープンしたカジノホテル内にスパがあった。そのエステティシャン部門に応募してみたが、面接もなく落とされた。後で聞いた話だが、このホテルのスパ経営陣は、ローカルの有名ホテルからエステティシャンを含む美容師達のベテランを引き抜いたそうである。
ラスベガスのホテルの求人に応募すると、履歴書とは別にホテル専用のアプリケーションへの記入が求められる。そこには、「そのホテルか、又は同じホテルチェーンに働く家族、又は知り合いはいるか?」の質問欄が必ず設けられており、そこに誰かの名を書き込める事が出来るか否かが雇用のキーポイントになるそうだ。実際に、ホテルが一般に求人する美容師の数は非常に少ない。従って、他所の土地から来てカジノホテルの職に就く事は容易ではない。
私は結局、地元にあるサロンの面接を受けた。月7万円ほどのフェイシャルルームレンタルだが、そこに長年働いていたエステティシャンがニューヨークへ引っ越すため、彼女の顧客を引き継いで欲しいという条件付きだった。この条件であれば一から顧客を築き上げなければならないという心配も無くなるので、家賃も払っていけるかもしれないと思った。なんとか彼女の眼鏡に適った私はそこで働き始めた。

息子の事と、私の心に残る傷
こうして仕事の方はなんとか落ち着いたものの、心配事はまだ他にもあった。
息子のユウキには、幼い頃から仲の良かった友達や小学校の学友と離れてしまうという悲しく寂しい思いをさせてしまった。明るく無邪気だった息子がそのために心を閉じ、あまり笑わなくなった。
しかし、親子3人で肩を寄せ合い明るく生きていけば、どんな場所でもどんな事でも乗り越えていけると信じていた。
近所にはユウキと同じ年頃の子供が居なかったので、まず私が友人を作り、同じ年頃の子供がいるお母さんに話して家へ遊びに来てくれるよう声を掛けた。
子供達が遊びに来てくれると、私は毎回クッキーを沢山焼き、冷たいミルクと共に振舞った。それでもユウキの心は長い間頑なに閉ざされていた。「また同じ子供たちを家に呼んであげようか?」と聞いても、ユウキは首を横に振るだけだった。彼も小学校の高学年に差し掛かる年で、少しずつ複雑に物事を考えるようになったためなのかと考えた。
引っ越して1年近く経っても、なかなかユウキの口から他の子供の名前を聞くことは無かった。まさかいじめに遭っているのでは?などと大袈裟に考え、学校の先生方に問い合わせて調査もしてもらったが、そういう事実は無いと言われた。
私がそういうことに敏感になるのには訳がある。私は小学校時代の一時期に、とても理不尽な理由でクラスの男子からいじめを受けた事があるのだ。時として残酷な行動に出てしまう未熟な子供達にとって、祖母に育てられた私は格好のいじめ対象となった。それにはいくつかの原因があった。
まず、私が小学校3年生の時に制服が全く新しいものに変わったのだが、明治生まれの祖母は無駄を嫌い、元の制服がまだまだ着れるという理由で私にそれを買い与えなかった。卒業するまで、1年生の頃に買った制服で過ごしたたのである。1年生の入学当時は長く着られるようにと、私の小さな体にはかなり大き過ぎる制服を着て通学した。
それから、祖母が作ってくれた遠足のお弁当は、おにぎり3個とゆで卵だけだった。それを同級生に見つからないようにいつも隠れて食べた。その事が恥ずかしかった私は、包丁が持てるようになった小学校3年生からは自分で弁当をこしらえた。
そして、極めつけは、女の子は冷やしてはいけないからと冬になると毛糸のパンツを履かされたのだが、小学生には渋すぎる灰色のパンツだった。こんなものが男子にばれたらまたいじめられると思った私は、ある日トイレでそれを脱いでそっと学校の裏にあったゴミ箱に捨てたのだが、どうもクラスの男子に見られていたらしい。その後、私の身の上に何が起こったかは想像にお任せする。
そして、今でも忘れられない、一番理不尽ないじめの原因となったある出来事がある。 何故、小学校であんな事が行われていたのか今でも信じがたいのだが・・・。
母の日になると、家に帰ったらお母さんに感謝しなさいという意味で、クラス全員に赤いカーネーションの花が配られた。母のいない私1人だけは白いカーネーションが与えられた。それがまたいじめられる理由の1つになった。学校の帰り道、悔しくてその白いカーネーションを思いっきり踏みつけ、ゴミ箱に捨てた。(だから今もカーネーションはあまり好きな花ではない。)それをまた誰かに見られていたのだ。学校から貰った花を無残な形にして葬り去った私へ浴びせられた『先生に言うたるぞ』 という言葉は、尖ったガラスの破片となって私の心に突き刺さった。
それでも、現代のいじめとは違い、クラス全員から総スカンをくらったわけではなかった。何人かの女子が男子の目を盗んで私を励まし、遊んでくれた。
しかし、いじめられたという経験は、子供時代に大きな傷を残す事は確かだ。私の大切な子供に同じ思いは決してさせたくはないし、いじめる側にも回って欲しくないと切に願う。けれど、もし、少しでもそんな兆候がユウキに起きることがあれば、私は全員を敵に回しても、彼のために戦う覚悟は出来ている。
少し偉そうな事を云わせて頂くと、親が子供を育てる時、しつけや勉強などを教える前に、自らの命を慈しみ同じように他の命を慈しむことを徹底的に教えてあげるべきだと思う。それは、最終的に大事な我が子を守る盾となると同時に、現代の社会問題となっている少年犯罪も減少するのではないかと思う。差別だってきっと無くなる。
ユウキが生まれた時、長年子供に恵まれなかった私達の喜びは喩えようもないほどで、誕生の瞬間に主人は涙を流した。その事はユウキが幼い頃から話し聞かせている。
「マミー、僕が生まれた時、ダーダ(主人のことをこう呼ぶ)は初めて泣いたんだよね。」
とユウキは事あるごとに繰り返し訊ねる。
「そうだよ。マミーもダーダもずっととユウキの事を待っていて、やっと逢えて嬉しかったんだよ。そやからユウキは、自分を大事にせなあかへんのやで。どの親もマミーらと同じような思いで子供を愛している。そやから他人を傷つけたらあかん。それだけは絶対忘れんといてな。」
このことがあるのか、ユウキは幼い頃から生き物や友達をとても大事にする。それは私にとって1番誇れる息子の性分だ。
ある日、息子に、
「新しい学校に仲の良い友達はいないの?自分から声をかけて、どんどん友達を作れば?」
と話し掛けたら、彼はこう言った。
「マミー、本当の友達を作るのはそんなに簡単なことではないんだよ。」
その言葉を聞いて、私は息子を理解出来ていないなと反省した。ユウキに友達が出来ない事を悩んでいるのは彼自身ではなく、私だったのだ。この子は自分なりに努力をして、この新しい場所で本当の友人を一から探し出そうとしているのだ。私は彼を信じて焦るらずに待ってあげるべきなのだと思った。
そんな息子も2年目に入る頃には仲の良い友人を作り、自分から家へ招待し始めたので、私の取り越し苦労という結果になった。
いやはや、長年待ってやっと恵まれた一人息子というものは、親にとってみれば時に常識を超えるほど気になってしまう存在なのである。いつの日かこの子が成長し私の手元を離れていくと想像するだけで、ドーンと寂しさを味わってしまう。困った親バカの私だ。
しかし、例えそういう日が来ても、ユウキが幸せになるのならそれも仕方がないと思う。我が子の笑顔は何事にも代え難いのだ。
ロサンゼルスの日本書店で、その頃ちょうど話題になり始めたリリー・フランキー氏の著書“東京タワー”を買って読んだ。リリーさんと亡くなられたお母様の、親子愛について綴られた、日本ではあまりにも有名なベストセラーを、息子へ向けられたオカンの気持ちと自分の思いを重ね合わせて読んだ。
リリーさんのお母様の命は、最終的に病気によって奪われてしまうのだが、彼女の想いは息子さんに100%伝わっていたし、最後までリリーさんの傍に居れて幸福だったと思う。亡くなった私の母も、きっとこんな風に私の事を愛してくれていたのだろうなぁ。だから、私が息子に対する深い愛情は、しっかりと母から私に受け継がれていたのだ。
私は机の上に飾られてある母の写真に訊ねた。
「そうやろ?お母さん。」
五十嵐ゆう子
JAC ENTERPRISES, INC.
ヘルス&ウェルネス、食品流通ビジネス専門通訳コーディネーター