〈第33話〉 ブルックリンの橋の上で
第11章 ―――― Thank You 命をありがとう
ブルックリンの橋の上で
グラウンドゼロを見学した後、未だ一度も訪れたことのなかったブルックリンへ向かうためにSUBWAY(地下鉄)のFラインに乗って、Yorkという駅で下車した。屋外へ出ると、橋の袂に100年以上前に建てられたであろうレンガ造りの倉庫を居抜きにし、アートギャラリー、ブティック、本屋等の店舗が造られていた。

寂れて治安も良くなかったこの地域を再開発し、ビジネスオフィスやアートディストリクトとして生まれ変わらせたプロジェクトをDUMBO(Down Under Brooklyn Bridge Project )と呼び、土地代が高額なマンハッタン島から若いアーティスト達が移り住んでいるらしい。

一度聞いたら忘れられないユニークな名称に興味を抱いたことと、美味しい手作りのチョコレート屋があるという噂につられて来た私は、すっかりこの個性的な地区の虜となった。道行く人に尋ねながら例の手作りチョコレート屋を見つけて、お土産を買った。そして、チョコレート屋の向かい側に偶然見付けたフランス人が営むケーキ屋で、フルーツが山盛りに乗せられたケーキとカフェラテを注文し、ショーケースの前に置かれたテーブルセットに腰掛けて休憩した。一切れのサイズが日本の倍はあるケーキだったが、とても美味しく、あと昼食を食べていなかった事もあり、ペロッと平らげてしまった。店の名刺を貰うのを忘れなんという店か覚えていないのだが、またいつかブルックリンへ行ったらこの店を探してみたいと思っている。(この5月に再度訪問した際に、そこはアマンディーユという名であることが判明した。写真を載せたので、もしブルックリンへ行く機会があれば寄って見て欲しい。)

帰りは、マンハッタン方向へ向かうSUBWAYに乗るはずだったが迷ってしまった。結局、ブルックリン橋を歩いて渡る事にした。10月だというのに気温は30度近くあり、夕方近くになっても蒸し暑さは一向に改善されなかった。この時期のニューヨークは涼しいからと聞かされ、1枚も半そでを持ってこなかった事を後悔した。私は長袖シャツの腕を捲くり、汗で足に張り付いたロングパンツを指で摘み上げ中に風を通した。タンクトップとショートパンツで颯爽と自転車に跨る赤毛でショートヘアーの若い女の子を横目に、流れる汗を拭いながら部屋に忘れてきた地図を思い出し、「あれさえ持参していれば、ブルックリンから地下鉄に乗れたなあ。」と自分の物忘れを反省して呟いた。

橋のちょうど真ん中あたりまで差し掛かったところで、ペットボトルにわずかばかり残っていた生暖かい水を取り出し、欄干にもたれて飲み干した。実は、この橋を渡る前、道に迷い始めた頃から、グラウンドゼロで自らに問いかけた事について考え続けていた。というよりも、セドナから戻って来てからずっと心の奥底に存在してきた大きな宿題であるような気がしていた。
“病の床から立ち上がった私は、統合的なヘルス&ウエルネスの提供機関の実現に携わるという夢を抱いた。しかし、私はその夢に何処まで近づく事が出来ているのか? 自分の体験を人々とシェアーすることや、私が闘病を通して本当に伝えなければいけない事を、まだ形にさえ出来ていないのだ。”
私はあせりと苛立ちで泣きたい気持ちになった。うだるような暑さと足の疲れも、沈む気持ちを更に重くしていた。足元を見つめながら一歩、一歩、歩き、一体どのあたりまで来ているのかわからなくなってぼんやりと前を見つめた。その時、このブルックリン側から真正面に見えたマンハッタンが夕焼けに染まり、とても美しいことに気付いて立ち止まった。目の前に広がる景色は大自然とはまた違い、もっと身近で躍動的な感じがして、人が生活する息遣いや匂いがあった。それは、あの同時多発テロの大惨事から立ち上がり再び蘇った力に満ちた美しさであり、混沌とした経済状況さえもきっと打破出来ると確信させる光景だった。
15年前に初めてマンハッタンを見て感動した以上の思いが溢れてきて、私は目の前に広がる街に完全にノックアウトされていた。ずっと自分のイメージの中にあったマンハッタンの摩天楼とは異なっていた。ここから見える街は、まるでおもちゃ箱をひっくり返したようにごちゃごちゃと賑やかで、圧倒されるような力で満ち溢れている。私が道に迷わなければこんな光景を見るチャンスは無かったのだ。方向音痴もまんざら悪くはないなと思った。
「ああ、私達の生きるこの世界はなんて素敵なのだろう。そして、そのことをいつも私に気付かせてくれるのは一体誰の仕業なのだろう?」と、考えた。
私はその時、前の晩にブロードウェイで観劇した“カラーパープル”というミュージカルの演目を思い出した。ベストセラーになりピューリッツア賞〔米国で出版物に与えられる最も権威ある賞〕を受賞したこの物語は、1985年にスピルバーグ監督によって映画化もされている。物語は、主人公の貧しい黒人女性が学校にも通えず、実の父親から暴力と性的虐待を受け、身篭った子供を取り上げられ、母を失い、妹と引き裂かれ、暴君のような夫にも虐待されながらも、生きて、生き抜いて困難と立ち向かい、やがてたった一人で自分の人生を切り開いく様子を、彼女が”Dear God,”と呼びかける心の中に居る神様と、届くあてがなくても書き続けた妹への手紙で綴られていた。そしてその妹へ書き続けた手紙の束が第三者に発見されることにより、大きく人生が開かれていくのだ。私の脳裏に、物語のクライマックスで主人公の女性が謳い上げる感動的な一節が再現された。
“私は貧しく、黒人で、
決して美しいとは言えない。
でも、私はこの場所にしっかりと立ち生きている。
私は素晴らしい、
そう、素晴らしい人間なんだ!”
与えられた運命が何であれ、それにキスして抱き締めて、ゼロの状態をプラスに転化させていく、そんな風に人生を歩んで行きたいと思った。一度は死と背中合わせだった私が再び健康になり、こうして再びニューヨークへ来ることが出来た今、ブルックリン橋の上で煌くマンハッタンを目の前にして、その素晴らしい景色とエネルギーを全身で感じている。私はこれからも、もっと夢を見て実現させていくことが可能なのだ。だって、こうして生きているというだけで、100%の可能性とオポチュニティー(機会)が与えられているのだから。
『サンキュー、命をありがとう!』
心の中でそう叫んだ。今、自分が感じている生きる喜びを、もっと多くの人々に知って欲しいと強く願った。体験の記録や自分の考えていることを文章にまとめ、沢山の人に発信する事。それが今の私に与えられた最初にやるべき仕事なのだと直感した。
“そうだ、私にもきっと出来る事がある!”そう思うと、体の底から喩えようのないエネルギーが沸いてきて、私はマンハッタン目がけて駆け出していた。

五十嵐ゆう子
JAC ENTERPRISES, INC.
ヘルス&ウエルネス、食品流通ビジネス専門通訳コーディネーター

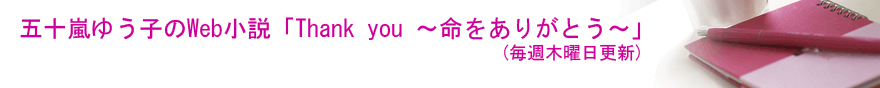

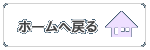
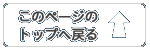
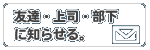
2 件のコメント
「生きているだけで、可能性と機会がある」という言葉は、なかなか言えない言葉だと思います。大変な苦労をして生き抜いてきた人だけが、言い切れる素晴らしいフレーズではないかと。ゆう子さんの思いを共有し、共感している人は、沢山いるのではないでしょうか。少なくとも私は、そうでしたよ。感謝。
この言葉は、同時多発テロや、病や、事故などで
生きたくても、生きることの出来なかった全ての方々を
代弁した言葉なのです。
今この瞬間に生きているという”素晴らしいギフト”を忘れないために
心の灯を、私も、そして読者の方々も消さないようにとの願いから
出てきた言葉なのです。