万代知識商人大学10期開講と「Knowledge Merchant」の由来

万代知識商人大学。
2016年に企業内大学として開講した。
日本のスーパーマーケットでは、
初めてのことだった。
当時の加藤徹社長、
現万代リテールホールディングス会長が、
当時の河野竜一人事部長に語った。
「技術を磨く場所はすでにできた。
知識を磨く場所をつくろう」
私がご指名を受けて、
加藤理事長、結城義晴学長の体制で、
静かにスタートした。
今、10年の節目を迎える。
開会のあいさつは和久正樹取締役。
正しいモノサシをもち、
「質のいい売上げ」をつくる。
そのための学習であることを強調。

いつものように、
企業内大学の歴史と意味を語る。
1956年、ゼネラルエレクトリック社が、
世界で最初の企業内大学を創設した。
通称「クロントンビル」。
その後、世界中の名だたる企業が、
次々に企業内大学を設立して、
将来の幹部候補生を養成した。
マクドナルドの「ハンバーガー大学」
ウォルトディズニーの「ディズニー大学」
日本では「トヨタインスティテュート」
小売業では、
「ジャスコ大学」が一番早かった。
ファーストリテイリングも、
2010年から「FR-MIC」を開始。
ファースト・リテイリング・マネジメント&イノベーション・センター。
万代は「知識商人大学」と名づけた。
ナレッジ・マーチャント・カレッジ。
とてもいい。

そのスローガンは、
「Big Thinker」になること。
大きな視野と視点をもつ人。
「着眼大局着手小局」である。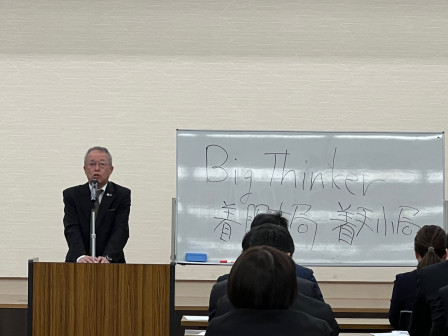
そして1年間学んでいく、
マネジメントの体系を説明した。
万代のミッションを改めて確認する。
創業からの歴史と事業の変遷を、
スライドを使って話した。

このあと開講式に出席した取締役が、
一言ずつ受講生への期待を語った。
河野竜一常務取締役。
マネジャーとしての在り方を語り、
「人のため」に学べとアドバイスした。
吉田秀史常務執行役員。
「プラスの力を持ち続けることが大事」

谷内(やち)毅取締役。
大谷翔平選手の努力を事例に、
「勝つことが正義、そのために学べ」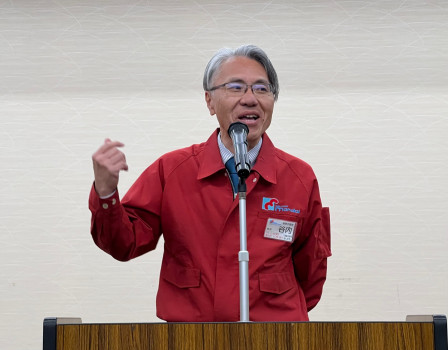
9時から始まった開講式は11時に終了。
そして第1回講義。
テーマは「ミッションマネジメント」。
はじめはいつも、
倉本長治とピーター・ドラッカー。
IntegrityとInnovationとMarketing。
最後にこの大学の命名の由来。
「知識商人」という言葉のヒントは、
ドラッカーの『ポスト資本主義社会』にある。
商人舎を設立してすぐに、
私は緑内障の大手術を受けた。
その病床に、予約していたこの本が届けられた。
この本の中に出てきたのが、
「knowledge worker」や、
「knowledge specialist」、
「knowledge manager」である。
私の手術では、
東邦大学の富田剛司教授が執刀医だった。
それ以外にも看護師さん、栄養士さん、
病院で仕事をするのはみんな、
「knowledge」の人々だった。
私は商売をする人たちも同じだと思った。
そして「knowledge merchant」という言葉を思いついた。
このknowledgeは、
日本語では知識と知恵と技術が、
完全に融合されたものだ。
そんな知識商人になってほしい。
昼がやってきてランチ。
その後は受講生一人ひとりが、
2分間スピーチをする。
1年間の目標を掲げて決意表明した。
ミッションとは「使命」「理念」のことだ。
それを説明するために、
パワーポイントを使って、
「凡事徹底と有事活躍」の事例を語る。
最後は「人間力経営」。
心の力と頭の力と技の力の積が、
人間力である。
最後に論文やレポートの書き方。
結城義晴の文章法をシンプルに教えたあと、
話し方・語り方のエッセンスを語った。
1年間の研修の間に、
自分なりの書く力・話す力を、
身に着けてほしい。
ミッションマネジメント講義の最後は、
阿部秀行社長の総括。
万代カレッジでは、
商売につながる「賢さ」を学ぶ。
そして、回りの人の長所を伸ばせる人になれ。
阿部さんの話はいつもわかりやすい。
その熱いメッセージを真剣に聞く受講生。

10期生にとっては緊張の連続の、
長い一日だった。
阿部社長も結城義晴も、
10期生の真剣な学習と、
その実践・実行に期待したい。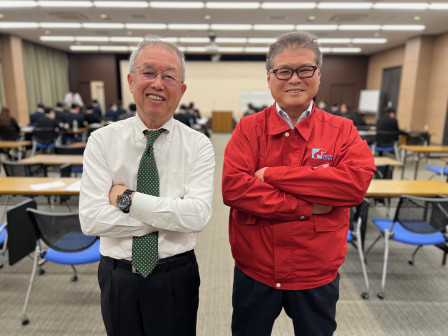
10期生の選定に携わった和久取締役。
いわば今年のプロデューサー。
今日も終日、講座を見守ってくれた。
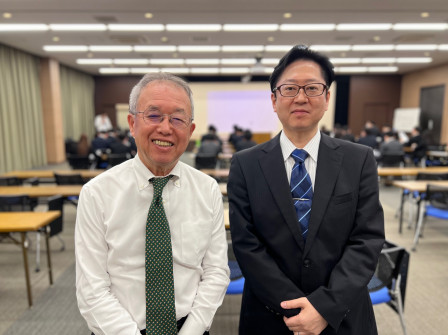
万代知識商人大学第10期、
始まりました。
よろしく。
〈結城義晴〉









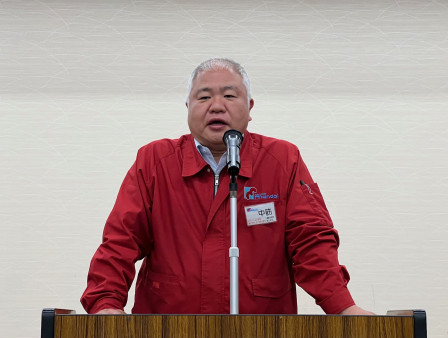






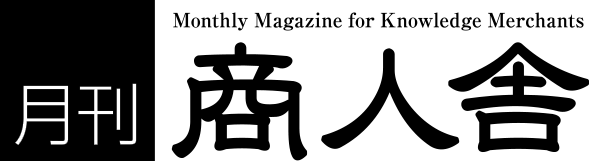
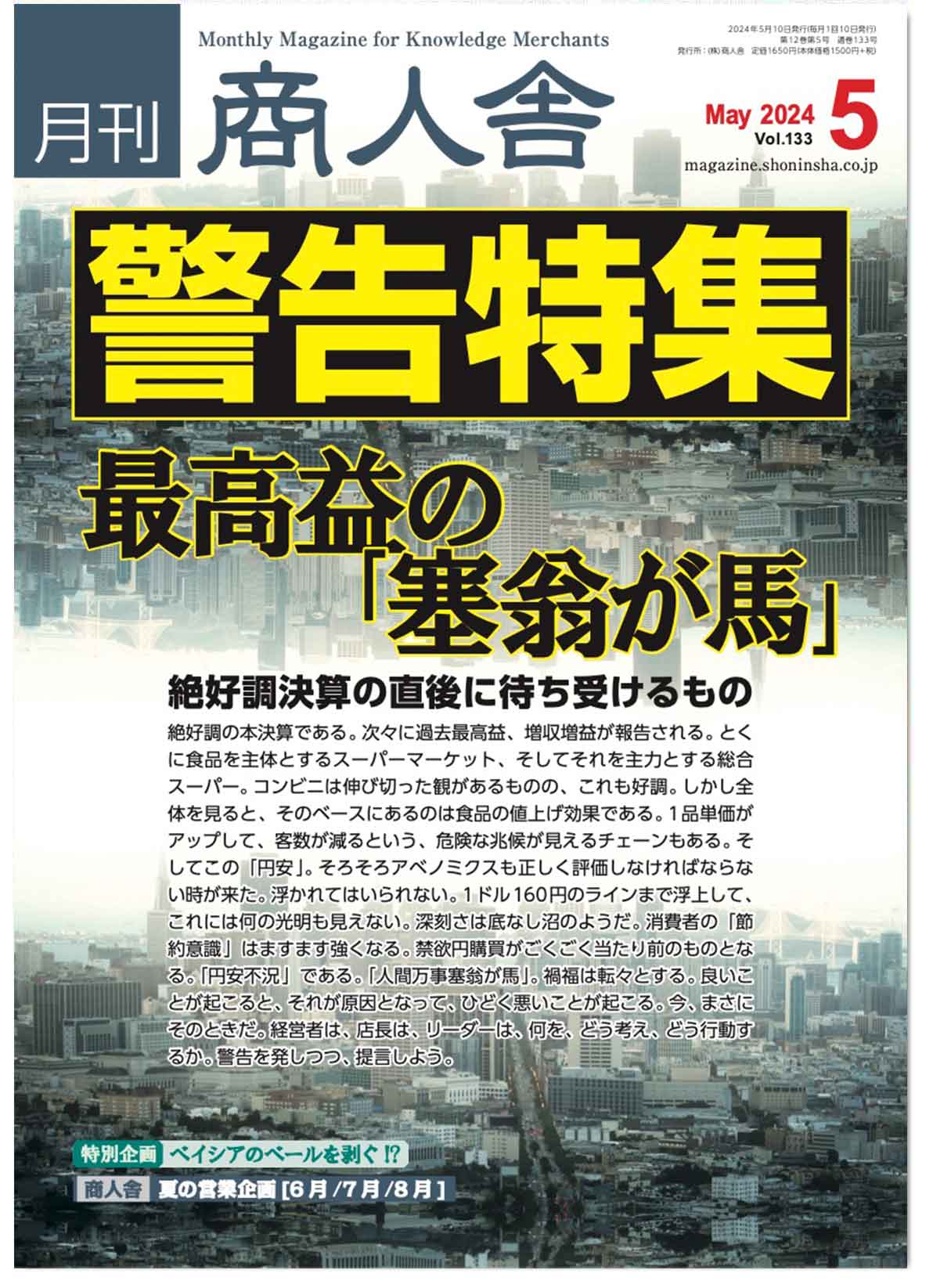









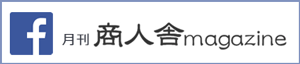

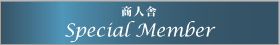
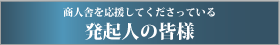
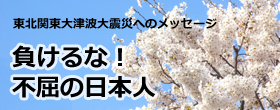




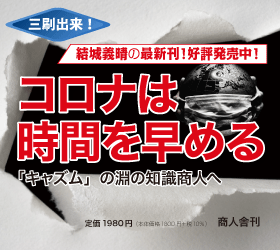
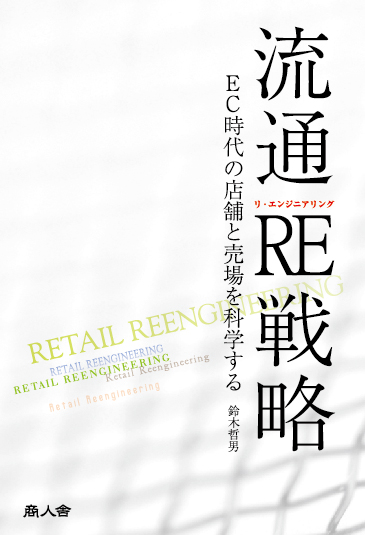
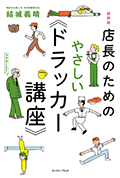
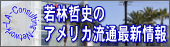



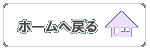
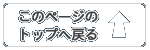
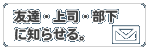

2 件のコメント
「知識商人」という結城さんの造語の定義は何だろうといつも思っていました。もちろん、単なる物知りでもないですし、いわゆる商売上手とも違います。
鳥の目、虫の目、魚の目を持つマーケッター、というのが、わたしのイメージです。
吉本さん、ありがとうございます。
ドラッカーは知識労働者をこう表現します。
「マーク・トウェインが1889年に書いた小説の主人公、
コネティカット出身のヤンキーは
教養ある人間ではなかった。
ラテン語もギリシャ語も知らず、
シェイクスピアを読んだこともなく、
『聖書』もほとんど顧みなかった。
しかし彼は、機械のことなら、
電気を起こすことから電話機をつくることまで、
すべて知っていた」
私はこう表現しています。
「商売のこと、商品のこと、お客様のこと、地域のこと。
これらを誰よりもよく知っている専門家。
それが、知識社会時代の知識商人である」