アーベル賞受賞・柏原正樹とその師匠・佐藤幹雄の「代数解析学」

野辺に咲く花。
ハナニラ。
英語ではSpring starflour。
丈夫で手間いらずな花。
だから植えっぱなしでも、
3月から4月に花を開かせる。
これは藤青色だが、
ピンクや白もある。
星形の花をよく咲かせる。
葉や球根を傷つけると、
ニラやねぎのような匂いを放つ。
秋に球根で売られている。
あるいはポリポットの苗でも手に入る。
歩いていて足元に咲く花に気がつく。
それがハナニラだ。
朝日新聞「天声人語」
「アーベル賞受賞」の話題。
数学界のノーベル賞と言われる。
京都大学特定教授の柏原(かしわら)正樹さんが受賞。
78歳。

偉業だ。
数学は3つの分野に分かれる。
代数学と幾何学、そして解析学。
私が中学生のころの数学の授業は、
代数と幾何に分かれていた。
代数は鳥羽先生、幾何は吉田先生。
懐かしい。
つまり中高で代数と幾何を学んだ。
それに「解析」が加わる。
解析は「極限」や「収束」といった概念を対象とし、
その基礎は微分学積分学だ。
高校の授業では通常、
数1と数2を教える。
これが代数と幾何。
初歩的な微積分は数3に入っていて、
私は大学に入ってから、
講義を選択して勉強した。
柏原教授の研究は、
解析学の分野に属しながらも、
代数学や幾何学の3分野すべてに関わり、
さまざまな数学の分野に応用されてきた。
柏原さんの師匠が故佐藤幹夫さんだ。
京都大名誉教授で、
「代数解析学」を創始した学者。

「xがyより大きい」という不等式の数学が解析。
「x=y」という等式の数学が代数。
佐藤さんは「解析」を「代数」のように、
等式でスマートに考えられることを発見。
解析の微積分をかけ算や割り算のように、
自由に扱えるようにした。
これが複雑な微分方程式を解く手法となった。
しかし佐藤さんは論文を書かない研究者だった。
そのかわりに弟子たちが、
細部を詰め、証明し、形にしていった。
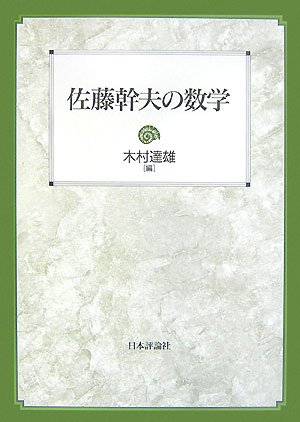
弟子たちは「佐藤スクール」と呼ばれ、
1970年代以降の日本の数学界を牽引した。
柏原さんがその代表だ。
東大在籍中に、佐藤さんの講義を聴いた。
「場外ホームラン級のアイデア」と触発され、
佐藤さんのあとを追って京大へ。
京大数理解析研究所3階の佐藤さんの研究室で、
連日のように黒板に式を書いて議論した。
佐藤さんは代数解析学を、
「D加群(D-module)」と名づけて、
構想をつくった。
微分を英語でDifferentiationという。
D加群の命名にはこの頭文字のDが使われている。
それを柏原教授が基礎から確立した。
代数と解析が融合し、それが幾何をはじめ、
分野の垣根を越えて現代数学の発展に広く貢献した。
物理学や情報科学などにも影響を与えた。
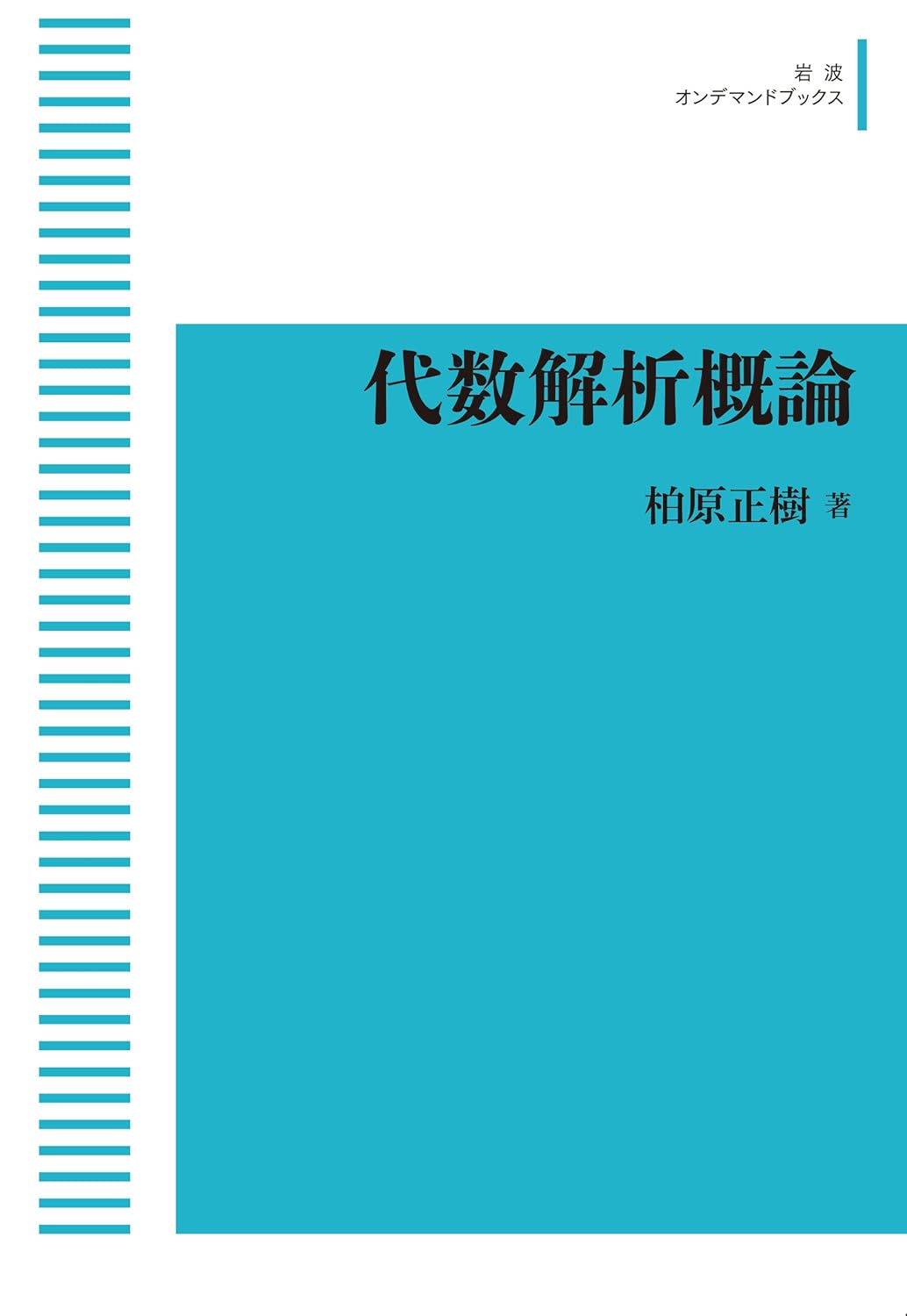
アーベル賞は2003年にノルウェー政府が始めた。
ノルウェーの数学者ニールス・アーベルの名を冠した。
ノーベル賞に匹敵する数学の科学賞だ。
これまでアーベル賞受賞で有名なのは、
2015年のジョン・ナッシュ氏、
2016年のアンドリュー・ワイルズ氏。
ナッシュ氏はゲーム理論の研究で、
ノーベル経済学賞も受賞。
ワイルズ氏は数学の超難問を証明した。
「フェルマーの最終定理」。
柏原教授は彼らに並ぶ功績と評価された。
ノルウェー科学文学アカデミーの選考の評。
多分野の研究をつなぐ柏原さんの「独創的な思考」は、
まるで「日本と南極を結ぶ橋」のようだ。
柏原さんが学んだ「佐藤スクール」の言葉。
「朝起きたときに、
きょうも一日数学をやるぞと
思っているようでは、
とても、ものにならない」
「数学を考えながらいつの間にか眠り、
目覚めたときにはすでに数学の世界に
入っていないといけない」
私はこの言葉に感動した。
こんな心境で、
仕事や商売に打ち込んだら、
凄いことができそうな気持ちになってくる。
㈱万代社長の阿部秀行さんの若いころ。
キャベツを売り切るアイデアを考えついたら、
「夜も眠れず朝が待ち遠しかった」
「佐藤スクール」に通じるものだ。
一心に仕事のことを考えながら、
眠りについてみることにしよう。
〈結城義晴〉

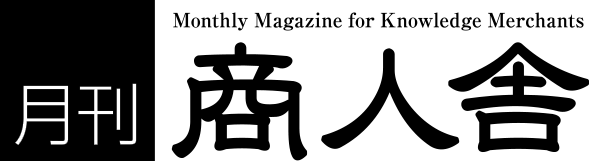
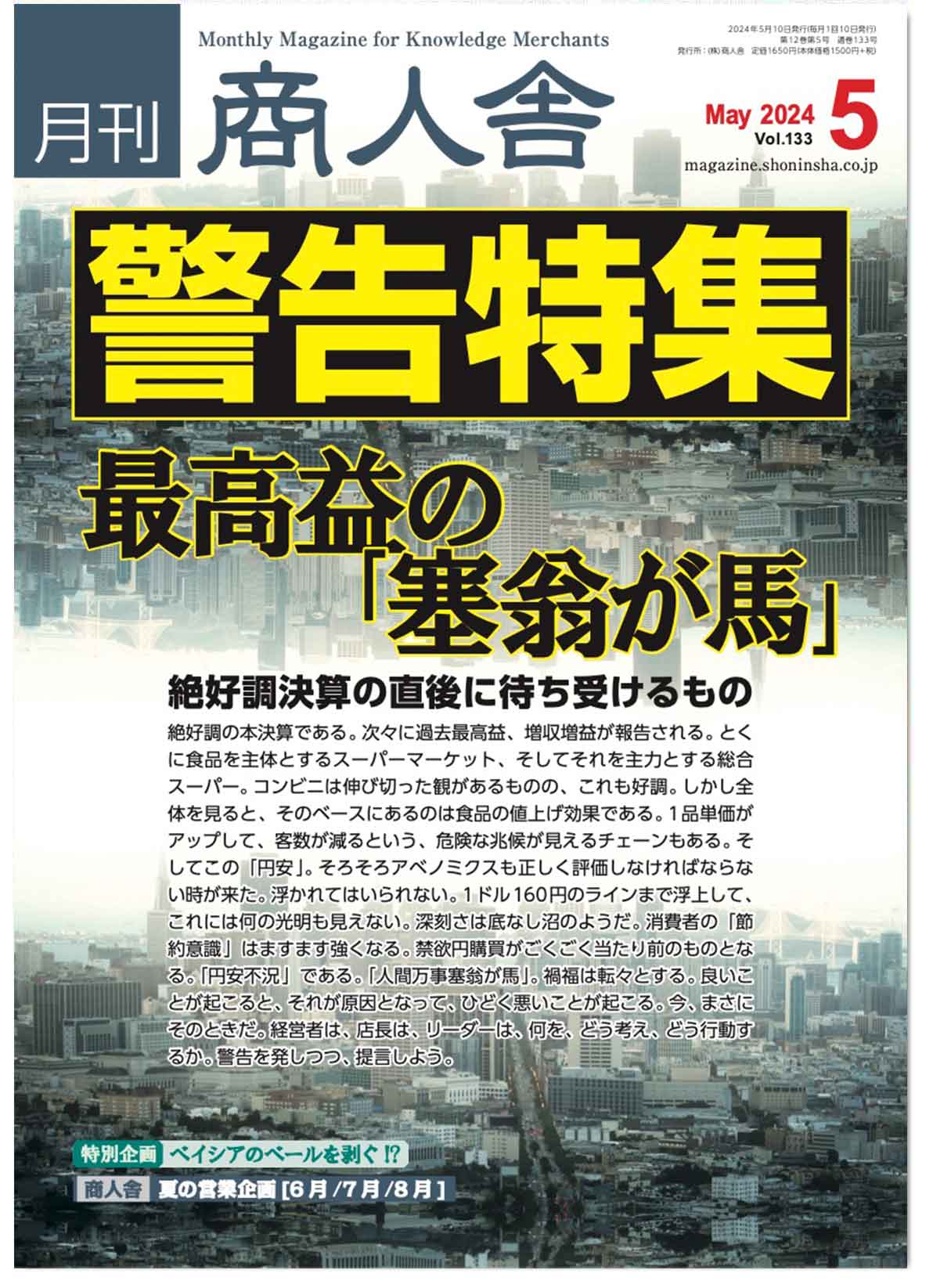









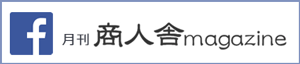

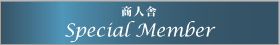
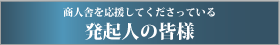
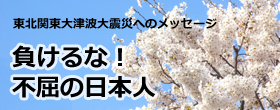
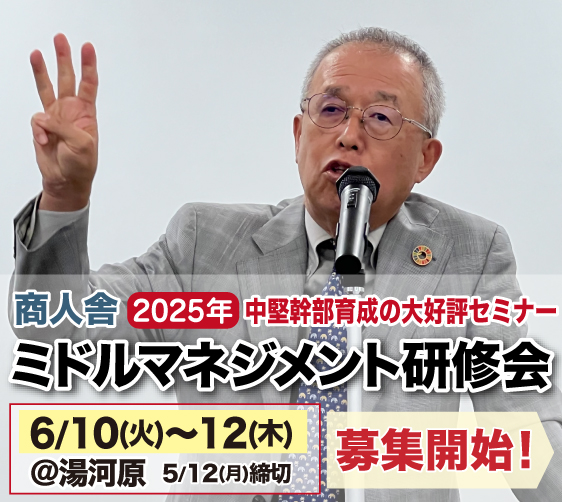



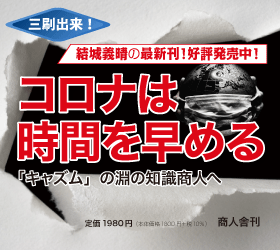
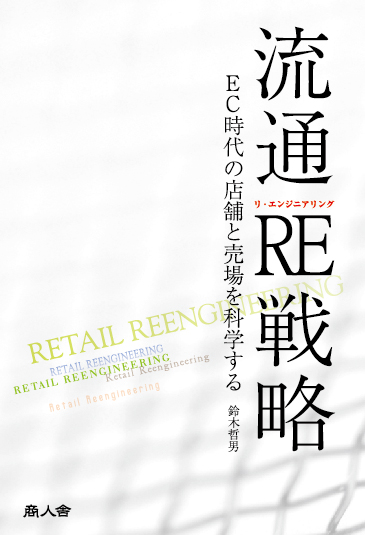
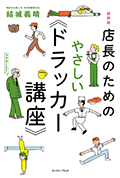
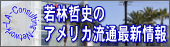



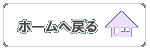
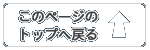
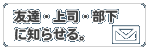

1 件のコメント
眠ってる最中に閃くこともよくありますね。そういう時のために、昔は枕元にペンと手帳を(今はスマホですが)、置いてました。